動画コンテンツ制作とは?企業向けの制作方法から費用・外注先まで徹底解説

「動画コンテンツを制作したいけど、何から始めればいいかわからない」
「自社制作と外注、どちらを選ぶべき?」
「動画コンテンツ制作にはどれくらいの費用がかかるの?」
動画コンテンツは、現代のマーケティングにおいて欠かせないツールとなっています。
しかし、動画の種類や制作方法の選択を誤ると、期待した効果が得られないだけでなく、無駄なコストがかかるリスクもあります。
この記事では、動画コンテンツの基本的な定義はもちろん、企業にとっての意義や具体的な制作方法、そして信頼できる外注先などについて詳しく解説しています。
最後まで読めば、自社に最適な動画コンテンツの活用方法がわかり、効果的な動画マーケティングが実現できるでしょう。
1.動画コンテンツとは?
![]()
動画コンテンツとは、情報提供や娯楽の提供のためにつくられる動画のことです。
視覚と聴覚に同時に訴えかけることができるため、文字や画像だけのコンテンツよりも高い情報伝達力を持っています。
特に企業が活用する動画コンテンツに関して押さえておくべきトピックは、以下の通りです。
- 動画コンテンツの定義
- 動画コンテンツの種類
順に見ていきましょう。
(1)動画コンテンツの定義
動画コンテンツは、映像と音声を組み合わせて情報を伝える媒体です。
企業においては、商品・サービスの紹介、ブランディング、採用活動、社内教育など、様々な目的で活用されています。
動画は静止画やテキストと比べて、約5,000倍の情報量を伝えることができるといわれており、効率よく情報を伝達できるのが特徴です。
また、スマートフォンの普及により、いつでもどこでも動画を視聴できる環境が整ったことも、動画コンテンツの重要性を高めています。
さらに、YouTubeやTikTok、Instagramなど、動画配信プラットフォームの多様化により、企業が動画を活用する機会は飛躍的に増加しました。
その結果、現代のマーケティング戦略において、動画コンテンツは必須のツールとなっているといえるでしょう。
なお、企業がYouTube動画を活用するためのポイントや活用事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)動画コンテンツの種類
企業が制作する動画コンテンツには、目的やターゲットに応じて様々な種類があります。
それぞれの動画は異なる役割を持ち、適切に使い分けることで最大の効果を発揮します。
- 商品やサービス紹介
- 採用動画
- 動画広告
- ブランディング動画
- マニュアルや教育動画
以下、主要な動画コンテンツの種類とその特徴について詳しく解説します。
#1:商品やサービス紹介
商品やサービス紹介動画は、既存ユーザーや見込み顧客をターゲットとした動画です。
製品の特徴や使い方、メリットを視覚的に伝えることで、購買意欲を高める効果があります。
例えば、複雑な機能を持つソフトウェアでも、動画で実際の操作画面を見せることで、ユーザーの理解を促しやすくなります。
また、実際の使用シーンを映すことで、顧客は商品を使った際のイメージを具体的に持つことができるでしょう。
加えてお客様の声や使用事例を動画化することで、信頼性も高められます。
その結果、静止画やテキストだけでは伝えきれない商品の魅力を効果的にアピールすることが可能です。
#2:採用動画
採用動画は、求職者をターゲットとして、企業の魅力や働く環境を伝える動画です。
テキストや写真だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や社員の人柄を、リアルに表現することができます。
具体的には、社員インタビューやオフィスツアー、一日の仕事の流れなどを映像化します。
また、企業理念やビジョンを動画で表現することで、求職者との価値観をマッチングさせて、短期離職の予防も可能です。
さらに、新卒採用と中途採用で異なる動画を制作することで、それぞれのターゲットに適したメッセージを発信できるでしょう。
採用動画を活用することで、ミスマッチを防ぎ、質の高い人員の獲得につながります。
なお、採用動画の種類や制作の流れ、活用事例については以下の記事も参考になります。
#3:動画広告
動画広告は、潜在顧客や新規顧客をターゲットとした、認知拡大を目的とする動画です。
YouTubeやSNSの広告枠、デジタルサイネージなど、様々な媒体で配信されます。
短時間で印象に残るメッセージを伝える必要があるため、インパクトのある演出が求められます。
例えば、最初の5秒で視聴者の興味を引く構成にすることで、スキップ率を下げて動画の内容をじっくり見てもらうことが可能です。
また、ターゲティング広告と組み合わせることで、特定の層に効率的にリーチでき、従来のテレビCMよりも費用対効果の高い広告展開が可能となっています。
動画広告の中でも、YouTube動画広告の特徴やメリット、制作の手順などの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
#4:ブランディング動画
ブランディング動画は、幅広いターゲットに対して企業イメージの向上を図る動画です。
企業の歴史や理念、社会貢献活動などを感動的に描くことで、ブランド価値を高めます。
直接的な販売促進ではなく、長期的な視点でファンを獲得することが目的の動画で、ストーリーテリングの手法を用いることで、視聴者の感情に訴えかけることができるでしょう。
さらに、一貫したブランドイメージを動画で表現することで、企業の信頼性も向上します。
ブランディング動画は、企業と顧客の絆を深める重要なツールといえるでしょう。
#5:マニュアルや教育動画
マニュアルや教育動画は、自社の社員や顧客をターゲットとした、知識や技術の伝達を目的とする動画です。
文字だけのマニュアルと比べて、複雑な作業も視覚的に理解しやすくなります。
例えば、機器の操作方法や業務フローを動画化することで、習得時間を大幅に短縮することが可能です。
また、何度でも繰り返し視聴できるため、自分のペースで学習を進められるというメリットもあります。
さらに、新入社員研修や製品の使い方説明など、幅広い用途で活用でき、教育にかかるコストを削減できるのもメリットです。
教育動画の活用により、教育コストの削減と学習効果の向上を同時に実現できるでしょう。
2.企業にとっての動画コンテンツ制作の意義

動画コンテンツは、企業の様々な課題を解決する強力なツールです。
具体的には、以下のような意義・メリットがあります。
- 顧客との接点を創出できる
- 採用フローを効率化できる
- 視聴者に向けて比較的低コストで広告を出稿できる
- 未獲得の顧客層に向けて自社の認知を高められる
- 社員教育や研修の手間を省ける
順にご説明します。
(1)顧客との接点を創出できる
動画コンテンツは、顧客との新たな接点を生み出す効果的な手段です。
SNSやYouTubeなど利用者が多く、さらに顧客が日常的に利用するプラットフォームで自然な形で露出できます。
例えば、有益な情報を提供する動画を定期的に配信することで、顧客との継続的な関係を構築することが可能です。
また、コメント機能を活用すれば、双方向のコミュニケーションも可能になるでしょう。
さらに、動画の視聴データを分析することで、顧客の興味や関心を把握することもできます。
(2)採用フローを効率化できる
動画コンテンツの活用により、採用活動の効率が大幅に向上します。
企業説明会の内容を動画化すれば時間や場所の制約なく情報提供ができ、24時間いつでも自動的に求人活動をする役割を果たします。
具体的には、会社概要や仕事内容を動画で事前に共有したり、よくある質問を動画化することで、応募を促進したり、会社説明会に参加する求職者の理解を深めることが可能です。
また、応募者も事前に企業理解を深められるため、ミスマッチの減少にもつながるでしょう。
採用動画の活用は、採用コストの削減と質の向上を両立させる効果的な手法となっています。
(3)視聴者に向けて比較的低コストで広告を出稿できる
動画広告は、従来のマス広告と比較して低コストで効果的な広告展開が可能です。
これは、ターゲティング機能により、興味を持つ可能性の高い層にピンポイントで配信することができる点に理由があります。
例えば、YouTubeやFacebook広告では、年齢や性別、興味関心などで細かくターゲットを設定できます。
また、少額から始めることができるため、中小企業でも動画広告を活用しやすいのもメリットです。
さらに、効果測定も容易なため、PDCAサイクルを回しながら最適化を図ることができるでしょう。
その結果、限られた予算でも高い費用対効果を実現できます。
(4)未獲得の顧客層に向けて自社の認知を高められる
動画コンテンツは、これまでリーチできなかった新たな顧客層の開拓に効果的です。
特にYouTubeなど利用者の年代が幅広いSNSを通じて、今まで自社のターゲットではなかった年齢層の顧客に動画を閲覧してもらえる可能性があります。
反対に若年層が多く利用するTikTokやInstagramでの動画配信により、新しい世代へのアプローチも可能になります。
バイラル効果により、想定を超えた拡散が起こることもあり、その場合は自動的にSNSが広告宣伝を担ってくれこともあるでしょう。
動画を通じて、従来の枠を超えた顧客層へのアプローチが実現できることからも、自社認知の拡大に動画マーケティングは有効です。
(5)社員教育や研修の手間を省ける
教育動画の活用により、社員研修の効率化と標準化が実現できます。
一度制作した動画は何度でも使用でき、講師の時間や労力を大幅に削減できるからです。
例えば、新入社員向けのオリエンテーション動画を作成すれば、毎回同じ品質の研修を提供することができます。
また、eラーニングシステムと組み合わせることで、学習進捗の管理も容易になるでしょう。
さらに、業務マニュアルを動画化することで、理解度の向上と習得時間の短縮が期待できます。
3.動画コンテンツを制作する方法

動画コンテンツの制作方法は、大きく分けて自社制作と外注の2つがあります。
- 自社で内製する
- 制作会社へ外注する
それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や予算に応じて選択することが重要です。
(1)自社で内製する
自社での動画制作は、費用を抑えながら動画コンテンツを始めたい企業に適しています。
特に、社内向けの動画など、高いクオリティが求められない場合は、まず自社制作から始めるのも良いでしょう。
最近では、スマートフォンでも高画質な動画が撮影でき、無料の編集アプリも充実しています。
社員インタビューや簡単な商品紹介動画なら、特別な機材がなくても制作可能です。
また、自社制作なら修正や更新も柔軟に対応でき、スピーディーな配信ができます。
ただし、プロレベルの品質を求める場合は、相応の機材投資と技術習得が必要になり、さらに担当者の時間的負担も考慮する必要があります。
(2)制作会社へ外注する
プロの制作会社への外注は、高品質な動画を確実に制作したい場合に最適です。
専門的な技術とノウハウを持つプロが、企画から納品まで一貫してサポートしてくれるため、高品質な動画を手間なく制作することができます。
例えばターゲットの分析や市場調査から、動画構成の作成や演出の提案、撮影から編集まで幅広い範囲の委託が可能です。
撮影機材や編集ソフトなども最新のものを使用するため、クオリティの高い仕上がりが期待できるでしょう。
さらに、マーケティング視点でのアドバイスも受けられるため、効果的な動画制作が可能です。
費用は高くなる傾向にあるものの、ブランドイメージを左右する重要な動画の場合は、外注を検討するのがおすすめです。
4.動画コンテンツの制作費用相場

動画コンテンツの制作費用は、種類や内容によって大きく異なります。
一般的に、動画制作費用の中央値は80万円程度といわれていますが、実際には10万円から500万円以上まで幅があります。
例えば、簡易的な編集のみなら10万円程度から可能ですが、TVCMレベルの動画では数百万円を超えることもあります。
費用の内訳としては、企画構成費、撮影費、編集費、ナレーション費、ディレクション費などが含まれ、動画の内容によって大きく費用が変動する点に注意しましょう。
詳しい費用相場については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
5.動画コンテンツ制作の流れ
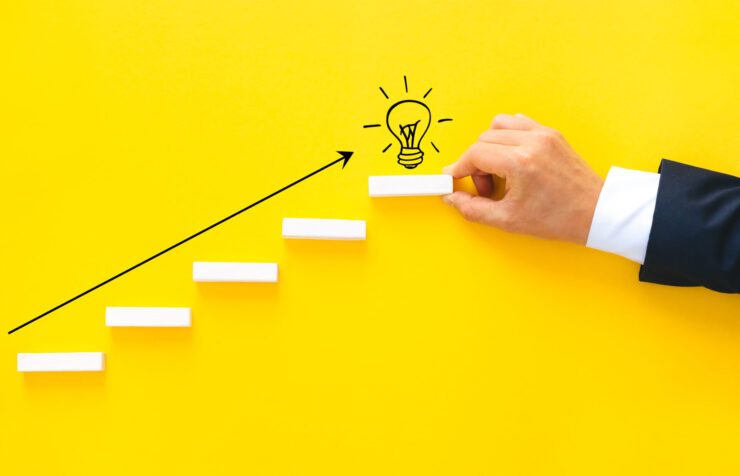
効果的な動画コンテンツを制作するには、体系的なプロセスを踏むことが重要です。
具体的には、以下の流れに沿って進行します。
- 制作する動画コンテンツの種類を選ぶ
- コンテンツの制作方法を決める
- 動画のメッセージと台本を作る
- 必要な素材を集める
- 動画を編集する
- 目的に応じて動画を配信する
それぞれの工程の概要やポイントについて解説します。
(1)制作する動画コンテンツの種類を選ぶ
まず最初に、どのような種類の動画を制作するか決定します。
動画の種類によって、必要な準備や制作手法が異なるため、まず種類を決めなければ制作の方針を決めることができません。
商品紹介動画なのか、採用動画なのか、それとも社内教育用なのか、目的を明確にしましょう。
また、ターゲットとなる視聴者層も同時に設定することが重要です。
誰のためにどんな動画を作るのかを明確にすれば、自ずと動画に込めるメッセージや配信すべきSNSなども決めることができます。
(2)コンテンツの制作方法を決める
動画の種類が決まったら、自社制作か外注かを選択します。
予算や必要なクオリティ、納期などを総合的に判断して決定しましょう。
品質の高いブランディング動画や商品説明動画は外注がおすすめですが、社内で使用するマニュアル動画であれば、社内で制作しても良いでしょう。
なお、自社制作の場合は、必要な機材や人員の確保から始める必要があります。
一方、外注の場合は、複数の制作会社から見積もりを取り、比較検討して適切な業者を選ぶことが重要です。
(3)動画のメッセージと台本を作る
動画制作の核となる、メッセージと台本の作成段階です。
ここでは、より詳細なステップに分けて説明します。
- 動画の目的を明確にする
- ペルソナを決める
- 動画のテイストを決める
- 台本を作る
#1:動画の目的を明確にする
動画の台本を決める前に、動画の目的を明確にしましょう。
「商品の認知度を20%向上させたい」、「求人への応募者数を前年度比150%にする」など、数値も含めた目標にすると、効果測定も容易です。
この目的が、すべての制作判断の基準となります。
また、成功指標(KPI)も同時に設定しておくと、後の効果測定がスムーズになるでしょう。
#2:ペルソナを決める
次に、動画のターゲットとなる視聴者の具体的な人物像を設定します。
年齢、性別、職業だけでなく、趣味や価値観、悩みやライフスタイルまでプロフィールを作り込むようなイメージで決めるのがおすすめです。
ペルソナが明確であればあるほど響くメッセージを作りやすくなり、動画の視聴者のアクションを促す効果があります。
「世界に一人だけしかいないかも」というレベルまで細かく作り込めば、動画の台本も決めやすくなるでしょう。
#3:動画のテイストを決める
ブランドイメージに合った動画の雰囲気や演出スタイルを決定します。
シリアスなのかカジュアルなのか、感動的なのかユーモラスなのか、方向性を明確にしましょう。
現時点の企業イメージを維持したいなら、自社のテイストに合わせた動画の方向性を、反対に企業イメージを変えたいと思っているなら、理想のブランディングに合わせて動画を選びましょう。
例えば、現時点では「お堅いイメージ」がある企業が親近感を演出したい場合は、ダンス動画などユーザーがカジュアルに閲覧できるコンテンツがおすすめです。
ただし、あまりに企業のブランディングと動画の方向性がズレると、視聴者が途中で離脱することもあるので、慎重に方向性を決めるようにしましょう。
#4:台本を作る
これまでの検討内容を踏まえて、具体的な台本を作成します。
冒頭でいかに視聴者の興味を引くか、中盤でどう展開するか、終盤でどうアクションを促すか、構成を練りましょう。
セリフやナレーション原稿も、ターゲットに響く言葉選びを心がけることも大切です。
また、映像と音声のタイミングを考慮し、詳細な指示も台本に記載することが重要といえます。
(4)必要な素材を集める
台本が完成したら、動画制作に必要な素材を準備します。
素材の種類によって集め方や準備方法が異なるため、計画的に進めることが大切です。
- 静止画主体の場合→画像を集める
- 動画主体の場合→撮影をする
- ナレーションやSEも用意する
順に見ていきましょう。
#1:静止画主体の場合→画像を集める
静止画を主体としてスライドショー形式の動画にする場合は、品質の高い写真素材を集めましょう。
自社で所有している写真素材を使う場合は、その中から解像度の高いものを選ぶのが重要です。
フリー素材サイトや有料の写真サイトの素材でも、商用利用が可能なものであれば、動画の素材として使用できます。
フリー素材は他社のLPや動画でも同じ写真が使われていることが多いので、可能であれば有料の写真サイトから素材をダウンロードしましょう。
#2:動画主体の場合→撮影をする
フルムービーで動画を制作する場合は、動画素材の撮影が必要です。
撮影には機材の確保はもちろん、撮影場所の許可取りと確保、出演者の手配などが必要です。
また、屋外での撮影の場合は天候や時間帯なども考慮して撮影スケジュールを組みましょう。
なお、撮影の日程はずれ込むこともあるので、予備日を用意してトラブルに備えるのがおすすめです。
#3:ナレーションやSEも用意する
動画ではナレーションやSEなども、動画の印象を大きく左右する要素となります。
例えば、インフォグラフィック主体の動画などにナレーションで解説を加えると、さらに理解度を高めることができます。
ナレーションはプロに依頼するほか、社内で録音して挿入する方法もあるため、予算に合わせてどちらかを選びましょう。
また、動画にBGMや効果音を入れることで展開にメリハリをつけて、視聴者が心地よく動画を最後まで視聴できるよう誘導する効果があります。
音質にもこだわり、クリアな音声素材を準備することが大切です。
(5)動画を編集する
すべての素材が揃ったら、いよいよ編集作業に入ります。
カット編集、テロップ挿入、エフェクト追加など、台本に沿って組み立てていきます。
編集ソフトは、無料のものから高機能な有料ソフトまで様々ありますが、目的に応じて選択しましょう。
また、色調整や音量調整など、細部の調整も忘れずに行ってください。
完成後は、複数人でチェックし、修正点がないか確認することが重要です。
(6)目的に応じて動画を配信する
完成した動画は、目的に応じた最適なプラットフォームで配信します。
YouTubeなら、SEOを意識したタイトルや説明文の設定が重要です。
SNSなら、各プラットフォームの特性に合わせた最適化が必要になります。
また、自社サイトに埋め込む場合は、ページの読み込み速度にも配慮しましょう。
さらに、配信後は視聴データを分析し、次回の制作に活かすことも大切です。
6.動画コンテンツを制作する場合の注意点

効果的な動画コンテンツを制作するために、押さえておくべき重要なポイントがあります。
具体的には、以下の通りです。
- 1ムービー1メッセージを心がける
- 自社のブランディングと動画のテイストを合わせる
- 必要な素材は一度に集めておく
- 商標権・著作権侵害に注意する
- 必ずリーガルチェックを依頼する
これらの注意点を守ることで、トラブルを避け、質の高い動画を制作することができるでしょう。
(1)1ムービー1メッセージを心がける
動画では、伝えたいメッセージを1つに絞ることが重要です。
複数のメッセージを詰め込むと、動画の趣旨がわかりにくくなり、視聴者の印象に残らない動画になってしまうからです。
例えば、商品紹介動画で機能も価格も品質もすべて伝えようとすると、焦点がぼやけてしまいます。
そのため、最も伝えたいポイントを1つ選び、それを軸に構成を組み立てましょう。
他の情報は別の動画で伝えるか、補足資料を読んでもらうようにリンクを貼るなどして対応するのがおすすめです。
(2)自社のブランディングと動画のテイストを合わせる
企業のイメージと動画のテイストが違いすぎると、視聴者に違和感や嫌悪感を与えることがあります。
例えば、JALがTikTokでPOPなダンス動画を公開した際、最初のうちはブランドイメージとのギャップから批判的な声も上がりました。
そのため、革新的な試みをする場合でも、ブランドの核となる価値観は保持することが大切です。
また、段階的にイメージを変えていくなど、視聴者が受け入れやすい工夫も必要です。
ブランディングとの一貫性を保ちながら、徐々に新しいチャレンジを進めていきましょう。
(3)必要な素材は一度に集めておく
動画制作する際は必要な素材を一度に集めておくのが重要です。
必要になるたびに素材を探していては、編集の効率が悪くなり公開までの時間的なロスが発生します。
外注の場合でも素材が不足していると編集が進まず、納期が遅延する可能性があるので注意してください。
そのため、想定される素材はすべて事前に集めておくことをおすすめします。
(4)商標権・著作権侵害に注意する
動画制作では素材の商標権や著作権侵害に注意しましょう。
それぞれの素材には商標権や著作権があり、利用規約を読まなければ、知らないうちに侵害してしまうリスクがあるからです。
無意識であっても企業が商標権や著作権侵害をすると、法的なリスクだけでなくイメージ低下を招きます。
BGMや画像、フォントなど、すべての素材について使用権を確認しましょう。
なお、無料素材でも商用利用が禁止されている場合があるので、しっかり規約を読んでから使用することが最も重要です。
(5)必ずリーガルチェックを依頼する
公開前には、必ず法務部門や専門家によるリーガルチェックを受けましょう。
意図せず法令違反や権利侵害をしている可能性があり、そのような場合には事前に確認を受けることで法的リスクを最小限に抑えることにつながります。
特に、比較広告や健康関連商品の動画は、表現に関する規制が厳しいため注意が必要です。
また、個人情報の取り扱いや、未成年者の出演についても確認が必要です。
リーガルチェックは時間がかかることもあるため、スケジュールに余裕を持って依頼しておくようにしましょう。
7.動画コンテンツの制作を委託できる外注先11選
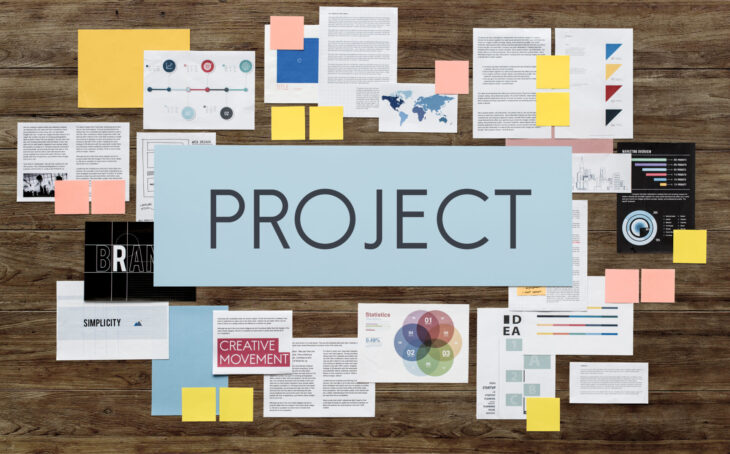
動画制作を外注する際は、自社が制作したい動画に強みを持つ会社を選ぶことが重要です。
ここでは、分野別におすすめの制作会社を紹介していきます。
- 商品やサービス紹介が得意な会社
- 採用動画が得意な会社
- 動画広告が得意な会社
- ブランディング動画が得意な会社
- 社内向け動画が得意な会社
(1)商品やサービス紹介が得意な会社
商品やサービスの魅力を効果的に伝える動画制作に強みをもつ会社を3つ紹介します。
- 株式会社Lumii
- 株式会社プルークス
- TMS Partners株式会社
順に見ていきましょう。
#1:株式会社Lumii
株式会社Lumiiは、商品の特徴を視覚的にわかりやすく表現する動画制作を得意としています。
アニメーションや実写などさまざまな編集技術を用いて、商品やサービスの特徴を伝える動画を制作できます。
さらに、従来の動画制作費用の1/3に費用を抑えるなど、比較的低コストで動画制作を依頼できるのが特徴です。
自社商品のPR動画を低価格で制作したいと考えているなら、ぜひ問い合わせしてみてください。
#2:株式会社プルークス
株式会社プルークスは、ストーリーテリングを重視した商品紹介動画を制作できる会社です。
感情に訴える演出で、商品への共感を生み出すことを得意としています。
過去には日本郵船やキリンホールディングスなどの大手企業の動画制作も担当しており、実績も技術も信頼できる企業といえるでしょう。
制作費用は規格構成からアフターフォローまでのプランで100〜200万円程度、TVCMに使用する動画は300万円〜となっています。
#3:TMS Partners株式会社
TMS Partners株式会社は、マーケティング視点での動画制作が強みです。
これまでさまざまな分野・領域でWeb施策を実施した経験もあり、BtoB、BtoC問わず的確なマーケ視点で動画を構成・制作することができます。
視聴者が知りたい情報を読み解いたうえで動画を構成するので、ユーザーから見たその商品の魅力を押し出した動画を制作できます。
なおWebコンサルティング業を主体としているため、動画の効果測定や運用まで任せられるのも特徴です。
(2)採用動画が得意な会社
次に紹介するのは、採用動画制作が得意な会社です。
- crevo株式会社
- StockSun株式会社
#1:crevo株式会社
crevo株式会社は、若年層に響く採用動画を作るのが得意な会社です。
実際の職場環境をしっかりヒアリングしたうえで、若者に親和性の高いアニメーションなどを用いた動画を制作します。
シンプルな動画なら49万円以内、ストーリー性のある表現を用いた動画は99万円以下など比較的安価に制作を委託できるのが特徴です。
セミナーで活用する動画、SNS向けの動画など配信先に合わせて動画制作も依頼できるため、採用活動を効率化することができるでしょう。
#2:StockSun株式会社
StockSun株式会社は、企業文化を効果的に伝える採用動画を制作します。
社員インタビューを中心とした、リアリティのある動画が特徴です。
さらに、専任担当者をクライアントが選べる体制を構築しており、打ち合わせ内容の引き継ぎ不足による動画の品質低下などの不安がありません。
また、企業として採用代行サービスを運用するなど採用ノウハウにも長けており、採用活動全体の相談ができることも強みです。
(3)動画広告が得意な会社
広告に用いる動画制作に強い制作会社を紹介します。
- 株式会社ヒューマンセントリックス
- 株式会社Kaizen Platform
効果的な動画広告で、認知拡大と売上向上を実現する制作会社です。
#1:株式会社ヒューマンセントリックス
株式会社ヒューマンセントリックスは、動画広告の制作に強みをもつ制作会社です。
自社で動画配信サービスを提供しており、広告や配信のノウハウが深いため、広告の目的に合わせた動画を制作できます。
制作には外注を一切使っておらず、動画制作体制も整っており、納期遅れなどの心配もありません。
YouTube広告やSNS広告など、各プラットフォームに最適化した広告動画を依頼したい企業におすすめです。
#2:株式会社Kaizen Platform
株式会社Kaizen Platformは、AIを活用した分析と動画広告運用が得意な会社です。
同社が提供する「KAIZEN AD」は動画広告の制作から配信までワンストップで委託でき、これまでCTRが2倍になったなどの実績もあります。
会社の既存パンフレットを動画化したり、LPを動画にして広告仕立てにしたり、既存素材を活用する動画制作も可能なので、コストが安いのも魅力です。
制作費用は見積もりが必要なので、事前にどんな動画を作りたいかを明確にしたうえで問い合わせをしてみましょう。
(4)ブランディング動画が得意な会社
企業のブランド価値を伝える動画制作が得意な会社を紹介します。
- 株式会社ピー・ディー・ネットワーク
- 株式会社グロウズ
#1:株式会社ピー・ディー・ネットワーク
株式会社ピー・ディー・ネットワークは、取材力を活かしたブランディング動画制作が得意な会社です。
過去には「カンブリア宮殿」や「WBS」などの経済・ドキュメンタリー番組を制作しており、その取材力を持って企業の魅力を深掘りして、ブランディング動画を制作します。
経営者へインタビューを実施した後にブランド戦略を考え、そのブランド戦略に基づいた一貫性のある動画を制作することが可能です。
過去には「日本コンセプト株式会社」、「株式会社RYODEN」などの大手企業との取引もあり、信頼性のある企業といえるでしょう。
#2:株式会社グロウズ
株式会社グロウズは、ブランディングに強みをもつ動画制作会社です。
これまで3,000本以上の企業動画制作の実績があり、深い知見でブランディングのサポートをしてもらえます。
規格構成からナレーションまでワンストップで委託できるため、リソースをかけずに動画制作が可能です。
さらにCG演出なども可能なため、実写では表現しきれない動画などを作りたい企業におすすめです。
(5)社内向け動画が得意な会社
教育研修や社内広報など、インナーコミュニケーション動画が得意な会社を紹介します。
- 株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント
- 株式会社ジェー・ピー・シー
#1:株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント
株式会社アジアピクチャーズエンタテインメントは、教育効果の高い研修動画が得意です。
テレビ番組や映画制作に携わってきた実績があり、動画制作についての技術はかなり高いといえます。
オンラインセミナーや研修用の動画を「楽しみながら学べるように作る」のがモットーで、社員が理解しやすい動画教材を制作することが可能です。
制作費用はプランによって異なりますが、シンプルプランなら50〜80万円の範囲から委託することができます。
#2:株式会社ジェー・ピー・シー
株式会社ジェー・ピー・シーは、業務マニュアル動画の制作を得意としています。
アニメーションなどを使ったマニュアル動画制作が得意で、社員研修に導入する企業も多いです。
複雑な工程をイラストやテキスト、実写素材を用いてわかりやすく表現できるので、教育のコストを下げるのに役立つでしょう。
まとめ
動画コンテンツは、現代の企業マーケティングにおいて欠かせないツールです。
商品紹介から採用活動、社内教育まで、幅広い用途で活用でき、それぞれに大きな効果をもたらします。
制作方法は自社制作と外注がありますが、目的や予算に応じて制作方法を選びましょう。
ただし、ブランディング動画や商品紹介など品質が求められる動画においては、外注がおすすめです。
動画の外注先にお悩みなら、TMS Partners株式会社へご相談ください。
TMS Partners株式会社なら、マーケター視点で動画構成を分析し、ユーザーの心に響く動画制作をお手伝いします。















