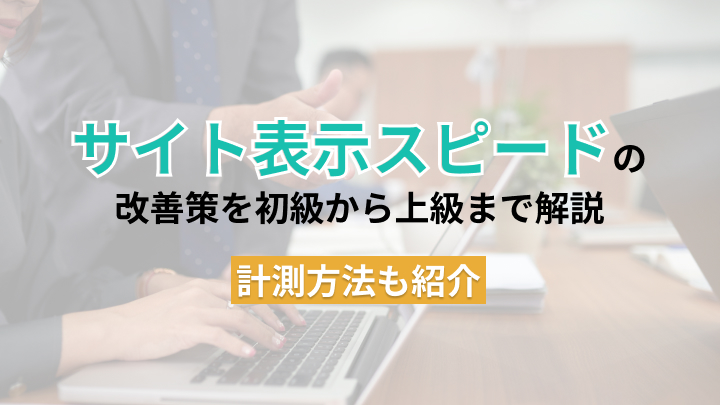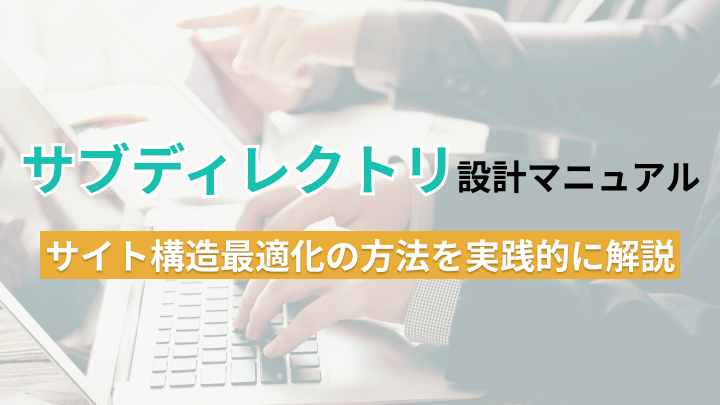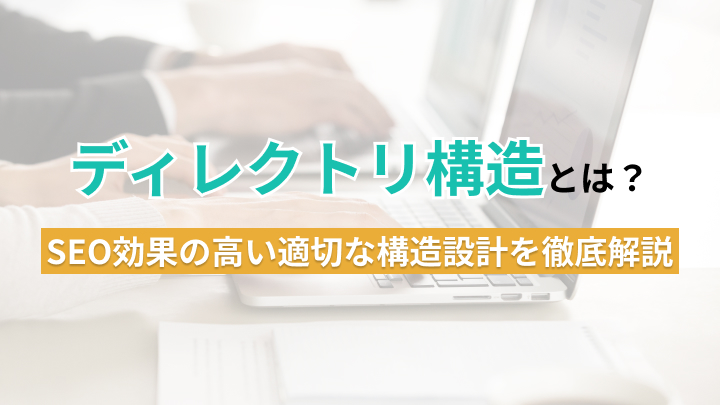サイト構造の基礎知識|SEOとユーザビリティを高める設計とは?
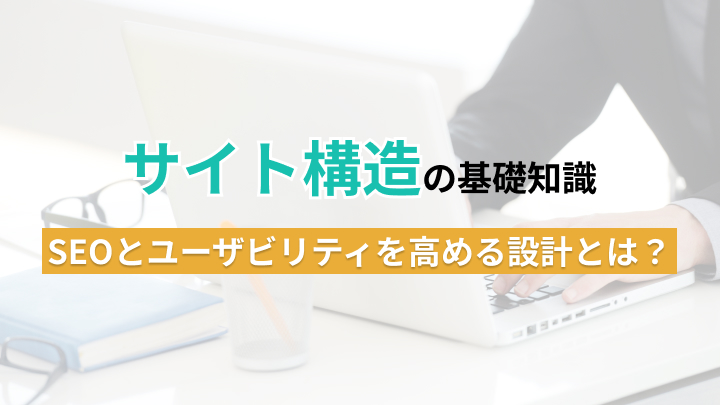
「サイト構造の基礎を知りたい」
「SEOとユーザビリティを高める設計方法が知りたい」
サイト構造は、Webサイトの骨組みとなる重要な要素です。
適切な構造設計により、ユーザビリティの向上とSEO効果の最大化が期待できます。
この記事では、サイト構造の基礎知識から実践的な改善手法まで、体系的に解説していきます。
初心者の方でも理解しやすいよう具体例を交えながら説明しているので、最後まで読めばサイト構造の重要性と効果的な設計方法が理解できるでしょう。
1.サイト構造とは?初心者でもわかるように解説

サイト構造は、Webサイトの骨組みとなる重要な要素です。
ページ同士のつながりや階層関係を整理することで、ユーザーにとって使いやすく、検索エンジンにとって理解しやすいサイトを実現できます。
適切なサイト構造の設計は、SEO対策の基盤となるだけでなく、ユーザー体験の向上にも直結する重要な要素です。
- サイト構造の定義と重要性
- ディレクトリ構造との違い
- HTMLサイトマップとXMLサイトマップの違い
- パンくずリストの役割
(1)サイト構造の定義と重要性
サイト構造とは、Webサイトを構成するページ同士の関係性や階層構造を指します。
トップページを頂点として、カテゴリーページや個別記事が枝分かれしていくようなツリー型の構造が一般的です。
この構造が明確であることで、ユーザーは目的のページに迷わずたどり着けるようになります。
また、GoogleなどのクローラーもWebサイトの内容を正確に理解できるため、適切な検索結果への表示が期待できます。
効果的なサイト構造を実現するためには、以下の3つの要素が重要となります。
- 明確な階層構造
- 論理的なカテゴリー分類
- 適切な内部リンク配置
これらの要素が適切に組み合わさることで、ユーザーにとって使いやすく、検索エンジンにとって理解しやすいサイトが完成します。
(2)ディレクトリ構造との違い
サイト構造とディレクトリ構造は、密接な関係にありますが異なるものであることを理解しておきましょう。
ディレクトリ構造は、URLやファイルの物理的な配置を示すものです。
一方、サイト構造は、ページ同士の論理的なつながりを示します。
効果的なサイト設計では、この2つの構造を一致させることで、ユーザーとクローラーの双方にとって分かりやすい構成を実現できます。
以下は、効果的なディレクトリ構造の例です。
example.com/
├── products/
│ ├── category1/
│ │ └── item1.html
│ └── category2/
│ └── item2.html
└── about/
├── company.html
└── contact.html
このような構造により、URLからコンテンツの位置関係が直感的に理解できます。
(3)HTMLサイトマップとXMLサイトマップの違い
HTMLサイトマップは、ユーザー向けのナビゲーションツールとして機能します。
一方、XMLサイトマップは検索エンジンのクローラー向けの案内図として働いており、以下のような形式で直感的に人には理解しにくい構造です。
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″>
<url>
<loc>https://example.com/</loc>
<lastmod>2024-01-20</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
</urlset>
それぞれの特徴と役割は大きく異なるため、両方を適切に実装することが推奨されます。
サイトマップについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
(4)パンくずリストの役割
パンくずリストは、ユーザーの現在位置を示す重要なナビゲーション要素です。
適切に実装されたパンくずリストは、ユーザビリティの向上だけでなく、検索結果での表示にも活用されます。
以下が、schema.orgに準拠したパンくずリストの実装例です。
<nav aria-label=”breadcrumb”>
<ol itemscope itemtype=”https://schema.org/BreadcrumbList”>
<li itemprop=”itemListElement” itemscope itemtype=”https://schema.org/ListItem”>
<a itemprop=”item” href=”/”>
<span itemprop=”name”>ホーム</span>
</a>
<meta itemprop=”position” content=”1″ />
</li>
<li itemprop=”itemListElement” itemscope itemtype=”https://schema.org/ListItem”>
<a itemprop=”item” href=”/category/”>
<span itemprop=”name”>カテゴリー</span>
</a>
<meta itemprop=”position” content=”2″ />
</li>
<li itemprop=”itemListElement” itemscope itemtype=”https://schema.org/ListItem”>
<span itemprop=”name”>現在のページ</span>
<meta itemprop=”position” content=”3″ />
</li>
</ol>
</nav>
このコードにより、検索エンジンはサイトの階層構造を正確に理解できます。
2.サイト構造が検索順位に与える影響とメリット

適切なサイト構造は、検索エンジンによるインデックスの効率化とユーザビリティの向上に貢献します。
サイト構造を最適化することで、コンテンツの価値を最大限に引き出し、検索順位の向上が期待できるのです。
検索エンジンは、明確な構造を持つWebサイトをより高く評価する傾向にあります。
- 検索エンジンのクローリング効率向上
- ユーザビリティとの関係性
- サイトの専門性評価への影響
- 内部リンクによる価値の分配
(1)検索エンジンのクローリング効率向上
適切なサイト構造は、クローラーの巡回効率を大幅に向上させます。
トップページから3クリック以内で全てのページにアクセスできる構造が理想的です。
Googleの公式ブログによると、効率的なクローリングは検索順位に直接的な影響を与えることが示唆されています。
具体的には深い階層に重要なコンテンツを配置すると、クローラーの到達が遅れる可能性があり、重要なコンテンツでもなかなかインデックスされません。
そのため、重要なコンテンツは比較的浅い階層に配置するなどの配慮が必要となります。
(2)ユーザビリティとの関係性
サイト構造の最適化は、ユーザー体験の向上に直結します。
論理的な構造により、ユーザーは目的のコンテンツに素早くアクセスできるためです。
また、直感的なナビゲーションは、サイト内での滞在時間を延ばす効果があります。
Google Search Consoleのデータによると、ユーザーの行動シグナルは検索順位の重要な指標となっています。
サイト構造の改善により、直帰率の低下や滞在時間の増加、ページビュー数の向上などの指標改が改善する効果も期待できるため、構造はしっかり設計しておくべきです。
(3)サイトの専門性評価への影響
明確なカテゴリー分類は、サイトの専門性をアピールする重要な要素となります。
関連コンテンツを適切にグループ化することで、特定分野における権威性を示すことができます。
Google EATの評価基準において、コンテンツの体系的な整理は専門性の判断材料となるためです。
例えば、医療情報サイトであれば、症状別、部位別、疾患別など、多角的な分類が有効です。
このような構造化により、サイトの信頼性と専門性を高めることができます。
(4)内部リンクによる価値の分配
適切な内部リンク構造は、ページ間でリンクジュースを効率的に分配します。
重要なページには、より多くの内部リンクを設置することで、その価値を高めることができます。
内部リンクは、検索エンジンに対してページの重要度を示す重要なシグナルとなるためです。
ただし、過度な内部リンクは逆効果となる可能性があります。
適切なバランスを保ちながら、戦略的な内部リンクの設計を行うことが重要です。
2.サイト構造が検索順位に与える影響とメリット

適切なサイト構造は、検索エンジンによるインデックスの効率化とユーザビリティの向上に貢献します。
サイト構造を最適化することで、コンテンツの価値を最大限に引き出し、検索順位の向上が期待できるのです。
検索エンジンは、明確な構造を持つWebサイトをより高く評価する傾向にあります。
- 検索エンジンのクローリング効率向上
- ユーザビリティとの関係性
- サイトの専門性評価への影響
- 内部リンクによる価値の分配
(1)検索エンジンのクローリング効率向上
適切なサイト構造は、クローラーの巡回効率を大幅に向上させます。
トップページから3クリック以内で全てのページにアクセスできる構造が理想的です。
Googleの公式ブログによると、効率的なクローリングは検索順位に直接的な影響を与えることが示唆されています。
深い階層に重要なコンテンツを配置すると、クローラーの到達が遅れる可能性があります。
そのため、重要度に応じた階層設計が不可欠となります。
(2)ユーザビリティとの関係性
サイト構造の最適化は、ユーザー体験の向上に直結します。
論理的な構造により、ユーザーは目的のコンテンツに素早くアクセスできます。
直感的なナビゲーションは、サイト内での滞在時間を延ばす効果があります。
Google Search Consoleのデータによると、ユーザーの行動シグナルは検索順位の重要な指標となっています。
サイト構造の改善により、直帰率の低下や滞在時間の増加、ページビュー数の向上などが期待できます。
(3)サイトの専門性評価への影響
明確なカテゴリー分類は、サイトの専門性をアピールする重要な要素となります。
関連コンテンツを適切にグループ化することで、特定分野における権威性を示すことができます。
Google EATの評価基準において、コンテンツの体系的な整理は専門性の判断材料となります。
例えば、医療情報サイトであれば、症状別や部位別、疾患別など、多角的な分類が有効です。
このような構造化により、サイトの信頼性と専門性を高めることができます。
(4)内部リンクによる価値の分配
適切な内部リンク構造は、ページ間でリンクジュースを効率的に分配しましょう。
内部リンクは、検索エンジンに対してページの重要度を示す重要なシグナルとなります。
重要なページにはより多くの内部リンクを設置することで、その価値を高めることができるからです。
ただし、過度な内部リンクは逆効果となる可能性があります。
適切なバランスを保ちながら、戦略的な内部リンクの設計を行うことが重要です。
4.SEOに効果的なページ構成とワイヤーフレーム設計

ページ構成とワイヤーフレームの設計は、SEOとユーザビリティを両立させる重要な要素です。
適切な設計により、コンテンツの価値を最大限に引き出し、検索エンジンとユーザーの双方に評価されるページを実現できます。
効果的なワイヤーフレームは、ユーザーの行動を促進しながら、検索エンジンの理解を促進します。
- ファーストビューの重要性と設計
- メインコンテンツの配置方法
- CTAの効果的な設置
- レイアウト構成の基本要素
(1)ファーストビューの重要性と設計
ファーストビューは、ユーザーが最初に目にする領域であり、継続的な閲覧を決定づける重要な部分です。
Google社の調査によると、ページ読み込み後1.5秒以内にユーザーの第一印象が形成されます。
この領域では、ユーザーの興味を引きつけながら、ページの主要なメッセージを明確に伝える必要があります。
効果的なファーストビューには、以下の要素が必要です。
- ヘッドラインが明確であること
- 商品やコンテンツの価値を提案していること
- アクションへの誘導(CTA)が設置されていること
また、視覚的な階層構造により、情報の優先順位を示すことも大切です。
(2)メインコンテンツの配置方法
メインコンテンツは、ユーザーの目的を満たす核心部分です。
検索エンジンがコンテンツを正しく理解できるよう、適切なHTML構造と意味のある見出し階層が必要です。
メインコンテンツの配置では、以下の点に注意しましょう。
視認性の高い位置への配置、適切な文字サイズとコントラスト、モバイルでの可読性確保の3点に注意してください。
視認性が悪いとそれだけで離脱されてしまい、コンテンツの内容を読み込んでもらえません。
また、サイドバーやフッターなど、補足的な要素との明確な区別も必要となります。
(3)CTAの効果的な設置位置
CTA(Call To Action)は、ユーザーに具体的なアクションを促す重要な要素です。
CTAは、ユーザーの興味が最も高まるタイミングで提示することが効果的であり、またコンバージョン率を上げるにはCTAの適切な配置が欠かせません。
具体的な設置位置として、以下のポイントが挙げられます。
ファーストビューの下部、コンテンツの自然な区切り、ページの最後など、文脈に応じた配置が重要です。
また、モバイル環境での操作性も考慮した設計が必要となります。
(4)レイアウト構成の基本要素
効果的なレイアウトは、情報の階層性と視線の流れを考慮して設計します。
ユーザーの行動パターンに基づいた、直感的な情報設計が重要です。
レイアウトの基本要素には以下のものがあります。
- ヘッダー
- ナビゲーション
- メインコンテンツ
- サイドバー
- フッター
これらの要素の配置により、ユーザーが情報を直感的に読み取れるようにします。
特にモバイルファーストの視点から、レスポンシブデザインの実装も重要な要素となるため、レスポンシブデザインでのサイト設計を心がけましょう。
5.ユーザー導線を意識したサイト構造設計の例

ユーザー導線の最適化は、Webサイトの成功を左右する重要な要素です。
適切な導線設計により、ユーザーを目的のページへスムーズに誘導し、最終的なコンバージョンにつなげることができます。
効果的な導線設計では、ユーザーの行動心理を理解し、それに沿った自然な流れを作ることが重要です。
- ターゲットユーザーの行動分析
- コンバージョンまでの導線設計
- 回遊性を高めるリンク構造
- 離脱を防ぐページ構成
(1)ターゲットユーザーの行動分析
Google Analytics 4のユーザー行動レポートを活用し、実際の閲覧パターンを分析します。
具体的には流入経路やページ遷移、滞在時間などのデータから、ユーザーの興味関心を読みときましょう。
これらデータに基づいた行動分析により、効果的な導線設計が可能となります。
ユーザーの行動パターンは、デバイスによっても大きく異なります。
デスクトップとモバイルの双方を分析したうえで、サイトの構造を考えましょう。
(2)コンバージョンまでの導線設計
サイト構造ではコンバージョンまでの道筋を、できるだけシンプルに設計することが重要です。
不要なステップを省き、ユーザーの負担を最小限に抑えることでコンバージョン率を上げることができるためです。
各ステップでのマイクロコンバージョンを設定し、段階的な成果を測定しましょう。
例えば、資料請求までの導線は以下のように設計できます。
関連コンテンツの閲覧 → メールマガジン登録 → 無料サンプルのダウンロード → 資料請求
このように設計を決めてからサイトの構造を作っていくことで、最小限の負担でユーザーに望むアクションを喚起できます。
(3)回遊性を高めるリンク構造
関連コンテンツへの適切な誘導により、サイト内の回遊性を高めることができます。
カテゴリーやタグ、関連記事など、多様なナビゲーション要素を効果的に配置します。
ユーザーの興味に応じた柔軟な導線を用意することで、サイトの価値を最大限に伝えることができます。
また、パンくずリストやサイトマップなど、補助的なナビゲーションも重要です。
これらの要素により、ユーザーはストレスなく情報を探索できるようになります。
(4)離脱を防ぐページ構成
ユーザーの離脱を防ぐには、各ページで明確な価値提供が必要です。
特に重要なページでは、ユーザーの不安や疑問に先回りして対応することが効果的です。
ページの目的に応じた適切なCTAを設置し、次のアクションを促します。
例えば、以下のような要素を効果的に配置します。
FAQセクション、信頼性を示す実績や証明、具体的な使用例や事例の提示によりユーザーの信頼を勝ち取ることができ、離脱を防げるでしょう。
また、問い合わせフォームへの導線も必要となります。
6.サイト構造の具体的な改善ステップ

サイト構造の改善は、現状分析から始まり段階的に実施していく必要があります。
体系的なアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら効果的な改善を実現できます。
データに基づいた継続的な改善プロセスにより、長期的なサイトパフォーマンスの向上が期待できます。
- 現状分析と課題抽出
- 改善プランの立案
- A/Bテストによる検証
- 段階的な実装アプローチ
(1)現状分析と課題の洗い出し
サイト構造を改善するにはまずGoogle Analyticsを活用し、現状のユーザー行動を詳細に分析します。
直帰率の高いページやコンバージョン率の低い導線、ユーザーの離脱ポイントを特定します。
定量データと定性データの両面から、改善が必要な箇所を特定することが重要です。
ヒートマップツールを使用して、クリック位置や視線の動きも確認します。
これにより、ユーザーの実際の行動パターンを把握して改善策を考えていきましょう。
(2)改善プランの立案方法
ステップ1で特定された課題に対して、具体的な改善案を策定します。
優先順位付けを行い、投資対効果の高い施策から着手しましょう。
各改善施策について、期待される効果とKPIを明確に設定しておくと、改善策がうまくいっているかの指標となります。
なお、改善プランには、以下の要素を含める必要があります。
- 具体的な実装内容
- 必要なリソース
- 実施スケジュール
- 期待される効果の測定方法
この4つを軸に改善プランを立案、実施してSEO的な効果が出るかを検証していきましょう。
(3)A/Bテストによる効果検証
サイト構造の改善ではA/Bテストを実施し、改善案の効果を客観的に検証します。
統計的に有意な結果が得られるまで、十分なサンプル数でテストを継続することが重要です。
A/Bテストの実施手順は以下のようになります。
- テスト仮説の設定
- バリエーションの作成
- テストの実施期間の決定
- データ収集と分析
- 結果に基づく意思決定
簡単にいえば「Aの構造とBの構造のどちらでコンバージョン率が高いか(指標は自社課題に合わせて設定)」を検証、最終的に結果が良好な方を最終的なサイト構造として決定するという流れになります。
(4)段階的な改善アプローチ
サイト構造の大規模な変更は、一度に実施するのではなく段階的に進めます。
各段階での効果を測定しながら、必要に応じて軌道修正を行います。
継続的な改善サイクルを確立することで、安定した成果を上げることができるでしょう
改善の各フェーズでは、以下の点に注意が必要です。
まず変更による影響範囲がどこまで及ぶか把握して、起こりうるリスクへ備えなければなりません。
また、テストを実施する前にバックアップをとっておき、万が一の際に元に戻せるようにすることも大切です。
なお、テスト時にはユーザーにサイトの閲覧上で迷惑がかからないように配慮しましょう。
7.業種別・目的別の最適なサイト構造

業種や目的に応じた適切なサイト構造は、ビジネス目標の達成に直結します。
各業種特有の要件を理解し、ユーザーの行動特性に合わせた設計が重要となります。
ビジネスモデルに適したサイト構造の選択により、コンバージョン率の向上と顧客満足度の改善が実現できます。
- ECサイトの購買導線設計
- コーポレートサイトの信頼性設計
- メディアサイトのコンテンツ設計
- リードジェネレーション型の導線設計
(1)ECサイトの購買導線設計
ECサイトでは、商品検索から購入完了までのスムーズな導線設計が必須です。
カテゴリー構造は、ユーザーの商品探索行動にもとづいて設計します。
商品詳細ページへの到達までのクリック数を最小限に抑えて、購買意欲を維持することが重要です。
基本的な構造として、以下の階層設計が理想的といえます。
トップページ → カテゴリー一覧 → サブカテゴリー → 商品一覧 → 商品詳細
また、関連商品やレコメンド機能による購買機会の創出も同時に実施して、購買率を高めましょう。
(2)コーポレートサイトの信頼性設計
コーポレートサイトは、企業の信頼性と専門性を効果的に伝える構造が重要です。
企業情報やサービス内容、実績などを、ユーザーが迷いなくアクセスできることを最優先にして配置しましょう。
例として、主要なコンテンツは以下のように配置します。
企業理念やビジョンをトップレベルに置き、具体的なサービスや製品情報を次層に配置しましょう。
採用情報やIR情報など、ターゲット別のセクションも明確に区分けすることで、ユーザーがサイト内で必要な情報を探しやすくなります。
(3)メディアサイトのコンテンツ設計
メディアサイトでは、コンテンツの発見性と回遊性を高めるサイト構造が重要です。
カテゴリーやタグを活用し、コンテンツにアクセスしやすい設計を考えましょう。
ユーザーの興味関心に応じて、関連コンテンツへ自然に誘導できる構造が効果的です。
また、サイドメニューに検索機能を配置するなどの施策も、コンテンツの発見とサイト回遊のための重要な要素です。
(4)リードジェネレーション型の導線設計
リードジェネレーション型サイトでは、段階的な信頼構築が重要です。
価値提案から問い合わせまでの導線を、ユーザーの検討段階に合わせて設計します。
各段階での適切な情報提供と行動喚起により、質の高いリード獲得を実現しましょう。
課題提起 → ソリューション提案 → 事例紹介 → 資料提供 → 問い合わせ
各ステップでの離脱を防ぐため、フォローアップコンテンツなども用意して、問い合わせまでにユーザーの不安を解消する仕組みを作りましょう。
8.サイト構造の運用と改善

サイト構造は、一度構築して終わりではなく、継続的な運用と改善が必要です。
ユーザーの行動変化やビジネス要件の変更に応じて、柔軟に対応していく必要があります。
定期的なデータ分析と改善サイクルの確立により、サイトの価値を持続的に向上させることができます。
- 定期的な構造の見直し方法
- アクセス解析による改善点の特定
- コンテンツの追加・削除時の注意点
- リニューアル時の移行計画
(1)定期的な構造の見直し方法
サイト構造の見直しは、四半期ごとなど定期的なタイミングで実施します。
ユーザーの行動データやビジネス目標の達成状況をもとに、改善点を特定します。
定量的なデータと定性的なフィードバックの両面から、改善の必要性を判断することが重要です。
見直しの際はページの階層関係、ナビゲーションの分かりやすさ、重要コンテンツへのアクセス性などを確認します。
また、競合サイトの動向分析なども併用して、ライバルに負けない見やすいサイト構造を目指しましょう。
(2)アクセス解析による改善点の特定
Google Analyticsを活用し、ユーザーの行動パターンの結果を改善に活かしましょう。
ページごとの滞在時間や離脱率、コンバージョン率などの指標から、改善が必要な箇所を特定します。
特にユーザーの動線分析により、構造上の問題点を早期に発見することができます。
例えば離脱が早ければファーストビューに魅力がなかったり、情報が不足しているのかもしれません。
また、回遊がないのであればコンテンツを発見しやすい構造に改善が必要です。
以上のようにアクセス解析でユーザーがサイトをどう見ているかを分析して、より良いサイト構造を考えましょう。
(3)コンテンツの追加・削除時の注意点
サイト構造を改善するにあたり、新規コンテンツの追加や既存コンテンツの削除をする場合にも注意が必要です。
コンテンツの追加や削除は、サイト構造に影響を与える可能性があります。
特にカテゴリー構造やナビゲーションへの影響を考慮した計画が必要です。
内部リンク構造への影響に注意を払い、SEO価値の分配を適切に維持するようにしましょう。
また、URL構造の一貫性や既存の導線への影響の確認、サイトマップの更新なども併せて実施してください。
また、コンテンツの削除をする際はそのページに直接ブックマークしているユーザーがいないか確認し、必要ならリダイレクト処理を実施しましょう。
リダイレクトについては、こちらの記事をご覧ください。
(4)リニューアル時の移行計画
サイトリニューアル時は、綿密な移行計画の立案が不可欠です。
既存のSEO評価を維持しながら、新しい構造への移行を実現する必要があります。
この場合は301リダイレクトの適切な設定により、検索エンジンとユーザーの双方に配慮した移行が可能となります。
既存URLの新URLへのマッピング、段階的な移行スケジュール、バックアップ体制の整備などを実施したうえで、リダイレクトを実施しましょう。
301リダイレクトの詳細については、こちらの記事で説明しています。
まとめ
サイト構造の最適化は、SEOとユーザビリティを向上させる重要な施策です。
明確な階層構造と効果的な導線設計により、サイトの価値を最大限に引き出すことができます。
継続的な分析と改善により、長期的な成果を実現することが可能です。
特に重要なポイントはユーザーの行動パターンを理解し、目的に応じた適切な構造を選択して改善していくことです。
また業種や目的に合わせた最適な設計により、効果的なコンバージョンを実現できます。
ただし、サイト構造の見直しを始めたばかりだと「何をどう変更して良いかわからない」と悩むこともあるでしょう。
サイト構造の改善についてプロに相談したい方は、TMS Partners株式会社へご相談ください。
TMS Partners株式会社は、数々の企業のサイト構造改善を含むSEO支援を実施しています。
豊富な支援実績を活かして、SEO対策はもちろん、広告支援まで幅広い内容の支援が可能です。
問い合わせは無料なので、まずは以下の問い合わせフォームより気になることや質問をお寄せください。