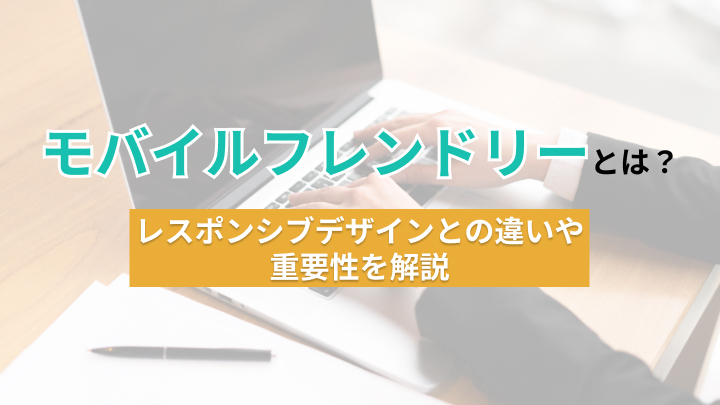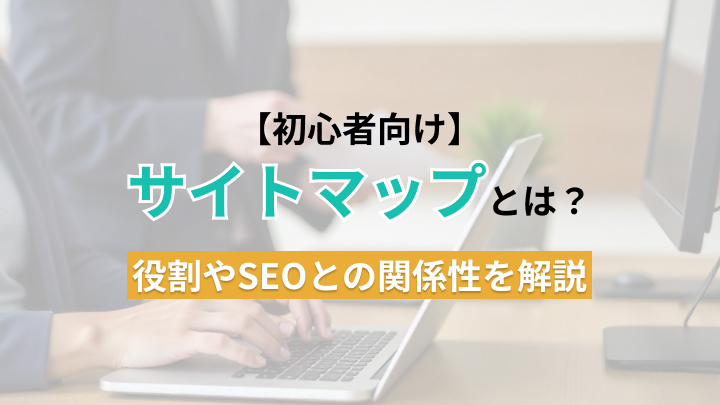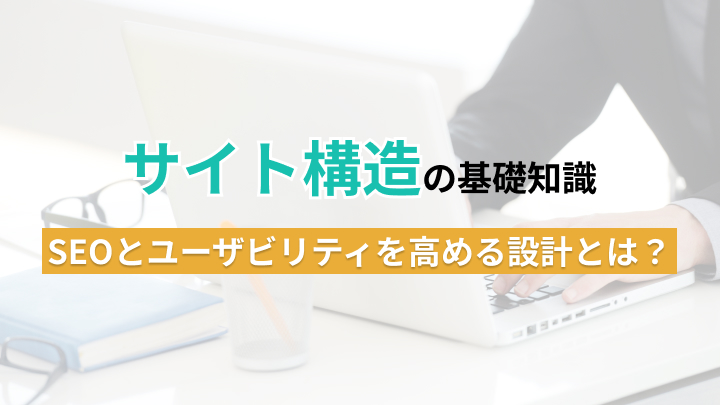UI改善とは?UXとの関係性や改善プロセスを解説
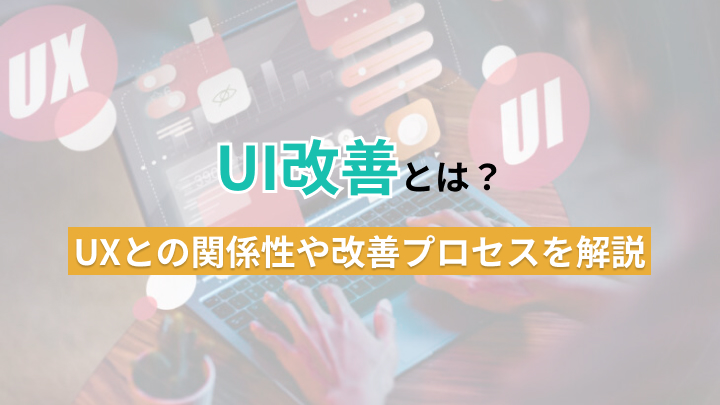
「UI改善ってなに?」
「UXとの関係やUI改善の方法を知りたい」
「UI改善のポイントは?」
企業の経営者やマーケティング担当者の中にはこのような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
UIはユーザーと商品・サービスの接点となるものを指す包括的な概念です。
ユーザーが商品・サービスに初めて触れる際の接点であることから、UIを改善することは、顧客満足度やロイヤリティ向上につながる重要な要素のひとつと言えます。
ユーザーに満足度の高い体験を提供することができれば、評判が広がり、新たなユーザーを獲得することができるでしょう。
このように、UIの改善に取り組むことは既存の顧客の囲い込みだけでなく、リード(見込み顧客)獲得のためにも有益です。
本記事では、UIについての基礎知識やUXとの関係、改善プロセスなどを解説していきます。
上記のような目的を達成するためには、UIだけでなくUXを向上させることも大切です。
これから自社商品・サービスのUI改善に取り組むことを検討されている方はもちろん、UIの基本概念について把握したい方もぜひご覧ください。
1.UIとは

UIとは、「User Interface(ユーザーインターフェース)」を略した言葉です。
Webサイトやアプリケーション、ソフトウェアなど、ユーザーが接点を持つあらゆる部分を指す概念です。
例えば、パソコンやスマートフォンであれば、ディスプレイやマウスだけでなく、キーボードやマイクなどのデバイスがUIに該当します。
もっとも、UIは上記のようなデバイスだけでなく、「ユーザーにとって使いやすいサービスを提供するためのもの」を包括する広い概念です。
具体的には、Webページのデザインやフォント、画像などもUIに当たります。
また、目に見えない操作性や機能性もUIに含まれるため、ユーザーとサービスの接点すべてを内包していると言えるでしょう。
ユーザーは商品・サービスに初めて触れる際に操作性やデザイン、レイアウトなどの要素から商品・サービスの印象や有益性を直ちに判断することが多いです。
そのため、UIの設計はユーザーが商品・サービスに対して抱く評価や印象を大きく左右します。
逆に言えば、優れたコンテンツや機能を提供できていたとしても、ユーザーが使いやすさや快適性を抱くことができなければ、ユーザーからの評価は低くなってしまいます。
ユーザーに商品・サービスを継続的に利用してもらうためには、UIの設計にこだわることや既存のUIを見直して改善を加えることは必須の施策と言えるでしょう。
2.UIとUXの関係性

結論から言うと、UIとUXは密接な関係にあります。
UXはUIと類似の概念で、「User Experience(ユーザーエクスペリエンス)」の略称です。
これは、商品・サービスの利用を通じてユーザーが得ることができる「体験」に焦点をあてたものです。
UXはユーザーが商品・サービスに触れ、利用する中で利便性や快適性を抱き、利用した後にどのような心理状態となるのかまでを含めた広範な概念と言えます。
つまり、「ユーザー接点」であるUIが、「ユーザー体験」であるUXの中で重要な役割を果たすひとつの要素であり、UXに内包される概念と言えるでしょう。
UIが使いやすくデザインされていれば、ユーザーはスムーズに目的を達成することができます。
例えば、ボタンの配置や配色、操作フローなどUIの改善を継続的に行うことでユーザーの満足度を高めることができるでしょう。
ただし、UXはUIによってのみ向上するわけではない点に注意が必要です。
UXの向上にはUI以外の要素も関係しているため、商品・サービスの機能面の改善だけではなく、アフターサービスなどの商品・サービス利用後のフォロー体制なども含めた全体的な改善を図ることが重要です。
UXの改善方法は以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
3.UI改善をするべき4つの理由

上記で述べたように、商品・サービスのUIを改善することは、ユーザーにとってメリットが大きいです。
もっとも、UI改善を行うことで、ユーザーだけでなく、自社にもメリットがあることを押さえておきましょう。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
- ユーザビリティの向上
- 競合他社との差別化
- ユーザーの満足度・信頼度向上
- 販路拡大や売上の向上
UI改善を通じてユーザーの満足度を高めることができれば、自社商品・サービスの市場価値を高めることにもつながるのです。
それぞれについて、解説します。
(1)ユーザビリティの向上
ユーザーがより快適にサービスやWebサイトを利用できるようにするためには、UIの改善が重要です。
どんなに優れた商品やサービスでも、操作が複雑で時間がかかったり、分かりにくかったりすると、ユーザーはストレスを感じ、離脱してしまいます。
そのためにも、ユーザーがサービスやWebサイトを利用する際にストレスを感じさせないことが大切です。
また、ユーザビリティの向上は、サービスの評価を高めるだけでなく、リピーターを増やすことにもつながります。
自社のサービスを長期的に利用してもらうためにも、UIの改善は不可欠な要素と言えるでしょう。
(2)競合他社との差別化
自社商品・サービスの競合他社が多い中では、UIが優れていることは、それだけで大きな差別化要素となりえます。
現在の市場には無数の商品やサービスが存在しており、ユーザーは自社と似たような商品・サービスを簡単に見つけることができる環境にあります。
そのため、商品の特徴や価格といった基本的な部分だけで競争するのでは不十分な場合が多く、ユーザーにとっての使いやすさや体験の質という点で他社との差別化を図る必要があります。
特に、現代のユーザーは利便性や快適さを非常に重視しています。
例えば、直感的に操作ができたり、購入や操作にかかる手間が最小限であったりすることが大切です。
そのため、より強い差別化を打ち出すためには、UIの改善と合わせてUXの改善を図ることが重要な要素となります。
ユーザーが最も利用しやすいと感じるサービスを提供することが、他社との差別化だけでなく、顧客からの信頼と評価を高めることにもつながるのです。
(3)ユーザーの満足度・信頼度の向上
ユーザーの満足度・信頼度を向上させるためにはUI改善が欠かせません。
使いやすく視覚的にも優れたUIを提供し続けることで、良質なUXを実現できます。
また、UI改善によって顧客が使いにくいと感じていたポイントが解消されれば、サービスへの信頼感が高まり、「このサービスは今後も改善されていく」と期待させることで、リピーターの創出にもつながります。
このように、UIの改善は、顧客満足度を向上させるだけでなく、ユーザーとの信頼関係を築き、継続利用を促進するための重要な施策と言えます。
(4)販路の拡大や売上の向上
UIを改善することで、販路の拡大や売上の向上も望めます。
つまり、UIの改善を梃子にして、ユーザーに満足度の高い体験を提供することで、その体験が口コミや評判として広がり、新規顧客の獲得にもつながるのです。
さらに、UIが改善されて使いやすくなることで、ユーザーはサービスに対する満足度を高め、次第に追加機能や上位プランへの興味を持つようになります。
これにより、基本プランからより多機能なプランや高価格帯のオプションにアップグレードする可能性が高まり、結果として売上や利益の増加を促進します。
また、商品・サービスに対する信頼や安心を企業ブランド自体に対する信頼にまで高めることができれば、その企業の別の商品・サービスの利用や導入の検討にもつながる可能性が高まります。
このように、UIの改善は単に快適な利用をユーザーに提供するだけでなく、ユーザーの満足度を起点に、事業全体の成長を後押しする重要な施策となります。
4.UI改善のプロセス

UIを改善する際のプロセスについて解説します。
改善を行う商品・サービスの内容や性質に関わらず、以下のような流れで進めることが重要です。
- 問題把握
- ユーザー理解
- プロトタイプ・デザインの作成
- 検証・実装
それぞれの具体的な内容やポイントについて、ご説明します。
(1)問題把握
まずは、 現在のUIが抱える問題点や改善点を明確にしましょう。
UIがどのように使いにくいのか、どこを改善すれば良いのかなど、具体的な改善点を洗い出します。
この際に、実際に使用するユーザー側に立って考えることが何よりも大切です。
Webサイトであれば、ヒートマップやGoogleアナリティクスを活用し、離脱が多いページや滞在時間の短いページを見つけます。
離脱率の高さや滞在時間の短さなどの要因をユーザーの行動データをもとにしながら検討し、コンテンツ内容やレイアウトの変更・改善を進めることが重要です。
また、ユーザビリティテストやアンケート調査を行うこともおすすめです。
ユーザーの意見を直接聞くことや現場環境を確認することで、本質的な改善ポイントを特定することができ、効果的なUI改善を実現できるでしょう。
(2)ユーザー理解
調査結果をもとに、ユーザーニーズを把握しましょう。
分析で判明した問題点に対し、手間を減らしたり、説明を追加するなど、ユーザーの視点から具体的な改善策を考えます。
この際に、改善の方向性をユーザーの視点に合わせることが大切です。
まずは、ペルソナを作成し、ユーザー層の特定や検索動機、課題をモデル化しましょう。
ペルソナを設定することで、改善すべき方向性が定まります。
また、ユーザーがサービスに触れる全体の流れを描き、接点ごとの課題を特定するためにカスタマージャーニーマップを作成し、ユーザー分析を進めます。
これらの分析手法を組み合わせることで、ユーザーの本質的な課題を抽出し、改善の優先順位を設定することが可能となります。
(3)プロトタイプ・デザインの作成
プロトタイプ作成は、課題の解決策を具体化する重要なステップです。
プロトタイプは、ユーザーのニーズを考慮し、問題点や課題点を落とし込んだシナリオを元に作成します。
作成するプロトタイプは、ユーザーが実際に試せるように、最小限の機能を備えたMVP(Minimum Viable Product)として設計するようにしましょう。
実際に形にすると違和感が生じることもあるので、その都度さらに改善を重ねていきます。
(4)検証・実装
プロトタイプがユーザーのニーズや期待をどの程度満たしているかを検証し、評価することが大切です。
そのために、ユーザーに実際にプロトタイプや完成した製品・サービスを使用してもらい、使い勝手や直感的な操作性が十分であるかを確認します。
この評価結果をもとに、表面化した課題をひとつずつ解決し、UIやUXを改良しましょう。
なお、ユーザーの満足度や信頼を維持するためには、一度の改善のみでは十分でないことに注意が必要です。
商品・サービスを取り巻く環境や業界の動向などによって、どのような機能や操作方法がユーザーにとって最も快適であるかは常に変動・流動化します。
そのため、これらのプロセスを定期的に回しながら商品・サービスの品質の改善・最適化に努めることが何よりも重要です。
PDCAサイクルを継続的に回すことによって、製品やサービスのUI/UXは進化し続け、ユーザーの満足度が高まるだけでなく、競争力のある魅力的な体験を提供できるようになるのです。
5.UI改善のポイント

UIを改善する際に押さえておきたいポイントを紹介します。
具体的には、以下の点を意識しましょう。
- サイト構造をシンプルにする
- アクセシビリティへの対応
- レスポンシブデザインの採用
- ユーザーからのフィードバックを反映する
順にご説明します。
(1)サイト構造をシンプルにする
サイト構造をシンプルにすることは、ユーザーが直感的にコンテンツにアクセスしやすくするために非常に大切です。
特に、ページ数が多くてコンテンツが膨大な大規模サイトでは、ユーザーが欲しい情報を見つけられず、途中で離脱してしまう可能性が高まります。
そのため、ユーザーが迷わずに目的のページへ簡単にアクセスできるように、視覚的にわかりやすく整理されたサイト構造を意識することが求められます。
さらに、モバイル端末でのアクセスが多い場合には、モバイルファーストのアプローチを取り入れたUI設計が非常に重要です。
スマートフォンやタブレットでも快適に操作できるよう、モバイル向けに最適化されたレイアウトやナビゲーションを考慮することが、UXの向上につながります。
シンプルなサイト構造を実現することで、ユーザーは必要な情報にすばやくアクセスでき、無駄なストレスを感じることなく、利便性が向上するのです。
サイト構造について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
(2)アクセシビリティへの対応
アクセシビリティとは、すべてのユーザーが必要な情報に簡単にアクセスし、利用できることを指します。
具体的な施策は、以下の通りです。
- コントラスト比の調整
- スクリーンリーダーへの対応
- 配色やテキストサイズの調整
- ボタンのタップエリアの確保
これらの工夫を取り入れることで、ユーザーの視認性や操作性が大きく向上します。
また、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン(WCAG)に準拠したデザインを採用することで、すべてのユーザーにとって使いやすいUIを提供できるようになります。
(3)レスポンシブデザインの採用
デバイスごとにユーザーの視覚的な体験が異なることを常に意識する必要があります。
例えば、パソコンで表示した場合とスマートフォンで表示した場合では、同じデザインでも表示される内容やレイアウト、フォントサイズなどが大きく異なります。
このため、レスポンシブデザインを採用することは非常に重要です。
特に、モバイルデバイスでのインターネット閲覧が増えている現在では、スマートフォンの画面に最適化された縦スクロール型のデザインに注目が集まっています。
また、小さな画面においては、ボタンのサイズや配置も重要なポイントです。
ユーザーが誤ってクリックしないように、適切なサイズと位置にボタンを配置し、タッチ操作が快適に行えるように設計するようにしましょう。
(4)ユーザーからのフィードバックを反映する
UI改善を行う際には、ユーザーからのフィードバックを積極的に取り入れることが大切です。
具体的な施策としては、アンケート調査やヒートマップ分析、ユーザーインタビューなどが挙げられます。
さらに、アクセス解析やヒートマップツールを活用することで、ユーザーの行動パターンを把握し、どのタイミングでユーザーが離脱しているのかを把握することも可能です。
また、ユーザーの意見をプロダクトに反映させるために、公開前に再度試用してもらい、改善を繰り返すことも重要です。
このように、ユーザーの声に耳を傾けることで、UIの利便性がさらに向上し、最終的にユーザー満足度を高めることにつながります。
6.UI改善をするための依頼先

上記で見てきたように、商品・サービスのUI改善を図るためにはテクニカルな要素が数多くあります。
特にWebサイト制作はもとより、ユーザー心理の把握や数値解析などのマーケティングに関する知見も必要不可欠です。
そのため、自社内にこれらの知識や経験に習熟している人員を確保できない場合には、外部に依頼することがおすすめです。
UI改善を外部に依頼するときは、フリーランスか制作会社の2つの依頼先があります。
どのようなクオリティを求めるのかはもちろん、予算などの要素によっても、どちらに依頼するのが適しているのかは異なります。
以下では、それぞれのメリットやデメリットについて解説します。
(1)フリーランス
フリーランスは後述する制作会社に比べて、一般的にコストが低いため、予算が限られているプロジェクトや小規模な案件を依頼するのに適しています。
また、フリーランスは、個人で仕事をしている分、プロジェクトの途中での変更や急な依頼にも柔軟に対応できる点が大きな強みです。
もっとも、大規模なUI改善を行うプロジェクトの場合や本格的な集客や顧客満足度の改善を図りたい場合には必ずしも適していないケースがあります。
さらに、フリーランスは経験やスキルに個人差があるため、成果物の品質にばらつきが出る可能性があることも懸念点のひとつです。
信頼できるフリーランスを見つけるためにも、過去の実績やポートフォリオをしっかり確認し、慎重に選定することが重要です。
(2)制作会社
制作会社では、UI/UXの専門知識を持つプロフェッショナルなチームが対応するケースが多いです。
デザインから開発、リリースに至るまでの全工程を一貫してサポートする体制が整っているため、大規模なプロジェクトに適しています。
また、ユーザーの行動や心理の分析・把握、改善後の運用といった幅広い作業を依頼できることも多く、専門的なフォローを受けたい場合にもおすすめです。
もっとも、制作会社に依頼する場合には、フリーランスに依頼する場合と比較すると、一般的にコストが高くなる傾向があります。
制作会社やプランによっても異なりますが、概ね数百万円から数千万円の費用がかかることも珍しくありません。
さらに、UIの改善後の運用施策の立案・実行については別途費用がかかる場合もあり、継続的にランニングコストが発生するケースがあることにも注意が必要です。
特に長期間にわたるプロジェクトでは予算が予想以上に膨らむ可能性があるため、事前に十分な予算管理と計画が重要です。
また、予算が限られている場合には、複数社に見積もりを依頼し、費用項目や相場について比較・検討することがおすすめです。
なお、フリーランスに依頼する場合と同様に過去の実績を確認することも重要です。
特に自社が属する業界や自社コンテンツに近い商品・サービスのUI/UX改善についての支援実績があるかどうかをWebサイトやミーティングの際に確認しておきましょう。
まとめ
UIとはユーザーインターフェースの略称で、ユーザーが目にするデザインや操作性を意味します。
UIが悪い場合はユーザーの離脱の原因となってしまうため、早急な改善が欠かせません。
本記事で解説したポイントを参考に、UI改善に取り組んでみてください。
UI改善を含めたサイト制作や運用について相談したい方は、TMS Partners株式会社へご相談ください。
TMS Partners株式会社は、UI改善を含め、数々の企業のサイト制作を実施しています。
数々の企業を支援した実績を活かして、サイト制作やSEO対策、広告支援まで、幅広い内容の支援が可能です。
問い合わせは無料なので、まずは以下の問い合わせフォームより気になることや質問をお寄せください。
お問い合わせはこちら