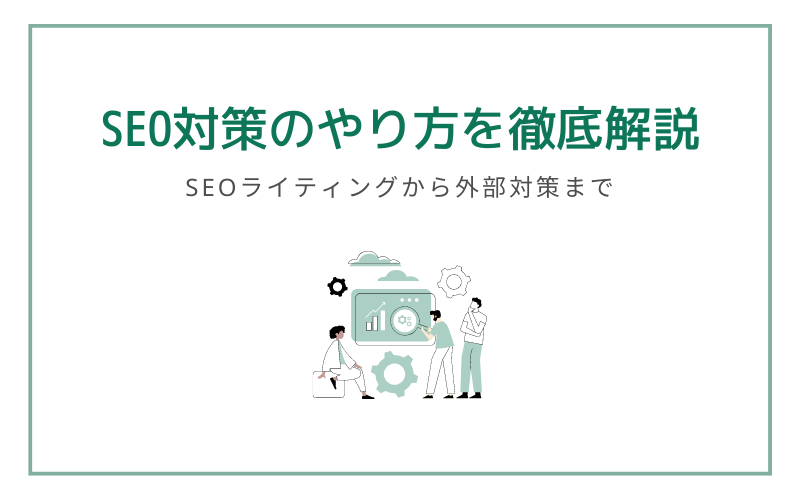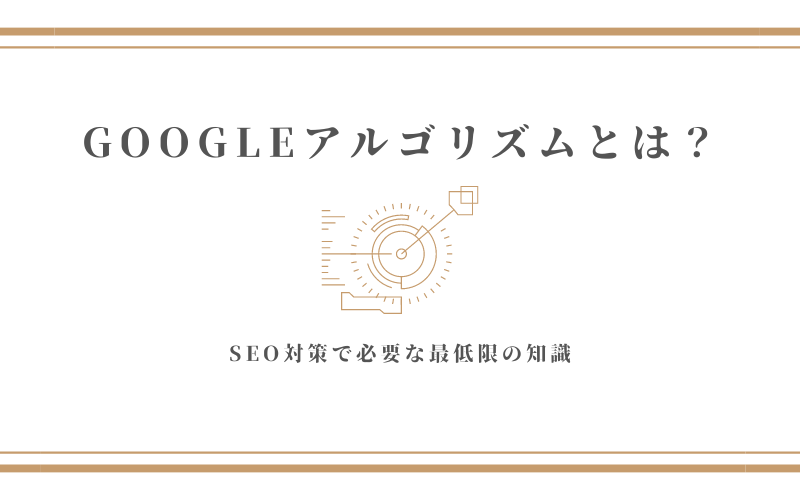検索エンジンの仕組みから学ぶSEO対策|自社サイトの集客力を高める第一歩

「検索エンジンの仕組みをわかりやすく知りたい」
「自社の検索順位が上がらない理由を把握したい」
企業の経営者やマーケティング担当者の中にはこのような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
検索エンジンとは、ユーザーが知りたい情報を瞬時に探し出すための仕組みであり、Webマーケティングを行う上で理解しておくべき重要な媒体の1つです。
特にSEO(検索エンジン最適化)に取り組む企業にとっては、検索エンジンの仕組みを知ることが、効果的なマーケティング施策へとつながります。
しかし、検索エンジンの仕組みは専門的な用語も多く、「結局何をすればよいのか」が曖昧なままになっている方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、検索エンジンの基本的な仕組みから、検索順位が上がらない主な原因、そして今日から実践できる対策まで、初心者にもわかりやすく解説します。
最後までお読みいただくことで、自社サイトの集客力を高めるための第一歩を踏み出せるようになるはずです。
1.検索エンジンとは

検索エンジンとは、ユーザーが情報を探すためのプラットフォームのことを指します。
具体的には、検索ボックスにキーワードを入力することで、そのキーワードと関連性の高いWebページや画像などの情報を一覧表示する仕組みを持つシステムです。
例えば、「東京 観光 スポット」と検索すれば、東京の観光地に関するブログ記事や旅行サイト、地図情報などが一気に表示される仕組みになっています。
現在、世界中で広く利用されている検索エンジンには、「Google」や「Yahoo!」、「Being」などがあります。
もっとも、圧倒的なシェアを誇っているのがGoogleです。
Web解析サービス「Statcounter Global Stats」の調査によると、2025年時点でGoogleの世界シェアは約90%にのぼります。
このため、SEO(検索エンジン最適化)対策を行う上では、まず「Googleを基準に考える」ことが大切です。
それぞれの検索エンジンについての違いや特徴は、次章で詳しく解説していきます。
2.検索エンジンの主な種類

検索エンジンにはいくつかの種類がありますが、日本国内で特に多くのシェアを持つのは以下の3つです。
- Yahoo!
- Bing
ここでは、それぞれの検索エンジンの特徴や違いについて解説します。
(1)Google
先述したように、Googleは、世界中で最も多く利用されている検索エンジンです。
日本国内でも、検索シェアの約70%以上を占めており、Web集客やSEOを行う上では、まずGoogleの仕組みを理解することが最も重要です。
なお、Googleの検索結果は、「検索アルゴリズム」と呼ばれる高度なプログラムによって決定されます。
このアルゴリズムは以下のような点を考慮して、どのページを上位に表示するかを判断しています。
- コンテンツの質
- モバイル対応状況
- 表示速度
- 外部リンクからの評価
また、Googleは常にユーザー体験の向上を目指しており、検索アルゴリズムも定期的にアップデートされています。
そのため、SEOの順位が急に下がったり上がったりする現象が発生することもあります。
こうした背景には、Googleの企業理念である「ユーザーファースト(ユーザーの利便性を最優先にする)」が強く関係しているからです。
(2)Yahoo!
Yahoo! は、日本国内で根強い人気を持つ検索エンジンの1つです。
特に中高年層を中心に利用されており、ポータルサイトとしての機能(ニュース、天気、ショッピング、オークションなど)も豊富で、多くのユーザーの「入口」として機能しています。
Yahoo!は、2011年以降Googleの検索エンジン技術(アルゴリズム)を採用しています。
そのため、検索結果の内容も基本的にはGoogleと非常によく似ています。
もっとも、検索結果の見せ方や表示されるコンテンツには、Yahoo!独自のフィルターや調整が加えられているため、検索結果が同一になることはありません。
具体的には、以下のような違いが挙げられます。
- Yahoo!はニュース、天気、ショッピング情報など、自社のサービスと関連するコンテンツを優先的に表示する傾向がある
- 広告やおすすめ枠の位置がGoogleとは異なる
- ユーザー属性(年齢・趣味)に応じた最適化が行われている可能性がある
このように、Yahoo!は単なる検索エンジンではなく、総合情報プラットフォームとして機能しているという点がGoogleとの大きな違いです。
また、Googleは「ユーザーファースト」という理念に基づき、純粋な検索体験の最適化を重視しています。
Yahoo!は検索以外のサービスが充実しているため、検索以外のサービスを楽しみたいユーザーに向いてる検索エンジンと言えます。
(3)Bing
BingはMicrosoft(マイクロソフト)社が提供する検索エンジンで、Googleに次ぐ世界的なシェアを誇ります。
特にアメリカを中心に一定のユーザー数を持ち、日本国内でもWindowsパソコンの標準ブラウザを通じて利用されるケースが少なくありません。
Bingは、Microsoft製のブラウザ「Internet Explorer」や「Microsoft Edge」の初期設定の検索エンジンとして設定されています。
また、Windowsの検索ボックスや音声アシスタント「Cortana(コルタナ)」とも連携しており、パソコン操作中に自然とBingを利用しているケースも多く見られます。
つまり、Windowsユーザーにとって最もアクセスしやすい検索エンジンである点が、Bingの強みの1つです。
なお、BingはGoogleとは異なる独自のアルゴリズムを用いており、「ユーザーの意思決定を支援する」という開発コンセプトのもと、検索結果の表示方法に特徴があります。
例えば、以下のような特徴が見られます。
- 検索結果に多くの動画を含める傾向があり、ユーザーの意図に合った動画コンテンツを優先的に表示する
- 大きなサムネイルで動画が並び、マウスを合わせるとプレビュー再生が可能
- 動画検索において、解像度・再生時間・投稿日付などの詳細な条件で絞り込みができる
このような特徴により、「視覚的な情報」や「動画検索」を重視するユーザーにとって使いやすい設計となっています。
3.検索エンジンの仕組み

検索エンジンは以下の3つのステップで構成されています。
- クローリング
- インデックス
- 検索結果の表示
これらのプロセスを経ることで、新たに作成したWebページが検索結果に反映されるようになります。
ここでは、それぞれのステップについてわかりやすく解説します。
(1)クローリング
クローリングとは、クローラーと呼ばれるロボット(プログラム)が、リンクを辿ることによって、インターネット上にあるWebページの情報を収集するプロセスを指します。
インターネット上では常に新たなWebページが公開されていますが、クローラーにページ情報を取り込んでもらうこと(クローリングを受け入れること)で、検索エンジンは初めてWebページの存在を知ることになります。
そのため、まずクローラーにWebページを発見してもらうことが必要です。
もっとも、IDやパスワードが必要な会員専用ページやrobots.txtやmetaタグでクローラーを拒否しているページなどは、クローラーがアクセスできない可能性があります。
そのため、「Webに公開すれば自然と検索される」と思い込まず、クローラーに正しく情報を届けるための設計が欠かせません。
(2)インデックス
インデックスとは、クローラーが収集したWebページの情報を、Googleのデータベースに分類・整理して登録するプロセスのことを指します。
このプロセスによって、初めてWebページは検索結果に表示される候補となります。
つまり、インデックスされなければ、そもそもGoogleの検索結果には出てこないということです。
ページがインデックスされるには、検索エンジンが「このページは検索結果に表示する価値がある」と判断する必要があります。
例えば、ページのコンテンツがオリジナルで有益であることや、適切なタイトルタグやメタディスクリプションが設定されているページは比較的インデックスされやすいと言われています。
一方で、コンテンツが重複している、あるいは品質が非常に低い、ページに「noindex」タグが設定されているページは、検索結果に反映されません。
自身が制作したWebページやコンテンツがインデックスされているかどうかは、Google Search Consoleを使うことで確認することが可能です。
(3)検索結果の表示
検索結果の表示とは、ユーザーが検索キーワードを入力したときに、検索エンジンがインデックスされたページの中から、最も関連性が高く、有益であると判断したページを順位づけして表示するプロセスです。
この際に活用されるのが、Google独自の「検索アルゴリズム」です。
検索アルゴリズムは、数百にもおよぶ評価指標(ランキングシグナル)をもとに、どのページを上位に表示するかを判断しています。
例えば、以下のような要素が検索順位に影響を与えると言われています。
- キーワードとコンテンツの関連性
- ページの専門性や信頼性
- 被リンクの質と量
- モバイル対応やページの表示速度
- ユーザーの検索意図との一致度
これらの要素をもとに、検索エンジンは「ユーザーの知りたい情報を、できるだけ正確かつ迅速に届ける」ことを目指して、最適なページを選び出しているのです。
したがって、SEO対策においては、インデックスされるだけでなく、「検索アルゴリズムに評価される」ことが非常に重要です。
検索結果に自分のページを上位表示させたい場合は、ユーザーの検索意図を考慮しながら、価値あるコンテンツを作成することが不可欠と言えるでしょう。
4.SEOの基本的な対策

SEO(検索エンジン最適化)を効果的に進めるためには、いくつかの基本的なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、特に重要な4つの対策について解説します。
- キーワード選定
- タイトル・メタディスクリプション
- 内部リンクとサイト構造
- 表示速度・モバイル対応
(1)キーワード選定
最初に行うべきSEO対策は「キーワード選定」です。
ユーザーが検索エンジンでどのような言葉を使って情報を探しているのかを把握し、そのキーワードに対してコンテンツを最適化することで、検索結果に表示されやすくなります。
なお、選定の際は以下のような視点が重要です。
- 検索ボリューム
- 競合性
- 検索意図
また、これら3つの視点を踏まえたうえで、ツールを活用しながら具体的なキーワードを選定することが重要です。
例えば、Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどを使い、具体的でニーズの強い関連キーワードを洗い出すことで、より効果的なSEO対策が可能になります。
(2)タイトル・メタディスクリプション
検索結果に表示されるタイトルとメタディスクリプションは、ユーザーのクリック率に大きく影響します。
タイトルは、ページの主題を端的に伝える役割を担っているため、重要なキーワードを含めるのが基本です。
また、ディスクリプションは検索結果の説明文として表示される部分で、ページ内容の要約やメリットを伝えます。
どちらも、ユーザーに「このページを見てみたい」と思わせる工夫が必要です。
(3)内部リンクとサイト構造
サイト内のページ同士を適切にリンクさせることで、検索エンジンにとってページの関係性が分かりやすくなり、クロールやインデックスの効率も向上します
例えば、関連性の高いページ同士を内部リンクでつなぐ、カテゴリーや階層を整理してシンプルなサイト構造にするといった工夫が有効です。
内部リンクやシンプルなサイト構造は、クロールや御デックスの効率を向上させるだけでなく、ユーザーの回遊性を高める上でも効果的です。
(4)表示速度・モバイル対応
検索エンジンは、ユーザー体験(UX)を非常に重要視しています。
そのため、ページの読み込み速度が遅いWebサイトや、スマートフォンなどで見にくいWebページなどは検索順位が下がる可能性があります。
対応策としては、画像の軽量化や、不要なスクリプト・プラグインの削除などが挙げられます。
また、モバイルファーストデザインを取り入れることも有効です。
Googleの「PageSpeed Insights」や「モバイルフレンドリーテスト」などのツールを使って改善点をチェックしましょう。
5.改善ポイントの見つけ方

低品質コンテンツを見つけるには、Google Search Consoleの「クロール済み – インデックス未登録」に分類されているページを確認する方法があります。
この一覧に表示されるページは、Googleのクローラーがページを読み取ったものの、インデックス登録の対象外と判断されたページです。
登録されなかった理由はさまざまですが、多く見られるのは「コンテンツの内容が薄い」「情報の価値が低い」といった品質面の問題です。
つまり、Googleの品質基準を満たしていないと判断された可能性があるということです。
もっとも、ここに表示されるすべてのページが「低品質」と断定されるわけではなく、以下のような理由も含まれます。
- 情報量が少なく、ユーザーにとって価値が薄いページ
- RSSフィードや技術的なURL
- 他ページと内容が重複しているもの
- 誤判定(Google側の自動判断によるもの)
改善の第一歩として、Google Search Consoleの「インデックス > ページ > ページのインデックス登録」画面を開き、リストに表示されたページを1つずつ精査しましょう。
内容が薄い・重複している・古い情報しか載っていないページが見つかった場合は、内容の追加・リライト・統合などを行い、検索エンジンにとってもユーザーにとっても有益なページに仕上げることが大切です。
6.外注と内製のバランス

SEO対策を進めるうえで重要なのが、「どこまでを社内で対応し、どこからを外部に委託するのか」という体制のバランスです。
すべてを内製で行うには専門知識やリソースの確保が必要である一方で、すべてを外注してしまうとコストが膨らむだけでなく、思ったような成果が出ない可能性もあります。
そこで、自社の自社の強みを活かしながら、足りない部分を外部で補うというハイブリッドな対応が効果的です。
内製の強みは、自社の商品や顧客を深く理解していることです。
コンテンツ制作を内製化することで、オリジナル性の高いコンテンツが作れるだけでなく、社内にノウハウも蓄積されます。
ただし、専門知識がないと成果が出にくく、リソース不足になることも念頭に置いておいてください。
一方で外注のメリットは、SEOに詳しいプロに任せることで、効率的かつ質の高い対策ができる点です。
もっとも、自社の内容を正しく伝えるためには、定期的なやり取りが必要です。
そこで、おすすめなのは記事制作などは社内で行い、戦略やキーワード選定、技術的な対策は外注する「ハイブリッド体制」です。
社内の強みと外部の専門性をうまく組み合わせることで、無理なく効果的なSEOが実現できます。
まとめ
本記事は、検索エンジンの基本的な仕組みから、検索順位が上がらない主な原因、そして具体的なSEO対策について解説しました。
検索エンジンは、ユーザーが知りたい情報を瞬時に探し出すための仕組みであり、Webマーケティングを行う上で理解しておくべき重要な媒体の1つです。
特にSEOに取り組む企業にとっては、検索エンジンの仕組みを知ることが、効果的なマーケティング施策へとつながります。
しかし、検索エンジンの仕組みには専門的な知識やノウハウが必要になることが多いため、自社でSEO対策を行うのが難しい場合は、外部に依頼することも検討しましょう。
特にSEO対策に強みや実績を持つ企業に依頼することで、費用対効果を高めることができます。
専門的なサポートを受けたい方は、TMS Partners株式会社へ問い合わせください。
TMS Partners株式会社は、SEO対策をはじめ、サイト制作や広告運用など、幅広い支援を行っています。
問い合わせは無料なので、まずは以下の問い合わせフォームより気になることや質問をお寄せください。
お問い合わせはこちら