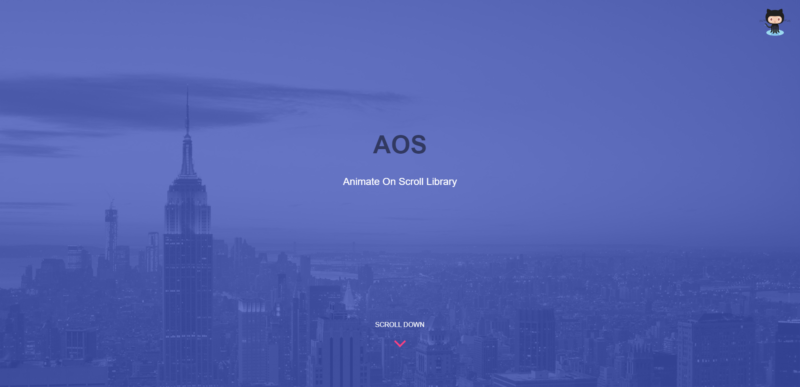アクセス減の原因になる?移管リニューアルの設定ポイント
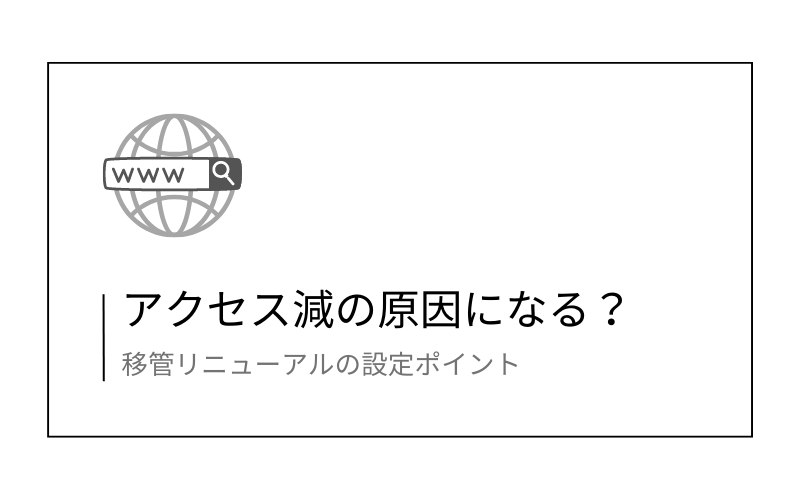
「移管リニューアルをするとアクセスが減ってしまった…」
「アクセス数を減らさないようにするためにはどんな方法があるの?」
今回の記事では、移管のタイミングでSEOの評価を引き継ぐためにはどうすればいいのか、アクセスを維持するためにはどのような作業を行っていけばいいのか、についてお伝えします。
上記内容と合わせて、原因がアップデートにあった時にはどのような対応をすべきか、についてもまとめています。
このような悩みを持っている方は、この先の内容をチェックしてみてください。
サイトへのアクセスが減るケース
サイトへのアクセスが減る原因は、以下のようなケースです。
- アクセスが減っているサイトのURLドメイン変更
- 新サイトが上位に表示されない
- アクセス評価の引き継ぎがわからない
- アクセスや問い合わせが急に減った
上記に該当される方は、自社で行った作業が原因か、またはアップデートの内容の影響を受けている可能性があります。
Webサイトの移管リニューアルとは、ウェブサイトのデザイン・URLをアップデートすること指します
Webサイトのリニューアルをする際に、コンテンツの量に変化があったり、URLを旧サイトから新サイトへ引っ越し・変更する作業内でトラブルが起こりやすいのです。
(→この部分の意味がわからなかったので日本語あやしいです)
移管リニューアル時の設定ポイント
移管をするにあたって必ず設定しておきたいポイントは、旧サイトから新サイトにリダイレクト処理を行った上でGoogleサーチコンソール側に具体的に設定する点です。
また、Webサイトの移管リニューアルにおいて意識しておきたい点は、旧サイトから新サイトに対して評価を引き継ぐ、つまり、Googleに上位表示されている自社のページやキーワードといった情報を、旧サイトから新サイトに引き継ぐ設定を行なわなければならない点です。
リニューアルするということは、Webサイトをガラっと変えて、全く違うWebサイトになるというイメージです。
また大きくリニューアルするケース以外にも、WordPressのカテゴリー変更のようにカテゴリーのURLだけが変わる場合や、旧サイトから新サイトでURLの一部だけが変わるような小さい規模のリニューアルの場合もあります。
ただ、ここで注意すべき点は、大きな変更も小さな変更も変わらず評価を引き継ぐ設定を行う必要があるということです。
では、具体的にどのような作業を行っていくのか説明します。
移管の作業内容
移管の際は以下の作業を行いましょう。
- 旧・新コンテンツの対応付け
- 旧サイトから新サイトへのリダイレクトとセットでGoogleサーチコンソールにおけるサイト移管
- WordPress上のインデックス設定
- 新サイトマップの送信
上記4つは何ですかね??以下で説明しているものが、1.旧・新コンテンツの対応付け2.301リダイレクト設定3.時間設定4.サイトマップ送信なので、それに変更してもいいでしょうか?
これらの4つの作業を行っていく必要があります。
では早速、順に説明していきます。
#1:旧・新コンテンツの対応付け
最初の作業としては、旧新コンテンツの対応付けです。
旧・新コンテンツの対応付けとは、旧URLに表示されている位置と新URLに表示されるページを、どことどのページを紐づけるか、つまり旧サイトの特定ページにアクセスしたときに、新サイトのどのページが表示されるべきなのかを紐づけていくという作業になります。
この中に出てくるリダイレクトが、サイトマップの設定においては旧ページから新ページにリダイレクトさせる情報の紐付けが必要になることから、最初はこの作業から取りかかることをおすすめします。
大規模なサイトリニューアルの場合は、旧サイトから新サイトに紐付けを行う際に旧サイト側がないケースがあり、一方で新サイト側がないケースというものも想定されます。
旧サイト側のページがないときは、そもそも新サイト側で評価が付いていくような形になるので、特段何も作業は必要ありません。
ただ新サイト側がないとき旧ページにアクセスすると、リダイレクト設定を行わないとそのままURLエラーとなってしまって、評価がそのまま落ちてしまうことにもなりかねませんので、おすすめのリダイレクト先の選択肢としてはトップページです。
新サイトのトップページにリダイレクトさせることが一つになります。
ページの内容や構成が似ている新サイト側のページです。
なぜ似ているページを選ぶかというと、旧ページにも何らかのキーワードや評価が紐づいている可能性があります。
旧サイトに載っているキーワードは、そのページに掲載されている文書や画像です。
文書やコンテンツの中身に対応したキーワードが紐づいていくわけです。
例えば、あなたが整骨院のWebサイトを運営している場合、肩こりや肩首の痛みのページが付いている、そういったキーワードのページに紐づいているわけです。
これらのキーワードをより生かすためには、新サイト側にも同じように肩こりや首の痛みというような文章が必要になってくるわけです。
こうすることで、旧サイトの旧ページに載っているキーワードの評価を、なるべく損なわないような形で緩和を進めることができます。
これが1つ目の旧新コンテンツの対応付けです。
#2:Googleサーチコンソールにおけるサイト移管
#3:WordPress上のインデックス設定
#4:新サイトマップの送信
301リダイレクト設定
2つ目が、301リダイレクト設定になります。
301リダイレクトが何かというと、そのURLにアクセスしたときに自動的に新WebサイトのURLに飛ばす設定を指します。
301に関しては、旧サイトから新サイトに対して、元々のページの評価を引き継ぐことができます。
引き継がれる期間はページのクローラーが回ってくる頻度にもよるのですが、おおむね速いサイトであれば2週間以内、遅くても2、3カ月以内にはすべての評価が引き継がれることが多いです。
注意が必要なのはそれまでです。
旧Webサイトのコンテンツは、残したままにする必要があるということです。
つまり、評価が引き継がれないまま旧サイトを閉じてしまうと、そのタイミングで旧サイトにアクセスしたユーザーには404ページが存在しないよとエラーが返ってきてしまうので、そのURLに載っていたページやキーワードの評価は失われてしまいます。
ですので、旧Webサイトから新Webサイトに対して評価が引き継がれたと確認されるまで、旧サイトのコンテンツはそのままにしておくことをおすすめします。
どのような形で評価が引き継がれたのか確認できるかというと、Googleアナリティクスのアクセスが1日0か1の状態であったり、ビジネスを使って旧サイトのURLを調査した結果、キーワードが全てなくなっているよというような状態が確認できればリダイレクトの設定が済み、評価も引き継がれたと判断することができます。
リダイレクトの設定を行う際は.htaccessに行動を追記する場合もあれば、WordPressを使っている場合はリダイレクションと呼ばれるリダイレクトを管理するプラグインもあります。
いずれかの方法によって、リダイレクトの設定を行いましょう。
リダイレクトの設定が完了された後に旧Webサイトにアクセスしてみて、新Webサイトに自動的にページが切り替わるようであれば、リダイレクト設定はきちんと行われている形になります。
こうすることで、少し時間を要するバナーの旧サイトから新サイトに評価が引き継がれる形です。
時間設定
3つ目が、Googleサーチコンソールの時間設定になります。
Googleサーチコンソール上は、Webサイトを移管した時にGoogle側に通知する機能があります。
その通知する機能を使うことで、旧WebサイトはこのURLで、新サイトはこのURLでというようなことをGoogle側に通知送信することで、Googleサーチコンソール側では時間の追跡を行うことができることになります。
必ず忘れないように設定しておきましょう。
サイトマップ送信
4つ目が、Googleサーチコンソールにサイトマップを送信する作業です。
新Webサイトに新規Webサイトを作成した後、そのURLを元にGoogleサーチコンソールに登録するわけですけれども、併せて行っておきたいのがサイトマップ送信になります。
サイトマップでGoogle側にサイトの構造やページの内訳を通知するような機能になりまして、それを行うことによってダイアログサイトがページの中身や構造をGoogle側に通知することによって、より早くGoogleの検索エンジンに新Webサイトの内容を評価されるようになってきます。
サイトマップの刷新自体は、新Webサイトでも今後更新が発生するでしょうから、Webサイトが追加されたり、更新されたタイミングで自動的に通知されるような設定を行っておくことをおすすめします。
WordPressであれば、サイトマップは自動的に作成してくれるようなプラグインがありますので、そのプラグインを使ってGoogleサーチコンソール側と連携させていった上で、自動的にサイトマップが設置されるような仕組みを構築しておくことをおすすめします。
これが4つ目のサイトマップを表示させる作業になります。
この4つの作業を行っていただいて、旧サイトのWebサイトの評価が新サイトに無事に移管されているようであれば移管作業自体は完了になります。
移管リニューアルでよくある失敗
ここでは、よくある落とし穴とも言える、注意しておきたい作業を紹介します。
- リダイレクト設定・Googleサーチコンソールへ通知
- 下層ページの紐付け設定
- リダイレクトの修正
- 評価の引き継ぎ
- アップデートの影響
上記に心当たりがある方は、確認してみましょう。
リダイレクト設定・Googleサーチコンソールへ通知
1つ目は、旧サイトから新サイトへリンクを貼っただけでは完了しないのか、という点です。
昔のサイトでは、”このWebサイトは新サイトにリニューアルされました”という表示を見かけることがよくありました。
しかし、この設定自体に評価を引き継ぐことは間接的で、多くの場合は仮想ページに関してもトップページに遷移させているケースがよく見られます。(→ここの意味がわかりません…)
それぞれの評価が紐づくGoogleの評価を引き継ぐためには、旧サイトと新サイトをリダイレクトの設定で行っていく必要があります。
リンクを張るだけの対応だと、2週間~2、3カ月といった期間で評価がすべて引き継がれることはありません。
また新サイトが上位に表示されたり、サービス名を検索したときに新サイトのほうが旧サイトよりも評価が高く表示されるには、多くの時間を要してしまいます。
リンク設定で移管を行うのではなく、リダイレクト設定及びGoogleサーチコンソール側への通知を設定するようにしましょう。
★下層ページの紐付け設定
2つ目は、下層ページも全てリダイレクトを貼らないといけないかです。
一括でトップページにリダイレクトさせるだけでは駄目なのかです。
こちらも先ほどと同様で、新サイトと旧サイトの下層に載っているキーワードや順位の内訳は、あくまで旧サイトの下層ページに表示されている文章、コンテンツの中身に依存してキーワード評価が付くものになります。
ですので、旧サイトの下層ページに載っているコンテンツの中身が新サイトのトップページに全て載っていれば、別に旧サイトから新サイトのトップページに対してリダイレクトさせたとしても、ページ評価は引き継がれることになります。
しかし、下層ページの内容が全て新サイトのトップページに載っていることは往々にしてあまり見られないケースです。
ですので、新サイトのトップページは、旧サイトの下層ページよりも古い文章量や特定のキーワードに対する文章量、コンテンツの量自体も少なくなることがほとんどなので、必ず下層ページの紐付けも行っていくようにしましょう。
これが2つ目の下層ページの紐付け設定です。
リダイレクトの修正
3つ目は、既に間違って貼ったリダイレクトを修正できるかです。
こちらに関しては、リダイレクトセットを貼り直すことで、一定程度評価の改善が見込まれます。
ですので、間違ったURLにリダイレクトさせてしまったと発覚したら、なるべく早く新サイトと旧サイトの紐付けを確認した上で正しい紐づけに修正し、リダイレクトの設定を見直すことをおすすめします。
評価の引き継ぎ
4つ目は、すべての作業を行ったものの、なかなか評価が引き継がれないです。
これはどうなっているのかというと、旧サイトから新サイトへのURLの紐付け及びリダイレクト設定は、あくまでGoogle側に正しく評価が引き継がれる設定をするに過ぎません。
実際の評価を決めるのはGoogleの検索エンジンになりますが、検索エンジンが順位を認知するまではGoogleクローラーが回ってきて、その内容が反映される形で検索結果が変動するわけですが、Webサイトによってはクローラーが回ってきやすい・回ってきにくいというものがあります。
これはサイトの規模感であったり、更新頻度であったり、既に付いているキーワードの順位によるものなんです。
これらの要素があまり良くないとクローラーがそれほど多く回ってこないので、結果としてGoogleの評価が旧サイトから新サイトに引き継がれる期間もより長く要することになります。
あくまで目安は2、3カ月ですけれども、ほとんどクローラーが回ってきていないようなサイトですと、それ以上の時間を要するケースがありますので、期間的に2、3カ月以上たってもこれは評価が付いていないなと感じられた場合は、設定評価の引き継ぎの設定値を、改めて見直すことをおすすめします。
アップデートの影響
5つ目は、旧サイトがアルゴリズムのアップデートを受けていて、新サイトに対して評価を引き継ぐかどうか迷っている場合はどうすればいいかということです。
これは今まで述べてきたケースよりも、若干トリッキーなケースになります。
今、旧サイトのドメインがアップデートの影響を受けていて、どこまで下がるのかまだ見えない、ただ事業進捗上は新サイトを作っていく必要がある状況下です。
この場合は、旧サイトのドメイン評価がどこまでアップデートの影響によってアクセスが落ち込むかというところが見えないわけですけど、この場合はケースバイケースの判断をさせていただくことが多いです。
よく行うのは、新サイトに対しては一定期間リダイレクトを張らず、新サイト側を先に運営しますので、旧サイトのドメイン評価が落ちついてきた。
またはアクセスの下落が落ち着いてきて、ある程度アップデートの影響を受けた後のアクセスが見えてきたタイミングで、初めてリダイレクトさせるかどうかを検討するケースです。
こうすることで、まず新サイト側上でアップデートの影響を受けずに運営することができること。
あとはアクセスで残ったドメイン評価を踏まえた上で、最終的に移管させてリダイレクト設定を行ったほうがメリットに働くのか。
それともアップデートの影響をもろに受けてしまって、ドメイン評価を引き継がないほうが新サイト側に対して影響を与えないのかという判断を、そのタイミングで下すことができる点がメリットです。
一方で、デメリットは旧サイトのアップデートの影響がそれほど悲観的なものではなかった場合です。
新サイト側の評価が付くのが遅れるというケースがあるんですけれども、遅れたとしてもリダイレクト設定を行った後は、元通り旧サイトからの評価も残っていく形になるので、リダイレクトの設定を張っていくのはそれほど大きなデメリットには働かないです。
このケースは新旧サイトを両方並存させてリダイレクト設定を貼らないまま様子を見ていくので、旧サイト側の影響が落ち着いた上で新サイト側に対して移管を行っていくかどうか検討されることをおすすめします。
アップデートの影響でアクセスが下落した場合
続いて、アップデートの影響を受けてアクセスがどんどん下落してしまっているというケースについて説明していきます。
アップデートの影響を受けてアクセスが落ち込んだ場合の対応策としては、コンテンツの品質が低い問題であったり、コンテンツの更新が何年も前だというケースであったり、Webサイトの一部でYMYL領域に関する情報を発信しているというようなことがあります。
WorldWideWeb上のページは非常に多様なトピックに関するものです。
一部のトピックはコンテンツが原因で害を及ぼすリスクが高くなります。
これらのトピックについて人々の健康・経済的安定・安全・または福利に重大な影響を与える可能性があります。
これらのトピックをYourMoneyorYourlife、またはYMYLと呼びます。
引用:「GeneralGuidelines 」
https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/ja//
searchqualityevaluatorguidelines.pdf
データの影響
いずれにしてもデータの影響です。
コンテンツの品質及びリンクの品質というものが問われるわけです。
対策としては、評価が下がっているコンテンツがGoogleアナリティクス上でアクセスが見えたり、Ahrefs上で順位の下落が確認できるわけですけれども、その対象のコンテンツを1度非表示にする、またはそのコンテンツの更新を図ってみることです。
コンテンツの更新を図っていくことによって評価が一定程度戻る可能性がありますので、まずはそのコンテンツを更新してみることでメタタイトルやアップデートをすることによってアクセスの下落を防げる可能性があります。
一度様子を見てみるという点が一つです。
リンクの数と品質
2つ目は、自社に貼られているリンクの数を増やす、または品質を高めていくということで、よく被リンク対策を行っていない記事メディアに見受けられるケースなんですけれども、コンテンツの質や量は十分あるものの、年間数が足りていないというケースです。
この場合は、コンテンツによって獲得できたアクセスをリンクの数質によって修正されてしまうケースですが、こういうケースは、やはり地道に被リンクを獲得していくほかありません。
被リンクの獲得自体も、サテライトサイトのように開設されたばかりのサイトからURLリンクを張っても、メリットどころかデメリットに働いてしまうケースもありますので、しっかりと自社との関係性が付いている取引先からリンクを張ってもらうことをおすすめします。
被リンク影響の内容については他の記事で述べていますので、併せてご参考いただければと思います。
正しい作業でアクセスは回復する
今回はWebサイトのリニューアルを行ったことで大きくアクセスが減ってしまった、どうすればいいかわからないというお悩みについて解説してきました。
Webサイトのリニューアルによってアクセスが激減している場合は、作業が間違っていたりアップデートの影響を受けてしまっているケースが見受けられますので、こうした原因別に対応を行ってみて、アクセスが回復するかどうか確かめてみられることをおすすめします。
自社で見極めが難しかったり、そもそも移管作業自体を誰かに依頼したいという場合は、弊社も多くの移管作業をご支援させていただいており、評価の引き継ぎ自体も行わせていただいた経験がございますので、お気軽にご相談いただければと思います。