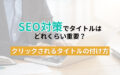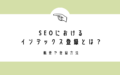リライトとは?リライト対象の選び方から具体的な検索順位改善のコツ

「リライトって結局何をしたらいいの?」
「どの記事をリライトすれば良いかわからない」
Webサイトの検索順位が思うように上がらない、アクセス数が伸び悩んでいるという悩みを抱えていませんか。
その解決策として、既存コンテンツのリライト(書き直し)が有効です。
リライトは新規記事作成よりもコストを抑えながら、検索エンジンでの評価を効率的に高めることができる手法です。
本記事では、SEO効果を最大化するリライトの方法から、具体的な施策まで詳しく解説します。
読み終えるころには、あなたのWebサイトのコンテンツを戦略的に改善し、検索順位の向上を実現できる知識が身につくでしょう。
1.リライトの概要

リライトとは、既存のコンテンツを再編集・更新し、情報の鮮度や構成を改善する作業を指します。
単純な文章の書き換えではなく、検索エンジンに評価されやすくすることで、順位やクリック率の向上を狙う戦略的な手法です。
具体的には、以下の要素から構成されます。
- 既存コンテンツの分析と課題の特定
- 検索意図に合わせた内容の最適化
- 情報の更新と構成の改善
順にご説明します。
(1)既存コンテンツの分析と課題の特定
リライトを成功させるためには、まず現在のコンテンツが抱える課題を明確にする必要があります。
GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールを活用して、検索順位、クリック率、滞在時間などの指標を分析しましょう。
数値データに基づいた客観的な評価により、改善すべきポイントが見えてきます。
また、競合サイトとの比較分析も重要な要素です。
上位表示されているページと自社コンテンツの違いを把握することで、不足している情報や構成の問題点を発見することができます。
なお、GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールの基本機能や具体的な活用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)検索意図に合わせた内容の最適化
リライトを実施する際には、ユーザーの検索意図を正確に理解し、それに応える内容へと最適化することが重要です。
同じキーワードでも、情報収集目的なのか、比較検討なのか、購入検討なのかによって求められる情報は大きく異なります。
実際に狙ったキーワードで検索をして検索結果の上位ページを分析し、どのような情報が評価されているかを把握しましょう。
さらに、関連キーワードや共起語を適切に配置することで、検索エンジンにとって理解しやすいコンテンツに仕上げることができます。
(3)情報の更新と構成の改善
リライトにより古い情報や統計データを最新のものに更新することで、コンテンツの信頼性を高められます。
特に法律や制度、技術的な内容は頻繁に変更されるため、定期的な確認と更新が必要です。
また、読みやすさを向上させるために、見出し構成や段落分けを見直すことも効果的です。
ユーザーが求める情報にすぐにアクセスできるよう、目次の設置やアンカーリンクの活用も検討しましょう。
2.リライトが果たす重要な役割

リライトは単なる文章の修正作業ではなく、Webサイト全体のSEO戦略において重要な役割を担っています。
具体的には、以下のような役割があります。
- コンテンツを最新の内容に保つ
- コンテンツの更新頻度の担保
- ユーザーニーズの反映
リライトをするにあたって、その役割をしっかり認識した上で実施することで、効果を高めることが可能です。
(1)コンテンツを最新の内容に保つ
リライトの役割は、コンテンツを最新の情報に保つことです。
情報の鮮度は検索エンジンの評価において重要な要素の1つであり、古い情報が掲載されたままのコンテンツは検索順位の低下を招く可能性があります。
また、ユーザーにとっても鮮度の低い情報を掲載していることで、そのサイトの信頼性が落ちるリスクもあるでしょう。
定期的なリライトにより、最新の情報や統計データを反映させることで、コンテンツの価値を維持することができます。
特に法律の改正や業界動向、製品やサービスの仕様などは変更になる可能性があるので、即座に更新が必要です。
また、季節性のあるコンテンツについては、事前にスケジュールを組んで更新作業を実施するなどして情報鮮度を保ちましょう。
なお、検索エンジンの仕組みについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)コンテンツの更新頻度の担保
リライトの実施により、コンテンツの更新頻度を担保して検索順位の向上を目指すことができます。
これは、定期的に更新されるサイトが検索エンジンに高く評価される傾向があるためです。
リライトを計画的に実施することで、新規記事の作成に頼らずとも、サイト全体の更新頻度を維持することができます。
これにより、検索エンジンのクローラーが頻繁にサイトを訪問するようになり、インデックスの更新速度も向上します。
あらに更新履歴を明確に示すことで、ユーザーに対してもサイトの信頼性をアピールできます。
定期的な更新により、リピーターの獲得や滞在時間の向上も期待できるでしょう。
クローラーとインデックスの関係性については、以下の記事も参考になります。
(3)ユーザーニーズの反映
リライトを重ねることで、ユーザーニーズを反映させたコンテンツを制作することができます。
ユーザーニーズは日々移り変わっていくものなので、検索行動の変化もそれに対応させなければなりません。
Googleサーチコンソールなどのデータや検索キーワードの分析を通じて、新たなユーザーニーズを発見し、それをコンテンツに反映させることが重要です。
また、コメントや問い合わせを通じて得られるユーザーの声も、リライトの貴重な材料として反映させましょう。
ユーザーが実際に抱いている疑問や課題を解決する内容を追加することで、コンテンツの価値を大幅に向上させることができます。
このようなユーザー視点での改善により、検索エンジンからの評価も自然と高まっていきます。
3.リライトによって得られるメリット

リライトを戦略的に実施することで、さまざまなメリットを得ることができます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- ユーザーニーズの反映による検索順位向上
- 情報の鮮度や正確性の維持による評価の獲得
- コンテンツの重複対策になりペナルティを回避できる
- クリック率や離脱率などの課題を解決できる
- 新規記事の作成よりもコストを削減できる
- インデックス済みの記事のためクロールされやすい
これらには、ユーザーに向けられたものがある一方、検索エンジンや検索結果の順位を意識したものもあります。
限られたリソースの中では、新規コンテンツの制作には限界がありますが、リライト施策を適切に運用することによって、新規コンテンツの制作に準じた効果を得ることも期待できるでしょう。
(1)ユーザーニーズの反映による検索順位向上
リライトにより検索ユーザーの意図に合致したコンテンツへと改善することで、検索順位の向上が期待できます。
Googleのアルゴリズムは、ユーザーの満足度を重視しているため、検索意図に適合したコンテンツほど高く評価される傾向があります。
具体的には、検索キーワードに対する答えを明確に提示し、関連する情報も網羅的に含めることが重要です。
また、ユーザーが求める情報の深度に応じて、初心者向けから専門家向けまで段階的に情報を提供することも効果的です。
このような改善により、検索結果における表示順位の向上だけでなく、クリック後の満足度も高められます。
なお、Googleのアルゴリズムを構成する要素やアルゴリズムを意識した効果的なSEO対策については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)情報の鮮度や正確性の維持による評価の獲得
リライトで最新かつ正確な情報を提供することで、検索エンジンからの信頼性評価を獲得できます。
特に、YMYL(Your Money or Your Life)領域のコンテンツにおいては、情報の正確性が検索順位に大きな影響を与えます。
具体的には、法律や経済、医療などに関するコンテンツがこれにあたります。
このようなジャンルでは、統計データや法令情報、業界の動向などを定期的に更新することで、コンテンツの権威性を維持することが可能です。
また、信頼できる一次情報源からの引用を増やすことで、コンテンツの信頼性をさらに向上させることができます。
このような取り組みにより、長期的に検索順位を安定させることにもつなげることができるでしょう。
(3)コンテンツの重複対策になりペナルティを回避できる
類似したテーマで複数の記事を作成している場合、リライトによる統合や差別化が可能です。
重複コンテンツは検索エンジンからペナルティを受ける可能性があり、サイト全体の評価低下につながります。
しかし、リライトで既存記事の内容を整理し、重複部分を削除または統合することで、この問題を解決することができます。
また、各記事の独自性を高めることで、サイト内での競合を避け、それぞれの記事が適切に評価されるようになります。
このようなリライト時の情報整理により、サイト全体のSEO効果を最大化することが可能になります。
なお、重複コンテンツと評価される可能性があるものの特徴や具体的な改善方法のポイントについては、以下の記事が参考になります。
(4)クリック率や離脱率などの課題を解決できる
リライトによってタイトルやメタディスクリプションを改善すると、検索結果でのクリック率の向上が期待できます。
また、コンテンツの構成や読みやすさを改善することで、ページの離脱率を低下させることも可能です。
例えば、ファーストビューの改善やユーザーが求める情報への誘導を最適化することで、ユーザー体験を大幅に向上させることができます。
これらの指標の改善は、直接的にSEO効果につながるため、継続的な監視と改善が重要です。
クリック率を向上させるためのタイトルのつけ方のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(5)新規記事の作成よりもコストを削減できる
リライトで既存のコンテンツを活用することで、ゼロから記事を作成するよりも大幅にコストを削減することが可能です。
リサーチ時間の短縮や、既存の構成を活用できるため、効率的に作業を進めることができます。
また、既に検索エンジンから評価を獲得している記事をベースとするため、成果が出やすいのもリライトのメリットです。
限られた予算やリソースの中で最大の効果を求める場合、リライトは非常に効率的な施策といえるでしょう。
(6)インデックス済みの記事のためクロールされやすい
リライトは、インデックス済みの記事に対して実施するため、クロールが早い可能性があることです。
既にGoogleにインデックスされている記事は、新規記事と比較してクローラーに発見されやすい状態にあります。
リライト後の更新も比較的早期に反映されるため、改善効果を素早く確認できます。
また、既存のバックリンクや内部リンクも活用できるため、ページの権威性を維持しながら改善を進めることもできます。
新規記事の場合、インデックスされるまでに時間がかかることも多いため、この点は大きなアドバンテージです。
継続的な改善サイクルを回すことで、サイト全体の評価向上にもつながるでしょう。
4.リライトすべきコンテンツの選び方

効果的なリライトを実施するためには、適切なコンテンツの選択が不可欠です。
すべての記事を無作為にリライトするのではなく、データに基づいて優先順位を決定することが重要です。
具体的には、以下のようなコンテンツに対してリライトを実施するようにしましょう。
- 検索順位は高いがクリック率が低い
- 表示回数やクリック率が高いが検索順位が低い
- 更新日や内容が古い
- 流入は多いが読了率が低い
順にご説明します。
(1)検索順位は高いがクリック率が低い
検索結果の上位に表示されているにも関わらず、クリック率が低い記事は積極的にリライトをすべきです。
この状況は、タイトルやメタディスクリプションがユーザーの検索意図に合致していない可能性を示しています。
そのような場合には、まずはGoogleサーチコンソールなどのデータを確認し、同じ検索順位帯の他のページと比較してクリック率を評価しましょう。
一般的に、1位表示で20〜30%、2〜3位で10〜15%程度のクリック率が目安とされています。
これを大幅に下回っている場合は、タイトルとメタディスクリプションの改善により、大幅なトラフィック増加を期待することができます。
(2)表示回数やクリック率が高いが検索順位が低い
多くのユーザーに表示され、一定のクリックも獲得しているものの、検索順位が低い記事も優先的にリライトすべき対象です。
この状況は、コンテンツの内容は一定の評価を得ているものの、SEO的な最適化が不十分であることを示しています。
そのような場合には、競合分析を行い、上位表示されているページと比較して不足している要素を特定しましょう。
コンテンツの追加や構成の改善により、検索順位の向上が期待できます。
順位が1ページ目に上がることで、クリック率とトラフィックの大幅な増加が見込めるでしょう。
(3)更新日や内容が古い
作成から長期間経過し、情報が古くなっている記事は、信頼性の観点からリライトが必要です。
特に統計データや法令、技術情報などが含まれている場合は、定期的な更新が不可欠といえます。
古い情報のままでは、ユーザーの信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も低下するリスクがあります。
また、業界の動向や市場環境の変化に応じて、新たな視点や情報を追加するのも重要です。
情報の鮮度を保つことで、コンテンツの価値を長期的に維持できるでしょう。
(4)流入は多いが読了率が低い
多くのユーザーが訪れているものの、すぐに離脱してしまう記事は、内容とユーザーの期待にミスマッチが生じている可能性があります。
Googleアナリティクスなどで滞在時間やスクロール率を確認し、ユーザーがどの部分で離脱しているかを分析しましょう。
分析を通じて、ファーストビューの改善やユーザーが求める情報への誘導を最適化するなどの具体的な改善を行うことで、滞在時間の向上が期待できます。
また、コンテンツの構成を見直し、より読みやすく理解しやすい形に改善することも効果的です。
読了率の向上は、検索エンジンからの評価向上にもつながる重要な指標です。
5.【パターン別】リライトの基本的な流れ
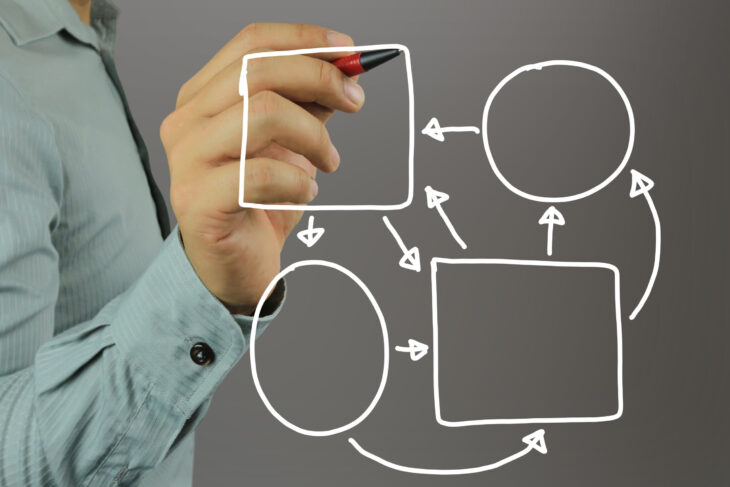
リライトの効果を最大化するためには、現在の課題に応じた適切なアプローチを選択することが重要です。
具体的には、以下のようなパターンによってアプローチの方法が異なります。
- 検索順位は高いがクリック率が低い場合
- 表示回数やクリック率が高く検索順位が低い場合
- 更新日や内容が古い場合
- 読了率が低い場合
なお、いずれの場合であっても、リライトの実施後はGoogleサーチコンソールを通じてインデックス登録のリクエストを行うことが重要です。
また、リライトによる効果は即時に現れるものではないため、数週間から数か月といった中長期的な視点で効果測定を行いましょう。
インデックス登録を促す具体的な方法については、以下の記事もご参照ください。
(1)検索順位は高いがクリック率が低い場合
検索順位は高いもののクリック率が低い場合、主な原因はタイトルとメタディスクリプションにあります。
検索結果の一覧を見たときに、ユーザーが見る情報はタイトルとメタディスクリプションであり、そこから魅力的なものが選ばれるからです。
そのため、タイトルでユーザーの目を引き、適切なメタディスクリプションへの変更が必要といえます。
#1:タイトルを見直す
効果的なタイトル作成には、検索キーワードの適切な配置と、ユーザーの関心を引く表現が重要です。
まず、対象キーワードをタイトルの前半部分に配置し、検索エンジンとユーザーの両方に内容を明確に伝えましょう。
さらに、数字や具体的な表現を使用することで、コンテンツの価値を分かりやすく示すことができます。
悪い例:ダイエットのコツとは?痩せない人向けのアドバイス
良い例:30代のダイエット成功のコツ!短期間で痩せる3つの方法とおすすめレシピ
例のように、具体的にペルソナを指定したり、3つなどの数値を入れることで、ユーザーの関心を引くタイトルを作成することが大切です。
競合他社のタイトルと差別化を図るため、独自の切り口や付加価値を強調することも効果的です。
#2:メタディスクリプションを見直す
メタディスクリプションは、検索結果でユーザーが最初に目にする詳細情報です。
120文字程度で、記事の内容を魅力的に要約し、ユーザーのクリック意欲を喚起する文章を作成しましょう。
30代で「なかなか痩せない」とお悩みの方へ向けて、ダイエットのコツを紹介します。
30日間の短期間で体重を落とすコツ、栄養士が監修したレシピも紹介します。
記事の内容を実践すれば、あなたも引き締まった身体を手に入れられるでしょう。(113文字)
具体的な数値や実績、読者が得られるメリットを明確に示すことで、他の検索結果との差別化を図れます。
また、疑問文や感嘆符を適度に使用することで、ユーザーの感情に訴える表現も効果的です。
キーワードの自然な配置により、検索語句とのマッチング度も向上させることができます。
なお、メタディスクリプションの書き方のポイントについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)表示回数やクリック率が高く検索順位が低い場合
表示回数やクリック率が高いものの、検索順位がそれに伴っていないのは、コンテンツの魅力はあるものの、SEO対策が不足している状態です。
SEOを最適化すれば、より検索順位を上げてトラフィックの増加を目指すことができます。
具体的には、以下の手順でリライトを実施しましょう。
- 競合と比べて不足している情報を追加する
- 検索ニーズを再度見直し必要な見出しを追加する
- 共起語を追加する
順にご説明します。
#1:競合と比べて不足している情報を追加する
上位表示されているページの内容を詳細に分析し、自社コンテンツに不足している情報を特定しましょう。
単純な情報量の比較だけでなく、ユーザーが求める情報の質や深度についても検討が必要です。
競合が提供している独自の視点や専門的な知見があれば、それを参考により価値の高いコンテンツを作成することができます。
ただし、単純なコピーではなく、自社独自の経験や知見を加えることで差別化を図ることが重要です。
競合調査の詳しい方法はこちらの記事で解説しています。
#2:検索ニーズを再度見直し必要な見出しを追加する
検索キーワードの背景にある潜在的なニーズを再分析し、それに対応する見出しを追加します。
そのためには、関連キーワードや共起語を調査し、ユーザーが求める情報の全体像を把握することが重要です。
具体的には、「よくある質問」セクションの追加や、段階的な解説の充実により、より包括的なコンテンツに仕上げましょう。
また、初心者から上級者まで、異なるレベルのユーザーに対応できる構成も効果的です。
見出しの追加時には、適切なHTMLタグ(H2、H3等)を使用し、構造化された読みやすいコンテンツを作成しましょう。
HTMLタグの概要やライティング時の活用ルールについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
#3:共起語を追加する
検索エンジンは、メインキーワードと関連性の高い語句(共起語)の存在を評価します。
専用ツールや競合分析により、対象キーワードに関連する共起語を特定し、自然な形でコンテンツに組み込みましょう。
ただし、不自然な詰め込みは逆効果となるため、文脈に合った自然な使用を心がけることが重要です。
共起語の配置により、コンテンツの専門性と関連性を検索エンジンに示すことができます。
結果として、対象キーワードだけでなく、関連キーワードでの検索順位向上も期待できるでしょう。
共起語の概要やSEO上での重要性、調べ方などの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
(3)更新日や内容が古い場合
情報の鮮度は、特に一部のジャンルにおいて検索順位に大きく影響します。
古くなった情報を最新のものに更新し、コンテンツの信頼性と価値を維持することが重要です。
データの更新と信頼性の向上を中心とした改善を実施しましょう。
#1:最新情報・日付・統計に差し替え
リライトで記事に含まれる情報の古いものを、最新のものに更新しましょう。
特に年次で発表される統計や定期的に変更される制度については、こまめな確認と更新が必要です。
例えば、コンテンツ内で政府統計を利用している場合などは、最新のものに差し替えてアンカーリンクなども更新します。
古いデータのままでは、読者の信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も低下する可能性があるからです。
更新時には、データの出典も併せて確認し、信頼性の高い情報源からの引用を心がけましょう。
#2:出典を更新し、信頼性を担保
引用している出典情報についても、最新のものに更新すると同時にリンク切れの確認や、より権威性の高い情報源への差し替えを検討しましょう。
政府機関や学術機関、業界団体等の一次情報源を優先的に使用することで、コンテンツの信頼性を大幅に向上させることができます。
出典の追加により、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の向上も期待できます。
適切な引用とリンクの設置により、読者にとってより価値の高い情報提供が可能になるでしょう。
E-E-A-Tの各要素を高めるためのポイントについては、以下の記事が参考になります。
(4)読了率が低い場合
多くの流入があるにも関わらず読了率が低い場合、コンテンツの構成や表現に改善の余地があります。
ユーザーの期待と実際のコンテンツ内容にギャップがある可能性が高いため、ユーザビリティの改善を中心とした施策が効果的です。
具体的には、以下の手順でリライトを実施しましょう。
- ファーストビューを見直す
- 再検索KWを活用してユーザーが求める情報を追加する
- 画像や表を追加して離脱率を下げる
- 内部リンクを追加する
それぞれについて解説します。
#1:ファーストビューを見直す
ページを開いた瞬間にユーザーが目にするファーストビューの印象は、離脱率に大きく影響します。
導入文で記事の価値や読者が得られるメリットを明確に示し、最後まで読むモチベーションを与えることが重要です。
具体的には、アイキャッチ画像を変更したり、リード文を見直したりして、読んでもらえるファーストビューを構築しましょう。
また、目次の設置により、コンテンツ全体の構成を分かりやすく提示することも効果的です。
視覚的な要素として、適切な画像や図表の配置により、読み進めたくなる魅力的なレイアウトを作成しましょう。
#2:再検索KWを活用してユーザーが求める情報を追加する
ユーザーが記事を読んだ後に再度検索するキーワードを分析し、不足している情報を特定します。
再検索KW調査ツールなどを使用して、ユーザーがリライト対象のコンテンツだけで補うことができなかった情報を見つけましょう。
これらの情報を記事に追加することで、ユーザーの疑問を完全に解決する包括的なコンテンツに仕上げることができます。
また、「よくある質問」セクションの充実により、読者の潜在的な疑問にも対応できます。
結果として、ユーザーの満足度向上と滞在時間の延長が期待できるでしょう。
#3:画像や表を追加して離脱率を下げる
テキストのみのコンテンツは読みにくく、離脱率の原因となる場合があります。
そのため、適切な画像や図表、グラフの追加により、視覚的に理解しやすいコンテンツに改善しましょう。
複雑な情報は表やリストにまとめることで、一目で理解できる形に整理することが効果的です。
画像には適切なalt属性を設定し、アクセシビリティとSEO効果の両方を向上させましょう。
#4:内部リンクを追加する
関連する記事への内部リンクを適切に配置することで、サイト内の回遊性を向上させることができます。
ユーザーの興味や疑問に応じて、より詳細な情報を提供する記事へ誘導しましょう。
内部リンクの設置により、サイト全体のSEO効果向上も期待できます。
アンカーテキストは自然な表現を使用し、リンク先の内容が明確に分かるようにすることが重要です。
もっとも、過度な内部リンクは逆効果となるため、読者にとって本当に価値のあるリンクのみを厳選して設置しましょう。
適切な内部リンクの設定方法については、以下の記事もご覧ください。
6.SEO効果を高めるリライト施策

基本的なリライト作業に加えて、より高度なSEO施策を実施することで、検索順位向上の効果を最大化することができます。
具体的には、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 検索クエリをタイトルや見出しの左側に配置する
- 画像にはalt属性を入れる
- 文章の可読性を上げる
- SERPsやPAAに基づく「よくある質問」を入れる
- 権威性のある出典元を追加する
- アンカーリンクなどでユーザビリティを上げる
- 重複コンテンツの削除も検討する
これにより、技術的な最適化からユーザビリティの改善まで、包括的なアプローチにより競合他社との差別化を図ることが可能です。
(1)検索クエリをタイトルや見出しの左側に配置する
リライトの際には検索クエリをタイトル、見出しの左側に配置しましょう。
これは、検索エンジンは重要なキーワードがタイトルや見出しの前半部分に配置されていることを高く評価すると言われているためです。
また、ユーザーも左から右に読む習慣があるため、重要な情報を前半に配置することで、クリック率の向上も期待できます。
ただし、不自然な文章にならないよう、読みやすさとのバランスを保つことが重要です。
見出しについても同様に、H2やH3タグ内でキーワードを前半に配置することで、SEO効果を高めることができます。
(2)画像にはalt属性を入れる
すべての画像に適切なalt属性を設定することで、アクセシビリティとSEO効果の両方を向上させることができます。
alt属性には、画像の内容を的確に説明する文章を記載し、画像が読み込めない環境などで操作するユーザーにも配慮した設計とします。
また、検索エンジンは画像の内容をalt属性から判断するため、関連キーワードを自然に含めることでSEO効果も期待できます。
装飾的な画像については空のalt属性(alt=””)を設定し、スクリーンリーダーが不要な情報を読み上げないようにしましょう。
適切なalt属性の設定により、画像検索での表示機会も増加し、多様な流入経路を確保できます。
なお、alt属性の概要や具体的な設定方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)文章の可読性を上げる
リライトで文章の可読性を上げることで、ユーザー体験を向上させ、検索エンジンからの評価も高めることが可能です。
例えば、適切な改行や段落分け、漢字とひらがなのバランスを調整することで、視覚的に読みやすいコンテンツを作成しましょう。
さらに専門用語の使用時には、必ず分かりやすい説明を併記することが重要です。
また、一文の長さを適度に調整し、複雑な構造の文章は分割して理解しやすくするのも良いでしょう。
(4)SERPsやPAAに基づく「よくある質問」を入れる
リライト時に検索結果ページの「他の人はこちらも検索」や「よくある質問」を参考に、関連する疑問への回答を追加しましょう。
これらの情報は、実際のユーザーが抱いている疑問を反映しているため、コンテンツの価値向上に直結します。
FAQ形式で情報を整理することで、構造化データの活用も可能となり、リッチスニペットでの表示が期待できるのもメリットです。
ユーザーの潜在的な疑問に先回りして答えることで、満足度の高いコンテンツを提供することができるでしょう。
なお、PAA(People Also Ask)の基本概念や対策方法については、以下の記事も参考になります。
(5)権威性のある出典元を追加する
リライト時に信頼性の高い一次情報源からの引用を増やすことで、コンテンツの権威性を大幅に向上させることができます。
具体的には、政府機関や学術機関、業界団体等の公式データを積極的に活用しましょう。
外部リンクは、関連性が高く信頼できるサイトへのものを厳選して設置することが重要です。
引用時には、適切な出典表記とリンクの設置により、情報の透明性を確保することが必要です。
(6)アンカーリンクなどでユーザビリティを上げる
長い記事においては、目次からのアンカーリンクを設置することで、ユーザーが求める情報にすぐにアクセスできる環境を整えましょう。
例えば、「ページトップに戻る」ボタンの設置により、ナビゲーションの利便性も向上させることができます。
関連する記事や追加情報への適切な内部リンクにより、サイト内での回遊性を高めることも重要です。
モバイルユーザーを考慮し、タップしやすいリンクサイズとレイアウトを心がけることが必要です。
ユーザビリティの向上は、直接的にユーザー満足度の向上につながり、結果として検索エンジンからの評価も高まります。
(7)重複コンテンツの削除も検討する
サイト内で類似したテーマを扱っている記事がある場合リライト時に重複コンテンツの整理が必要です。
検索エンジンは重複コンテンツを低く評価するため、統合や削除により問題を解決しましょう。
統合が困難な場合は、それぞれの記事の独自性を明確にし、異なる角度からの情報提供を心がけることが重要です。
重複の解消により、サイト全体のSEO効果を最大化し、各記事が適切に評価される環境を整えることができます。
7.リライトについてよくある質問

リライトの実施にあたって、多くの担当者が抱く疑問や不安があります。
以下では、特に多く寄せられる質問とその回答を整理していきます。
- 上位表示されている記事もリライトすべきですか?
- リライトはどれくらいの頻度ですればいいですか?
これからリライト施策を進める際の参考となれば幸いです。
(1)上位表示されている記事もリライトすべきですか?
上位表示されている記事であっても、定期的なリライトは必要です。
検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しており、競合他社も継続的に改善を行っているためです。
また、上位表示記事でもデータが古くなっていることはあるので、最新情報への更新は必要となります。
ただし、大幅な変更は避け、情報の更新や微細な改善に留める程度で良いでしょう。
なお、上位表示されている記事については月に1回程度内容を確認し、必要な情報があれば更新する程度で十分です。
タイトルやSEOの構造を大幅に変えることで順位が下がるリスクもあるので、慎重にリライトしましょう。
(2)リライトはどれくらいの頻度ですればいいですか?
リライトの頻度は、コンテンツの性質と現在の状況によって決めましょう。
ニュース性の高い内容や法令関連の情報は、変更があるたびに即座に更新が必要です。
一般的なハウツー記事や基本的な情報については、3〜6か月に1回程度の確認と更新が適切でしょう。
なお、検索順位が下がっている記事については一度リライトし、1か月後に様子を見て情報を追加するなどの施策が必要になる可能性があります。
サイト全体としては、月に数本の記事をリライトすることで、継続的な改善サイクルを維持できます。
重要なのは、質の高いリライトを継続的に実施することです。
無計画な頻繁更新は逆効果となる可能性もあるため、戦略的なアプローチが重要です。
データに基づいた優先順位付けにより、効率的なリライトスケジュールを構築しましょう。
まとめ
リライトは、既存コンテンツの価値を最大化し、効率的にSEO効果を向上させる重要な施策です。
新規記事作成と比較して、コストを抑えながら高い効果が期待できるため、限られたリソースの中で成果を上げる必要がある企業にとって、特に有効な手法となります。
成功の鍵は、データに基づいた適切な記事選定と、課題に応じた最適な改善施策の実施にあります。
検索順位、クリック率、滞在時間などの指標を総合的に分析し、最も改善ポテンシャルの高い記事から優先的にリライトを実施しましょう。
また、一度の大幅な改変よりも、継続的な小さな改善の積み重ねが、長期的な成果につながることを理解することが重要です。
リライトは単なる文章の修正ではなく、ユーザーニーズの変化や市場環境の変化に対応する戦略的な取り組みです。
適切な計画と継続的な実施により、あなたのWebサイトの検索順位向上と、ユーザー満足度の向上を同時に実現できるでしょう。
リライト戦略の決め方、リライト時のSEO施策にお悩みならTMS Partners株式会社へご相談ください。
TMS Partners株式会社はコンテンツのリライトはもちろん、制作からSEO対策まで包括的なサポートを提供しています。