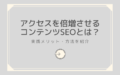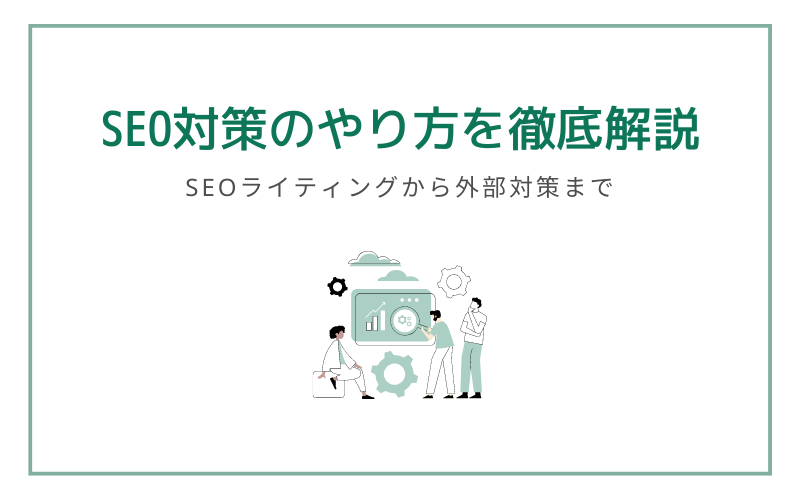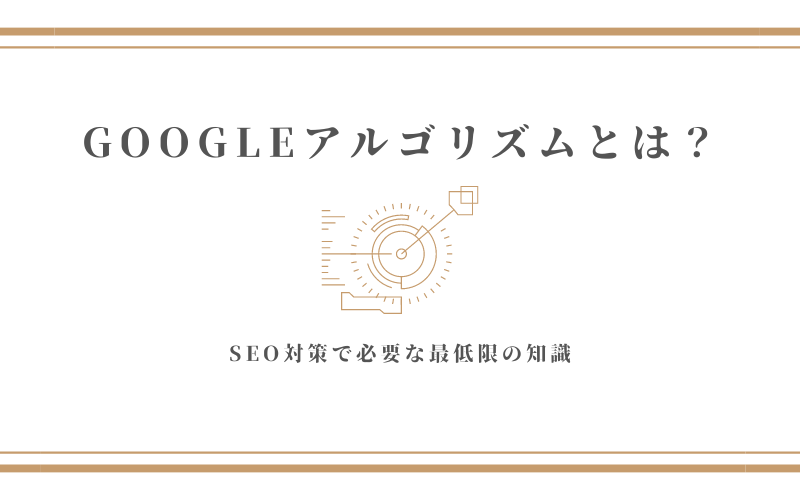Googleパンダアップデートとは?検索順位が激減した際の対策まで解説

「最近サイトのアクセスが急に減った」
「Google検索での順位が落ちているようだが、原因がわからない」
このような状況が発生した際にWeb担当者がまず疑うのが、Googleのアップデートです。
しかし、Googleアルゴリズムアップデートの存在は知っていても、その種類について詳しく知らない方も多いでしょう。
本記事では、Googleの重要なアルゴリズム「パンダアップデート」について、基本的な概念から対策方法まで詳しく解説します。
現在もSEOに大きな影響を与え続けているパンダアップデートの仕組みを理解し、適切な対策を取ることで、検索順位の回復・向上を目指しましょう。
1.パンダアップデートとは

まずはパンダアップデートの基本概念について説明します。
- パンダアップデートの概要
- 名前の由来
- 導入の背景
(1)パンダアップデートの概要
パンダアップデートは、Googleが2011年に導入した検索アルゴリズムの一種です。
このアップデートは、検索結果における低品質なコンテンツの順位を下げ、高品質なページを優遇する目的で設計されました。
Google公式の発表によると、当時の検索クエリの約11.8%に影響を与えたとされています。
これは多くのWebサイトにとって大きな転換点となり、コンテンツの質がSEOにおいて最重要視されるきっかけとなりました。
(2)名前の由来
パンダアップデートという名称は、このアルゴリズムの開発に関与したGoogleのエンジニア「Navneet Panda(ナブニート・パンダ)」氏の名字に由来しています。
意外かもしれませんが、動物のパンダとは無関係であり、開発者の名前から取られたものなのです。
Googleのアルゴリズム更新は開発者の名前が冠されることがあり、後述するペンギンアップデートも同様の命名法則によるものです。
(3)導入の背景
パンダアップデート導入の主な背景には、当時コンテンツファームや自動生成コンテンツなどが検索結果の上位に表示されており、ユーザーにとって価値の薄いページが増加していたことがあります。
これらのページは、SEOテクニックを駆使して検索順位を上げることに成功していましたが、実際のユーザーにとっては役立つ情報が少ないものでした。
Googleが掲げる「ユーザー第一」の理念を実現するため、このようなコンテンツを排除し、「真に価値のある情報を提供するサイトを評価する仕組みが必要である」という背景から導入されました。
2.パンダアップデートの歴史と現在も続く影響
![]()
パンダアップデートは単発の更新ではなく、複数回にわたる改良を経て現在のGoogleアルゴリズムに統合されています。
そのため、現在では基本方針の一部として組み込まれていると評価することも可能です。
パンダアップデートに関連して、押さえておきたいトピックスには以下のようなものがあります。
- パンダアップデートのリリースの流れ
- 2015年以降はコアアルゴリズムに統合されている
- 現在でも影響が残る理由
順に見ていきましょう。
(1)パンダアップデートのリリースの流れ
パンダアップデートは2011年2月23日に初めてリリースされました。
当初は英語圏のサイトを対象に実施され、その後数か月かけて他言語のサイトにも適用範囲が拡大していきました。
その後、Panda 2.0、2.5、3.0といった形で複数回のバージョンアップが行われ、その都度アルゴリズムの精度が向上していっています。
最終的には2015年にPanda 4.2が実施されたのを最後に、単独のアップデートとしては終了しています。
(2)2015年以降はコアアルゴリズムに統合されている
2016年、Googleは公式にパンダアップデートがコアアルゴリズムに統合されたことを発表しました。
これによりパンダは単独のアップデートという形では実施されなくなり、Googleの検索アルゴリズムの中に常時稼働する要素として組み込まれました。
つまり、特定のタイミングでの更新ではなく、常に作用し続けるものになったということです。
これにより、サイト運営者は一時的な対応ではなく、継続的にコンテンツの質を維持する必要性が高まりました。
(3)現在でも影響が残る理由
パンダアップデートが単独のアップデートとしては終了したにもかかわらず、現在もその影響が強く残っている理由は、「低品質コンテンツの排除」という考え方自体がGoogle検索の本質に組み込まれているからです。
高品質なコンテンツを提供するサイトを優遇するというパンダの基本理念は、その後のアルゴリズム更新にも一貫して反映されています。
そのため、SEO担当者は今もなお、パンダアップデートの評価軸を意識したコンテンツ改善が必要となっているのです。
現代のSEOにおいて「コンテンツの質」が最重要視されるようになった背景には、このパンダアップデートの存在が大きく影響しています。
現在のGoogleアップデート「コアアップデート」については、こちらの記事をご覧ください。
3.パンダアップデートに影響を受けるサイトの特徴とは?

どのようなサイトがパンダアップデートの影響を受けやすいのでしょうか。
ここでは具体的な特徴を解説します。
- 低品質なコンテンツでサイトが構成されている
- 広告や誘導リンクばかりのアフィリエイトサイトである
- コピーコンテンツが多く差別化されていない
(1)低品質なコンテンツでサイトが構成されている
パンダアップデートの主なターゲットは、低品質なコンテンツを多く含むサイトです。
例えば、同じような内容の重複ページが大量にあるサイトは、ユーザーにとって価値が低いと判断されがちです。
また、中身が薄く文字数だけが多いページや、自動生成された機械的な文章で構成されたコンテンツも低評価の対象となります。
このようなページは「薄いコンテンツ(Thin Content)」と呼ばれ、パンダアップデート以降、検索順位が大きく下がるケースが多くなっています。
(2)広告や誘導リンクばかりのアフィリエイトサイトである
コンテンツよりも広告エリアが目立つ構成のサイトも、パンダアップデートの影響を受けやすくなっています。
特に、ランキング記事風のアフィリエイトリンク誘導が過剰なサイトは、ユーザーに価値ある情報を提供するよりも収益を優先していると判断される可能性が高いです。
収益を得るという目的が前面に出すぎてユーザー視点に欠けるサイトは、パンダアップデート後に順位を大きく落とすケースが増えています。
ユーザーファーストでない広告主導のサイト構成は、現在のGoogle評価においても不利になる要素です。
(3)コピーコンテンツが多く差別化されていない
引用・転載・リライト中心で一次情報がないサイトも、パンダアップデートの影響を強く受けます。
他サイトのコンテンツを少し言い換えただけのものや、検索上位サイトと構成や内容が酷似しているページは、オリジナリティに欠けると判断されて検索順位が落ちることが多いです。
これはGoogleが独自の価値を持つコンテンツを高く評価する方針を明確にしており、差別化されていないコンテンツは検索順位が下がりやすいからです。
サイト全体として独自の視点や情報を提供できているかどうかが、パンダアップデート以降の重要な評価ポイントとなっています。
4.パンダアップデートで検索順位が下がることによる主な影響
![]()
検索順位の低下は、サイト運営にどのような影響をもたらすのでしょうか。
具体的な影響は、以下のようなものがあります。
- 自然検索からのアクセス数が激減する
- 売上・問い合わせ・応募数などが大幅に低下する
- 企業サイトの信頼性やブランド価値にも影響する
順にご説明します。
(1)自然検索からのアクセス数が激減する
パンダアップデートによって検索順位が下がることで発生する一番大きな影響は、アクセス数の激減です。
検索順位が1ページ目から2ページ目へ落ちるだけでも、クリック率は大幅に低下することが知られています。
特定のキーワードでの流入がゼロ近くまで落ち込むケースも珍しくありません。
特にSEO流入の割合が大きいサイトでは、総トラフィックが半減以上するなど致命的な影響を受けることもあります。
(2)売上・問い合わせ・応募数などが大幅に低下する
自然検索からの流入減少は、そのままコンバージョン率(CVR)にも悪影響を及ぼします。
特に自然検索からの流入に依存していた場合には、パンダアップデートの影響で売上が激減することもあるでしょう。
例えばEC(電子商取引)サイトでは売上の低下、企業サイトでは問い合わせ数の減少、求人サイトでは応募者数の減少など、ビジネス指標に直結する数値が悪化します。
(3)企業サイトの信頼性やブランド価値にも影響する
検索順位の低下は、単なるトラフィックやコンバージョンの問題だけでなく、企業の信頼性やブランド価値にも影響を与えます。
これは「検索ユーザーが検索上位のサイトは信ぴょう性が高いサイトだ」と考える傾向があるからです。
つまり、Googleで検索順位が下がるほどユーザーからそのサイトの情報が信用されず、企業への信頼感を損なうことにつながります。
企業イメージやブランディングの観点からも、検索順位の維持・向上は重要な課題となっています。
5.自社サイトがパンダアップデートの影響を受けているか確認する方法

自社サイトがパンダアップデートの影響を受けているかどうかを確認するためのポイントを解説します。
- Googleアナリティクスとサーチコンソールを用いた変化の可視化
- 順位チェックツールでのキーワード別推移の確認
- 公式発表や業界ニュースと照らし合わせた時系列分析
(1)Googleアナリティクスとサーチコンソールを用いた変化の可視化
自社サイトがパンダアップデートの影響を受けているかを確認する最も基本的な方法は、Googleアナリティクスとサーチコンソールのデータを分析することです。
まず、Googleアナリティクスで日付を絞って自然検索からの流入数の推移を確認しましょう。
急激な減少が見られる日があれば、その前後でのアルゴリズム更新がなかったか調査します。
また、サーチコンソールでは特定ページの表示回数やCTR(クリック率)の急落などを確認できるので、データを出してチェックをおこないましょう。
サーチコンソールでページへの影響度合いを把握すれば、コンテンツの問題点を特定して、改善するのに役立ちます。
(2)順位チェックツールでのキーワード別推移の確認
GRCやRank Trackerなどの順位チェックツールを導入している場合には、重要キーワードの日別推移を記録・分析しましょう。
特定の日付を境に複数キーワードの順位が一斉に下落しているようであれば、アルゴリズム更新の影響を受けている可能性が高いと考えられます。
また、コンテンツの更新日と順位変化の因果関係を分析することで、どのような変更が良い影響を与えたのか、あるいは悪影響を及ぼしたのかを把握できます。
長期的なトレンドとピンポイントな変化を区別することで、アルゴリズム更新の影響をより正確に特定することができるでしょう。
(3)公式発表や業界ニュースと照らし合わせた時系列分析
SEO業界のニュースサイトやGoogle公式ブログをチェックして、アルゴリズム更新の実施情報を収集することも重要です。
SEO関連のメディアを確認したり、Xで「コアアップデート、Google 変動」などと検索すれば、アルゴリズム変更についての投稿が見つかります。
具体的には、以下のようなものを見つけることができます。
2025年5月20日は、大きな順位の上下動が見られました。
金融業界、飲食業界、リクルート業界が、特に順位が上下しています。
また、Googleからの公式アップデート情報は、本日はございません。
— Google検索順位・順位変動ニュース (@se_search_news) May 20, 2025
自社サイトのアクセス減少タイミングとGoogleのアップデート実施日が重なっている場合、その影響を受けている可能性は高いです。
また、Google関連のニュースはアメリカのSEO専門家のツイートなども参考になる場合もあります。
3 SEO Action Steps to Take After a Google Core Update:
Google’s algorithm updates can significantly impact your website’s visibility and traffic. To maintain and improve your search rankings, consider these three strategic actions:
1) Conduct a Comprehensive SEO Audit…
— Colin Slager (@slagermeister) April 28, 2025
このような情報については、翻訳ツールを用いて情報をチェックするのがおすすめです。
6.パンダアップデートの対策に有効な改善ポイント

パンダアップデートの影響を受けたサイトの改善策について「Google検索セントラル」の情報を元に解説します。
具体的には、以下の点を意識しましょう。
- 低品質ページの削除または統合
- E-E-A-Tを意識したコンテンツ強化
- 広告配置や導線設計の最適化によるUX向上
- 内部リンク構造の改善による巡回性アップ
- Google公式ガイドラインに基づくページ全体の品質見直し
これらは、アップデートの影響を受けないためにも重要ですが、ユーザビリティという観点からも重要といえます。
(1)低品質ページの削除または統合
パンダアップデート対策として最も効果的な方法の一つが、低品質ページの削除または統合です。
アクセスがない、あるいは極めて少ない類似ページは、統合するかnoindex化することを検討しましょう。
また、質が低いと判断されたページについては思い切って削除するのも、サイト全体の評価向上に役立つ場合があります。
今のGoogleは「量より質」が重視されるので、少数であっても高品質なページで構成されたサイトを目指しましょう。
noindexのやり方については、こちらの記事をご覧ください。
(2)E-E-A-Tを意識したコンテンツ強化
Googleアルゴリズムへの対策として、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:経験、専門性、権威性、信頼性)を意識したコンテンツ強化も効果的です。
それぞれ、どのようにすればコンテンツを強化できるか表にまとめました。
| E-E-A-T要素 | 意味 | 強化方法 |
|---|---|---|
| Experience(経験) | 実際の経験に基づく情報提供 | 体験談や事例の追加、著者の実務経験を明記 |
| Expertise(専門性) | 特定分野における知識・技術の深さ | 専門資格の表示、業界経験年数の明記、専門用語の適切な解説 |
| Authoritativeness(権威性) | 業界での認知度や信頼される立場 | 第三者からの引用・言及、業界賞の受賞歴、講演実績の紹介 |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報の正確さと信頼できる根拠 | 信頼性の高い情報源の引用、データの出典明記、最新情報への更新日の表示 |
例えば、体験談に基づいたコンテンツを増やしたり、専門知識がある人の監修を受けて監修者情報を挿入するなどの対策が有効です。
また、権威性を高めるためには自社に発信する情報のエキスパートがいる場合は、経歴を記載したプロフィールを入れるのもおすすめです。
最後の「信頼性」については、信頼性が高い情報源(研究機関や公的な機関など)から出典元を明記する形で情報を引用すること、また情報を最新のものへアップデートし、更新日を表示させるなどの対策が取れます。
このように、E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作は、ユーザーのコンテンツに対する信頼を高めることにつながります。
E-E-A-Tの各要素の概念や具体的なコンテンツ制作のポイントについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(3)広告配置や導線設計の最適化によるUX向上
Googleが重視するのは「ユーザーファースト」であることです。
そのために、ユーザーエクスペリエンス(UX)を重視した広告配置や導線設計の最適化も、パンダアップデート対策になります。
具体的にはページ上の広告の比率を下げ、ユーザーの読みやすさを最優先に考えたレイアウトに変更しましょう。
特に本文途中の煩雑なバナーは、ユーザビリティを低下させる要因となるため、削除または配置の見直しがおすすめです。
まずは自分がユーザーになりきってページを閲覧し、コンテンツが読みやすいことを優先して広告配置を考えましょう。
UX改善の意義やポイント、成功事例については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(4)内部リンク構造の改善による巡回性アップ
パンダアップデート対策として、内部リンク構造の改善も実施しましょう。
内部リンクの構造を改善することで孤立するページをなくし、関連性の高いコンテンツをリンクでつなげればサイト全体の価値向上につながります。
特に読んでほしい主要なページに向けた適切な内部リンクを設置することで、重要コンテンツへの評価を集中させることができます。
また、ユーザーにとっても内部リンクは必要な情報を巡回するのに役立つため、ユーザーファーストの観点でも内部リンクの見直しは重要です。
なお、内部リンクの設計はSEO対策の中でも、「内部対策」と呼ばれるものに属します。
SEOの内部対策の概要や具体的な実施のポイントについては、以下の記事も参考になります。
(5)Google公式ガイドラインに基づくページ全体の品質見直し
Googleが公開している「Google 検索の基本事項」などの公式ガイドラインに基づいて、ページ全体の品質を見直すことも重要です。
-
有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。
-
ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。
-
リンクをクロール可能にする。これにより、Google がページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できます。
-
サイトに関する情報を発信する。自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。
-
画像、動画、構造化データ、JavaScript などの他のコンテンツがある場合、各タイプに固有のベスト プラクティスを実践する。これにより、ページ上の各コンテンツを Google に提示できます。
-
サイトに適した機能を有効にすることで、Google 検索におけるサイトの表示を改善する。
-
検索結果に表示したくないコンテンツがある場合や、完全なオプトアウトを希望する場合は、適切な方法でGoogle 検索でのコンテンツの表示を管理する。
これらの質問に照らし合わせて自社サイトを評価し、不足している要素を補強していきましょう。
独自性・価値・読者視点のバランスを取りながら、総合的な品質向上を目指すことがパンダアップデート対策の基本となります。
定期的な品質チェックを行い、常に改善を続けることが長期的な検索順位の安定につながります。
その他コンテンツSEOについては、こちらの記事をご覧ください。
7.Googleの他の主要アルゴリズムとの違い

パンダアップデートと他のGoogleアルゴリズムとの違いについて解説します。
- パンダアップデートとペンギンアップデートの違い
- ハミングバードアップデート・コアアップデートとの違い
- アップデートの比較表
(1)パンダアップデートとペンギンアップデートの違い
パンダアップデートとペンギンアップデートは、どちらもGoogleの重要なアルゴリズム更新ですが、評価対象が異なります。
パンダアップデートは主にコンテンツの品質を評価するアルゴリズムであり、サイト内の情報の価値、オリジナリティ、ユーザビリティなどが主な評価対象となります。
一方、ペンギンアップデートは不自然な被リンク操作などの外部SEO施策を評価するアルゴリズムで、低品質なリンクを大量に獲得するなどの人為的なSEO手法を排除する目的で導入されました。
つまり、パンダは「内部要因」、ペンギンは「外部要因」に焦点を当てたアルゴリズムといえるでしょう。
(2)ハミングバードアップデート・コアアップデートとの違い
ハミングバードアップデートは、検索意図の解釈精度を高めることを目的とした言語処理中心のアルゴリズムです。
検索クエリの文脈や意味を理解し、ユーザーが本当に求めている情報を提供することに焦点を当てています。
一方、コアアップデート(Core Update)は、様々な要因を総合的に評価する全体最適型のアップデートです。
パンダやペンギンなど個別の要素だけでなく、サイト全体としての価値を多角的に評価します。
パンダアップデートはコンテンツ品質という特定の側面に注目したものであるのに対し、コアアップデートはより包括的な評価に基づいてるのが違いです。
(3)アップデートの比較表
主要なGoogleアップデートの特徴を比較表にまとめました。
| アップデート名 | 導入時期 | 主な評価対象 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|
| パンダ | 2011年2月 | コンテンツ品質、重複性、オリジナリティ | コアアルゴリズムに統合 |
| ペンギン | 2012年4月 | 被リンクの質、リンク構築手法 | コアアルゴリズムに統合 |
| ハミングバード | 2013年8月 | 検索意図理解、自然言語処理 | 継続的に進化中 |
| コアアップデート | 2018年~ | サイト全体の総合評価 | 年数回実施中 |
これらのアップデートはそれぞれ異なる側面からサイトを評価していますが、すべての基本にあるのは「ユーザーに価値ある情報を提供すること」という共通点です。
Googleが提唱する重要な基本概念である「ユーザーファースト」の観点を忘れずに、コンテンツをアップデートしていきましょう。
8.過去にパンダアップデートの影響を受けた実例

実際にパンダアップデートの影響を受けたサイト事例について紹介します。
- MadeLoud.comが受けた順位下落の背景
- 改善によって復活できたサイトが実践した対策
(1)MadeLoud.comが受けた順位下落の背景
MadeLoud.comは、有名な音楽コミュニティサイトで、パンダアップデートで多大な影響を受けています。
元々MadeLoud.comではアーティストの情報や音楽レビューを提供していましたが、独自の観点をもつコンテンツがほぼなく、他サイトからの情報の寄せ集めのようになっていました。
特に自動生成のように見えてしまう類似ページが多く、オリジナルコンテンツの比率が低くなっていました。
これらが原因でパンダアップデート導入後にMadeLoud.comのトラフィックは激減し、検索上位から姿を消しています。
なお、MadeLoud.comはこのアップデート以降は休止状態となっており、パンダアップデートの影響の大きさがわかる事例となっています。
(2)改善によって復活できたサイトが実践した対策
パンダアップデートの影響を受けたものの、改善策を実施して検索順位を回復させたサイトも存在します。
これらのサイトが実践した主な対策としては、まず低品質ページを大量に削除したことです。
サイトにあるコンテンツの量が減ることを恐れずに、品質の低いページを削除することでサイトに存在するコンテンツの質を高める戦略です。
さらに、オリジナルコンテンツを追加して独自の観点や意見を取り入れたことで、順位を回復させたケースも見られました。
9.パンダアップデートについてよくある質問

最後に、パンダアップデートについてよくある質問とその回答をまとめました。
- パンダアップデートは今も実施されているの?
- ペンギンアップデートとの違いをわかりやすく教えてください。
- 順位が落ちてから回復するにはどれくらいかかりますか?
- アフィリエイトサイトはパンダアップデートで不利ですか?
- 企業ブログでもパンダアップデートの影響を受けますか?
(1)パンダアップデートは今も実施されているの?
パンダアップデートは単独のアップデートとしては既に終了しています。
2016年にGoogleのコアアルゴリズムに統合されており、常にコンテンツの品質が評価されるという方針は継続しています。
(2)ペンギンアップデートとの違いをわかりやすく教えてください。
パンダアップデートとペンギンアップデートの違いはパンダアップデートが品質に関する評価なのに対し、ペンギンアップデートはスパムリンクの排除をしていることです。
両方ともGoogleの検索品質向上を目的としていますが、注目しているポイントが異なります。
(3)順位が落ちてから回復するにはどれくらいかかりますか?
パンダアップデートなどの影響で順位が落ちた場合、早くて数週間、通常は数か月単位の時間がかかります。
コンテンツの改善策を実施した後、Googleのクローラーが再度サイトを巡回し、内容を評価するのに一定の時間がかかるからです。
特に大規模サイトはコンテンツ数が多いので、すべてのページが再クロールされるまでに時間がかかることがあります。
そのような場合には、サイト運営者側でクローラーの巡回を促すことも可能です。
クローラーの役割や巡回を促す意義、具体的な方法などについては、以下の記事で解説しています。
(4)アフィリエイトサイトはパンダアップデートで不利ですか?
アフィリエイトサイトであること自体がパンダアップデートで不利になるわけではありません。
しかし、単純なランキング形式やコピーコンテンツ中心の構成であれば、コンテンツの質が低いと判断される可能性は高いでしょう。
しかし、独自の体験や比較ポイント、オリジナル写真などを加えることで、独自性のあるコンテンツに品質をあげる工夫は可能です。
(5)企業ブログでもパンダアップデートの影響を受けますか?
企業ブログもパンダアップデートの影響を受ける可能性は十分にあります。
特に情報が古いままの記事や、他社のブログの後追いばかりのコンテンツ、サイト内の回遊設計が弱い場合はリスクが高まります。
企業ブログは専門性や信頼性が高い反面、形式的なコンテンツや一般的な情報の羅列では評価されにくいです。
定期的な更新と独自の視点を取り入れた高品質なコンテンツ提供を心がけることで、検索順位向上を目指しましょう。
まとめ
パンダアップデートは、Googleの検索結果において低品質なコンテンツを排除し、ユーザーにとって価値ある情報を提供するサイトを評価するために導入されたアルゴリズムです。
2011年の初回リリース以降、複数回の改良を経て、現在ではGoogleのコアアルゴリズムに統合されています。
パンダアップデートの影響を受けやすいサイトは、低品質コンテンツや重複ページが多い、広告主導の構成、差別化されていないコンテンツなどです。
これらのアップデートの対策としては質の高いコンテンツを継続的に提供し、ユーザーファーストの姿勢を貫くことを意識しましょう。
TMS Partners株式会社では、パンダアップデートをはじめとするGoogleアルゴリズム対策を含む、総合的なSEOコンサルティングサービスを提供しています。
検索順位の低下にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。