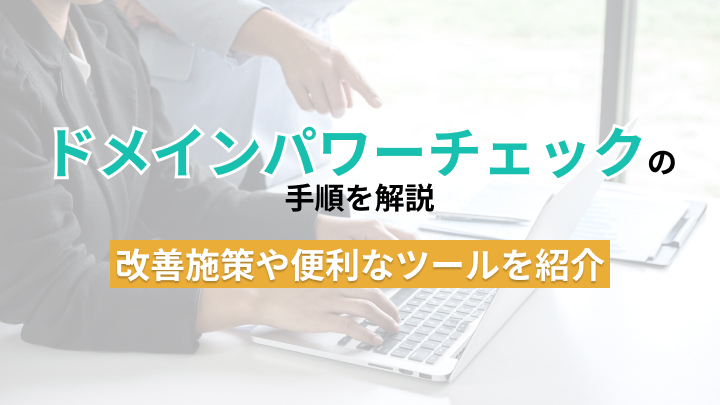PAAとは?基本概念やメリット、具体的な対策方法についても解説

「PAAとはどのようなものか」
「表示される仕組みやSEO上の効果は?」
「具体的な対策方法のポイントについて知りたい」
企業の経営者やマーケティング部門の担当者、Webサイトの運営者の中には、このような疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
PAA(People Also Ask)は、具体的な検索クエリやキーワードに関連する形で表示されるコンテンツです。
主にユーザーの検索意図をAIが読み取り、コンテンツが自動的に生成されますが、PAAに表示されるコンテンツは、インターネット上に存在する情報に基づいています。
そのため、PAAに自社サイトのコンテンツが表示されることで、ユーザーが関心を持ち、サイトへのアクセスを促すことができる可能性があります。
本記事では、PAAの基本概念や対策方法などについて解説します。
また、PAAをSEOに活用するためのアイディアについても合わせて解説しています。
これからSEO対策としてPAA対策に着手することを検討されている方の参考となれば幸いです。
1.PAA(People Also Ask)の基本概念

PAA(People Also Ask)とは、Google検索の機能の1つです。
ユーザーの検索の利便性を高めることを目的として導入されています。
そのため、PAAが表示されることは検索ユーザーにとっては検索の手間や時間を削減することにつながる一方、Webサイトの運営者にとっても一定のメリットがあります。
以下では、PAAについて押さえておきたいトピックスについて解説します。
- PAA(People Also Ask)とは
- PAAが表示される仕組み
- 強調スニペットとの違い
順に見ていきましょう。
(1)PAA(People Also Ask)とは
PAA(People Also Ask)とは、検索結果に「関連する質問」のように表示されるコンテンツをいいます。
ユーザーがコンテンツを開くと、自動的に別のコンテンツが順次追加されていきます。
これによって、ユーザーは自分が知りたい情報をピンポイントで収集したり、関連する別の情報を閲覧することが可能です。
検索ユーザーからすれば、1つの検索クエリやキーワードを入力して検索するだけで、それに関連するQ&Aを順次閲覧することができるため、新たなクエリを入力し直して検索する手間を省くことができます。
そのため、検索ユーザーにとっては検索の利便性が高まり、より短時間で網羅的な情報を収集することができるようになったのです。
その意味では、検索に対するユーザー体験(UX)を高める機能ということができるでしょう。
(2)PAAが表示される仕組み
PAAは、検索窓にユーザーが入力したクエリと関連がありそうなコンテンツをAIが自動生成することによって表示されます。
表示される数は特に決まってないものの、3~5つ程度のコンテンツが表示されるケースが多いです。
質問を開くと、その質問に対する答えと掲載先のWebページのURLが表示される仕組みとなっています。
つまり、表示されるコンテンツは、インターネット上のコンテンツから引用されているのです。
また、引用される部分はWebページのすべてではなく、一部が抜粋された状態で表示されます。
そのため、抜粋して表示されているコンテンツについて、ユーザーが興味・関心を抱けば、URLをクリックしてWebサイトへアクセスする可能性が高まります。
特にコンテンツがユーザーにとって良質なものであれば、コンテンツを通じてユーザー体験を高めることも可能です。
そうすると、Webサイトに対するユーザーの評価や信頼が向上し、アクセス数の増加や問い合わせなどのコンバージョンの向上を期待することができるでしょう。
もっとも、コンテンツのどの部分が引用されるかはGoogleが判断するため、Webサイトの運営者側で制御できないことには注意が必要です。
なお、PAAにコンテンツが表示されるアルゴリズムは明確にはなっていないものの、以下のようなコンテンツが表示されやすいといわれています。
- 概念や定義の説明(「○○ と は」や「○○ 意味」など)
- 簡潔にまとめられた回答や解説
- 具体例が箇条書きでまとめられたもの
- 料金や性能などの比較表 など
このように、コンテンツ自体がQ&Aの形式をとっていなくても、具体的な質問に対して回答を示しているような箇所があれば抜粋して表示されます。
そのため、コンテンツ制作の際に上記のような記述を意識することで、PAAに自社サイトのコンテンツが表示される可能性を高めることができるでしょう。
(3)強調スニペットとの違い
PAAと類似したコンテンツには強調スニペットがあります。
強調スニペットもコンテンツの一部が抜粋されて表示されるという点では、PAAとも似ています。
しかし、両者の大きな違いは、表示される場所が異なる点です。
強調スニペットは、検索結果の一番上に表示されるものをいいます。
もっとも、PAAは検索結果の1ページ目の途中に表示され、概ね検索結果の1つ目~3つ目の直下辺りに生成されることが多いです。
その意味では、PAAも強調スニペットも内容としてはほとんど変わりませんが、表示される位置に違いがあることを押さえておきましょう。
強調スニペットの概要や表示形式などの詳細については、以下の記事も合わせてご覧ください。
2.PAA対策を行うことによって得られるメリットと注意点
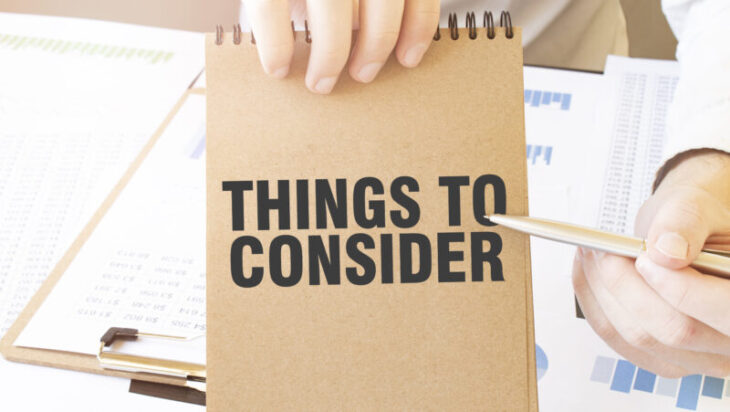
PAAでは、具体的な質問に対する回答内容として、コンテンツの抜粋部分とURLが表示されます。
そのため、その内容に興味を持ったユーザーがURLを介してコンテンツにアクセスすることで、Webサイトやページへの流入を期待することができます。
また、ユーザーが検索の際に入力したクエリと直接関係しないコンテンツであっても、Googleが関連性があると評価すれば、PAAに表示される可能性があるのです。
これによって、ユーザーがURLを介してWebページにアクセスすれば、当初想定していなかったクエリによる流入を期待することもできるでしょう。
その意味では、PAAはSEO対策にも一定の影響を与えるといえます。
なお、PAAの内容を読んで満足したユーザーは、引用元となるURLに遷移することなく離脱する可能性があります(ゼロクリック検索)。
そうすると、PAAに表示されることによって、却ってアクセス数が減少するリスクがあることにも注意が必要です。
もっとも、自社のWebサイトやページへのアクセスを直接伸ばすためには、SEO対策を行うことが大前提となります。
そのため、PAAに表示されることのみを意識した対策を行うよりも、むしろSEO対策をしっかりと行うことが最も重要といえます。
あくまでも正攻法はSEO対策を着実に実行することであり、PAA対策はその中の1つとして位置づけ、PAA対策のみを過度に重視しないことも意識しましょう。
なお、SEO対策をしっかりと行うことは、同時にPAA対策につながることもあるのです。
具体的な対策方法やポイントについては、次項で詳しく解説します。
3.SEOを意識したPAA対策の具体的な方法

先ほども述べたように、PAAはSEO対策にも少なからず影響を与えるといえます。
しかし、PAAのみに向けられた対策を行うよりも、SEO対策を着実に行うことが正攻法であるといえます。
その意味で、コンテンツに関するSEO対策を行うことがPAA対策にもつながるともいえるでしょう。
具体的には、以下の点について対策を行うことが重要です。
- 検索上位に表示される良質なコンテンツを制作する
- Q&Aを意識した簡潔な記述を心がける
- 関連性のある情報について網羅的にコンテンツ制作を行う
- 適切なHTMLを用いてマークアップを行う
- Googleのポリシーに準拠したコンテンツ制作を意識する
なお、上記にはWebマーケティングの1つでもあるコンテンツマーケティングのポイントとも共通するものがあります。
コンテンツマーケティングの概要や具体的な手順などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(1)検索上位に表示される良質なコンテンツを制作する
PAAに表示されるコンテンツは、概ね検索上位に表示される10サイトの情報から引用されている傾向があります。
そのため、自社のコンテンツが検索上位に表示されると、PAAに掲載される可能性が高まります。
検索結果の上位に表示されるためには、検索エンジンから良質なコンテンツであると評価されることが重要です。
具体的には、ユーザーの役に立つようなコンテンツを制作することが必要といえます。
なお、検索エンジンがユーザーにとって価値があると評価する指標には、「E-E-A-T」と呼ばれるものがあります。
これは、以下の4つの要素の頭文字をとったものです。
- Experience(経験・体験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
例えば、自社で独自に行った調査や研究に基づくオリジナリティのあるコンテンツを制作したり、制作したコンテンツについて専門家のチェックを受けたりすることで、これらの要素を高めることができます。
また、ユーザー視点に立った分かりやすい文章やユーザーの検索意図に整合した情報の掲載など、コンテンツの形式や質などについて、総合的に意識を向けることが大切です。
E-E-A-Tを高めるための具体的なポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、SEO効果を高めるためのコンテンツ制作のポイントについては、以下の記事も参考になります。
(2)Q&Aを意識した簡潔な記述を心がける
PAAに掲載される文字数は、概ね50~150文字程度であることが多いです。
そのため、その文字数の範囲で具体的な質問に対する簡潔な回答を提供できるような文章を意識することが大切といえます。
具体的には、「○○とは、~です。」のような要点を押さえた簡潔な文章を心がけましょう。
このような文章は、ユーザーが抱く疑問や悩みに対して明快な回答を提供することにもなり、ユーザーの満足度や信頼を高めることにもつながります。
また、文章の表現だけでなく、記述の流れも意識することが大切です。
具体的には、以下のような流れで記述することがおすすめです。
- 結論
- 理由
- 具体例
- 要点(=「結論」の確認)
このような流れによって記述された文章は、ユーザーが次に抱く疑問に合わせて回答を提示していくスタイルになっているため、ユーザーが納得しながら読み進めることができます。
そのため、ユーザーが離脱することなく最後まで読み進める可能性が高まり、サイト全体の滞在時間が改善する効果も期待できるのです。
また、文章のセクションが上記のようにはっきりと分かれていることによって、PAAに抜粋される可能性も高まるでしょう。
(3)関連性のある情報について網羅的にコンテンツ制作を行う
PAAでは、特定のクエリやキーワードに関連するコンテンツが表示されるため、コンテンツ制作では、関連キーワードを網羅的に把握した上で対策を行うこともおすすめです。
関連キーワードごとにコンテンツを制作して頭数を増やすことで、PAAに掲載される可能性を高めることもできるでしょう。
そうすると、メインの検索クエリやキーワードで自社のコンテンツが上位表示されるのと同時に、PAAでも自社コンテンツが表示・引用されることで、さらなるアクセス数の増加を期待することが可能です。
もっとも、PAAで掲載される部分はコンテンツの一部であり、どの部分が抜粋されるかは運営者や制作者が指定することができません。
そのため、複数のコンテンツを制作しても、必ずしも上位表示とPAA表示の双方を狙うことができるわけではありません。
また、関連するキーワードで複数のコンテンツを制作することで、それらのコンテンツ間でSEO評価が分散してしまう可能性もあります。
さらに、コンテンツ間の差別化がうまく図られていない場合には類似した情報が掲載されることによって、検索エンジンから重複コンテンツと評価される可能性があることに注意が必要です。
重複コンテンツがあるサイトと評価されれば、検索順位が大きく低下し、これまで行ってきたSEO対策も無意味になってしまうリスクもあります。
そのため、コンテンツを分散させるよりも1つのコンテンツ内で関連性のあるトピックを網羅的に盛り込む方が適している場合もあります。
なお、コンテンツ内に関連情報について内部リンクを設定することで、PAA表示を通じてコンテンツにアクセスしたユーザーの回遊率や滞在時間を高めることにもつながります。
このように、PAAを意識した網羅的なコンテンツ制作を行う場合には、SEO評価に与える影響についても考慮した上で戦略を立案することが重要です。
なお、1つのコンテンツに内部リンクを複数設定することでユーザーの回遊率を高めるほか、SEO評価を集中させる手法にトピッククラスターの設計があります。
トピッククラスターの設計方法や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)適切なHTMLを用いてマークアップを行う
検索結果に自社のサイトやコンテンツが表示されるためには、検索エンジンの機能の一部であるクローラーがサイトを訪問し、情報を収集・インデックス登録を行う必要があります。
そのため、クローラーの訪問とインデックス登録を促すために、適切なHTMLを用いてコンテンツやサイトをマークアップすることも重要です。
これは、クローラーがHTMLファイルなどのテキストデータについて情報を収集し、インデックス登録を行うからです。
クローラーがインデックス登録を行ったサイトの情報については、検索エンジンのデータベースに集積され、検索エンジンが独自のアルゴリズムによって検索順位を決定します。
HTMLでは、主にコンテンツの構造のほか、表や画像などの特定のデータ形式についての情報をクローラーに伝えることができます。
これによって、クローラーがページに掲載されている情報を正確に理解することができ、クローラーの巡回のしやすさ(クローラビリティ)を向上させることが可能です。
例えば、コンテンツの章立てには見出しの情報を正しくクローラーに伝えるhタグを用いたり、画像の内容や情報を伝えるためにalt属性を適切に使用したりしましょう。
なお、適切にHTMLタグを用いることは、検索エンジンにコンテンツやページの構造を正しく伝えるだけでなく、ユーザーに対しても有益であることが多いです。
論理的な文章構造はもちろん、適宜本文中に図や表、箇条書きで要点が示されていると、まとまった情報をユーザーは直感的に理解できます。
SEOにおけるhタグの重要性や具体的な設定方法については、以下の記事も参考になります。
また、alt属性の概要やSEO上の意義、設定のポイントについては以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(5)Googleのポリシーに準拠したコンテンツ制作を意識する
コンテンツ制作を行う場合には、Google社があらかじめ定めているポリシーに準拠する必要があります。
これは、Google社がポリシーに反するコンテンツやサイトについては、検索順位に影響を与えることを明言しているからです。
なお、PAAが表示されるためのアルゴリズムは明らかにはされていないものの、PAAと類似する強調スニペットでは、以下のようなコンテンツは表示されないことが明らかにされています。
- 危険なコンテンツ
- 欺瞞行為
- ハラスメントコンテンツ
- ヘイトコンテンツ
- 操作されたメディア
- 医療のコンテンツ
- 性的描写が露骨なコンテンツ
- テロに関するコンテンツ
- 暴力や残虐行為
- 下品な言葉や冒とく的表現
強調スニペットが表示されるアルゴリズムもPAAと同様に公表されていませんが、表示される内容が共通していることなどから、PAAでもこれらのコンテンツは表示されない可能性が高いです。
そのため、上記に該当するようなコンテンツが自社サイトにある場合には、削除やリライトなどの対応を行うことが重要といえます。
4.PAAの活用方法

PAAの内容や表示されるコンテンツについては、実際に検索エンジンを利用して具体的なクエリやキーワードを入力することで確かめることができます。
そのため、現状としてユーザーがどのような質問を行い、その回答を求めているかについてのニーズを把握することが可能です。
PAAを通じてユーザーのニーズを把握することには、以下のような活用方法が考えられます。
- コンテンツの新規制作
- 既存コンテンツのリライト
順に見ていきましょう。
(1)コンテンツの新規制作
ユーザーのニーズを把握することで、自社コンテンツの制作や戦略設計に活かすことができます。
ユーザーのニーズに適合する情報やコンテンツを発信することができれば、ユーザーの満足度を高め、サイトへのアクセス数を伸ばすことにもつながるでしょう。
また、コンテンツ制作はもちろん、キーワードプランの設計などにも活用することが可能です。
ユーザーのニーズを把握・分析することで、ユーザーが求める情報を発信することができ、サイト全体のSEO評価向上も期待することができます。
このように、PAAを通じてユーザーのニーズを把握することは、コンテンツ制作とコンテンツの方向性の策定の双方の観点から有益です。
なお、SEOにおけるキーワードの重要性やキーワードプランの具体的な設計方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)既存コンテンツのリライト
既存のコンテンツをユーザーの現在のニーズに基づいたものにリライトする場合にも活用することが可能です。
自社のコンテンツは一度制作して終わりではなく、定期的に情報の見直しや追加などを行う必要があります。
情報の修正や追加を行うことによって、コンテンツの品質を維持し、ユーザーにとって役に立つ情報を発信し続けることができ、そのことが検索結果の表示にもよい影響を与えます。
情報の修正や追加などによって、良質なコンテンツと評価されれば、ユーザーのアクセス数を伸ばすことができるのです。
また、コンテンツのリライトを行うことによって検索上位に表示されれば、PAAに表示されてさらなるアクセス数の増加を見込めるなど、相乗効果を狙うこともできるでしょう。
まとめ
本記事では、PAAの概要や表示されることによるメリット、具体的な対策方法などについて解説しました。
PAAが表示されるアルゴリズムは公表されているわけではないため、どのような対策を行えば確実に表示されるかについては見通しを持つことが難しい側面もあります。
また、PAAに表示されることのみを目的に対策を行うよりも、まずはSEO対策を着実に行い、検索結果の上位表示を目指すことが最も重要といえます。
しかし、効果的なSEO対策を行うためには、専門的な知識や技術が要求されることも多いです。
そのため、これからSEO対策やPAA対策を行うことを検討されている方にとっては、どのようなことを行うべきか判断に迷うこともあると思います。
そのような場合には、専門の業者やコンサルタントに相談の上で具体的な施策を進めていくのがおすすめです。
SEOを意識したPAA対策について相談したい方は、TMS Partners株式会社へ問い合わせください。
TMS Partners株式会社は、WebサイトのSEO対策をはじめ、サイト制作・改修や広告運用など、幅広い支援を行っています。
問い合わせは無料なので、まずは以下の問い合わせフォームより気になることや質問をお寄せください。