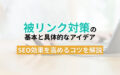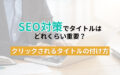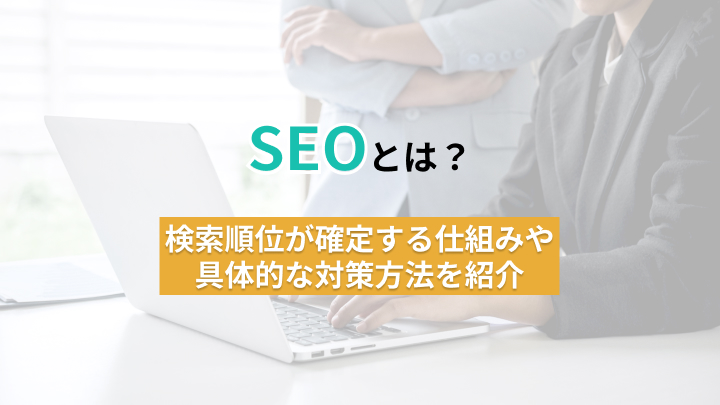ECサイトのSEO対策とは?対策を行うメリットや具体的な方法について解説

「ECサイトにSEO対策を行うとどのようなメリットや効果が期待できるのか」
「具体的にどのようなことを行うべきかが分からない」
「ECサイトへのSEO効果を高めるためのポイントについて知りたい」
企業の経営者やECサイトの運営担当者の中には、このような疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
ECサイトは、自社の商品・サービスを販売するためのツールであるため、自社のECサイトにSEO対策を行うことで、アクセス数の増加や売上の向上が期待できます。
もっとも、具体的にどのような点を押さえながらSEO対策を行うべきか判断に悩むこともあると思います。
実は、ECサイトの場合であっても、押さえておくべきポイントは通常のSEO対策の場合と大きくは変わりません。
本記事では、ECサイトへSEO対策を行うメリットや具体的なポイントについて解説します。
また、SEO効果を高めるためのポイントについても合わせて解説します。
ECサイトへのアクセスを増やすことで売上の向上につなげたい方の参考となれば幸いです。
1.ECサイトとSEO対策の関係

ECサイトは、Webサイトの一種であり、自社の商品・サービスの販売を行うことができます。
これに対して、SEO対策は「検索エンジン最適化」とも呼ばれる施策のことで、インターネット上のWebサイトやページを検索結果の上位に表示させることを目的としています。
そのため、ECサイトであっても、SEO対策を行う対象となりうることを押さえておきましょう。
ECサイトとSEO対策の関係性について、押さえておきたいトピックスは以下の通りです。
- ECサイトとは
- SEO対策とは
- ECサイトにSEO対策を行うメリット
順に見ていきましょう。
(1)ECサイトとは
ECサイトは、オンライン上で商品・サービスの売買を行うことができるWebサイトです。
従来の実店舗での商品・サービスの取引とは異なり、店舗や販売員などを用意する必要がなく、オンライン上で24時間365日やりとりを行うことができます。
そのため、ECサイトを運営することで、店舗や備品、人件費などのコストをカットすることができる点が大きなメリットです。
また、ユーザーにとっても、直接店舗に向かう必要なくいつでも商品・サービスを購入でき、決済までオンラインで完結するため、利便性が高い点がメリットといえるでしょう。
実際に、その手軽さなどを背景として、ECサイトの市場は年々拡大傾向にあることが指摘されています。
そのため、ECサイトを主軸に置いた販売やマーケティング施策は、売上の拡大を目指す上で重要な意味を持つといえます。
なお、ECサイトには、企業が一般消費者との間で取引を行う「BtoC」や企業間取引がメインの「BtoB」など、取引の形態に応じてさまざまなものがあります。
もっとも、その大半は「BtoC」のタイプに属するものが占めるため、本記事では一般消費者向けのものを念頭に置いて解説を行います。
(2)SEO対策とは
SEO対策とは、自社のWebサイトやページが検索結果の上位に表示されることを目的とした施策を指します。
自社のWebサイトやページが検索結果の上位に表示されると、検索ユーザーに認識されやすくなり、クリックやアクセスなどの行動を促すことができます。
これによって、サイトへのアクセス数の増加などの効果が期待できるのです。
なお、検索結果に表示されるためには、検索エンジンの機能の1つでもある「クローラー」に自社のWebサイトやページが巡回される必要があります。
そのため、検索エンジンへの対策が必要不可欠です。
また、ユーザーのアクセスなどを促すためには、ユーザーの視点に立ったサイト設計やコンテンツ制作が欠かせません。
このように、SEO対策では、検索エンジンとユーザーの双方を意識しながら具体的な施策の立案・実行を進めることが大切です。
SEO対策には、大きく分けると以下の対策方法があります。
- 内部対策
- 外部対策
- コンテンツ対策
これらについては、ECサイトを対象としたSEO対策でも意識すべきポイントといえます。
具体的な対策方法については、2以降で詳しく解説します。
なお、SEO対策の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)ECサイトにSEO対策を行うメリット
自社のECサイトにSEO対策を行うことで、検索結果の上位に自社のECサイトが表示される可能性が高まります。
検索結果の上位に自社のECサイトが表示されることで、ユーザーのアクセス数が増加し、商品・サービスの購入につながり、売上の向上も期待できるのです。
先ほども述べたように、ECサイトを巡る動向は活発であり、ユーザーのニーズも引き続き高いまま推移しています。
特にECサイトへのユーザーの流入経路は、検索エンジンを通じた自然検索が最も多い傾向にあります。
そのため、ECサイトにSEO対策を行い、検索結果の上位に表示させることは、ECサイトを起点とした売上を伸ばすためには有効な施策であるといえるでしょう。
2.内部対策編|ECサイトのSEO対策方法

ECサイトを対象とするSEO対策のうち、内部対策では、主に検索エンジンのクローラーへの対策が中心となります。
これは、自社のECサイトへクローラーの巡回とインデックスを促すことで、より早期に検索結果に表示されるように対策を行うことを目的としています。
具体的には、以下のような対策方法をとりましょう。
- サイトの階層構造を最適化する
- サイトマップを作成・登録する
- パンくずリストを整理する
- 重複ページに適切に対処する
順にご説明します。
なお、SEO対策を適切に進めていくためには、検索エンジンの仕組みと検索結果が決まるアルゴリズムについて把握しておくことが必要不可欠です。
検索エンジンやクローラーの仕組みについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
また、検索エンジンの中でもGoogle社の検索アルゴリズムについては、以下の記事が参考になります。
(1)サイトの階層構造を最適化する
Webサイトの構造は、階層を深くしすぎず、可能な限りシンプルなものにすることが重要です。
クローラーはWebサイトを巡回するとき、特定のページを起点としてページ内に設置されているリンクをたどりながらそのサイト全体を巡回し、情報を収集・インデックス登録を行います。
階層が深すぎる場合や複雑なサイト構造の場合には、クローラーが効率よくサイト全体を巡回することができません。
これによって、自社のECサイトの重要なページの情報収集が行われず、インデックス登録もされなければ、検索結果に表示されない可能性が高まります。
そのため、サイト構造やディレクトリ構造をシンプルにすることで、クローラーの効率的な巡回を促すことにつながります。
なお、このような対策は、ユーザーにとっても有益であることを押さえておきましょう。
ユーザーの利便性(ユーザビリティ)という観点からは、2クリック程度で目的のページにたどり着くような階層構造が最適であるともいわれています。
そのため、サイト構造の最適化は、クローラーの巡回のしやすさ(クローラビリティ)とユーザーの利便性(ユーザビリティ)の双方の観点からも重要であるといえるでしょう。
なお、具体的なサイト構造の設計方法やECサイトの購買導線の作り方については、以下の記事も参考になります。
(2)サイトマップを作成・登録する
サイトの階層構造を最適化させると同時に、サイトマップも作成しましょう。
サイトマップとは、Webサイト全体の構造を表したファイル形式のデータのことをいいます。
Webサイトやページを訪問したユーザーに対してサイト全体を示すもの(HTMLサイトマップ)をイメージする方もいるかも知れませんが、ここでのサイトマップとは検索エンジンに対するもの(XMLサイトマップ)を指します。
具体的には、XMLサイトマップには、検索エンジンのクローラーが理解できる言語を用いて、ページのリストやページごとの更新頻度などについて記述します。
これを作成し、登録することで、クローラーの効率的な巡回を促すことができるのです。
例えば、ページごとに最終更新日を検索エンジン側に伝えることが可能であり、これによってECサイトでは新商品のページや情報の更新が加えられたページを優先的にクロールさせることができます。
そのため、優先的に売り出したい商品・サービスなどのページが早期にクロールされてインデックス登録がされると、検索結果にも早期に表示される可能性が高まります。
これによって、商品・サービスの認知度を高め、売上の拡大につなげることもできるでしょう。
なお、サイトマップの具体的な作成方法やポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(3)パンくずリストを整理する
パンくずリストとは、表示されているWebページがサイト全体の中でどこに位置づけられているかを示すものです。
例えば、以下のような形式で表示されます。
ホーム >サービストップ >SEO
これによって、Webページを閲覧するユーザーがサイトの中でどの位置にいるかを確認することができます。
また、それぞれのテキストには内部リンクが設定されていることも多く、該当箇所をクリックすると元のページに戻ることができるようになっています。
パンくずリストは、ユーザーだけでなく、クローラーの巡回のしやすさにもよい影響を与えます。
クローラーはページのリンクをたどりながらサイト全体を巡回し、情報を収集・インデックス登録を行います。
パンくずリストを設置することで、クローラーがサイト構造を把握し、たどることができるリンクを増やすことができるため、巡回の効率を高めることが可能です。
なお、パンくずリストを整理する場合には、サイト構造を反映した形式のほか、サイトで扱われる情報の属性などに合わせて整理する方法もあります。
例えば、以下のようなものです。
ホーム >商品 >カテゴリ >カラー
特に商品・サービスを扱うECサイトでは、ユーザーの検索の利便性などを念頭に置いた上で、商品・サービスの属性やユーザーのニーズなどを基準としてパンくずリストが整理されることが多いといえます。
このように、サイトの性質や情報などを考慮した上で、自社サイトに適したパンくずリストの整理が必要となることも押さえておきましょう。
パンくずリストの種類やSEO上の効果、具体的な実装のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)重複ページに適切に対処する
同じ商品でも、色やサイズなどによっては異なるページが自動生成される機能があります。
特にECサイトでは、ユーザーが検索した条件に従って、ページが自動的に生成され、その数が膨大になることもあるのです。
そのような場合には、クローラーはそれらのページを重複コンテンツと評価し、クロールをやめたりインデックスをしなかったりする可能性があります。
そのため、サイトの階層構造の最適化と合わせ、商品・サービスに関する自動生成ページの調整も行うことが大切です。
例えば、色やサイズ違いの商品情報は同じページ内にまとめて購入できるような設計にするほか、URLの正規化を行うなどして適切な対処を行うことがおすすめといえます。
また、情報を一覧で確認できることは、ユーザーの利便性を考える上でも有益です。
URLの正規化を行うこととSEO上の効果の関係や技術的なトピックについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
3.外部対策編|ECサイトのSEO対策方法

ECサイトにSEO対策を行う場合には、上記のような内部対策に加えて、外部対策に取り組むことも大切です。
外部対策では、主に被リンクの獲得を目指します。
具体的には、他社のWebサイトに自社のECサイトのリンクが貼られるように対策を行うことが重要です。
そのためには、他社がリンクを貼りたくなるような魅力的な商品・サービスの品揃えを強化したり、ユーザーの利益になるような良質なコンテンツを制作したりするようにしましょう。
他社がリンクを貼ることによって、自社サイトが優良なものであると評価されることにつながります。
例えば、お酒を販売するECサイトの場合、お酒の蔵元や製造メーカーのWebサイトで提携サイトとしてリンクを獲得することができれば、ユーザーも安心してそのサイトで商品を購入することができるでしょう。
また、ユーザーが自発的に口コミやSNSなどを通じてサイトを紹介する可能性もあります。
そうすると、ユーザーの間で話題となり、さらなるサイトへのアクセスや認知度の向上を期待することができます。
ユーザーの口コミなどは、被リンクの獲得とは異なり、直接的にSEOに影響を与えるものではありませんが、自社のECサイトの評価を高めることに間接的な効果を得ることができる可能性もあります。
このように、自然発生的に被リンクを獲得したりユーザーの評価を高めたりするためには、自社サイト内に向けられた対策はもちろん、サイトの外へ向けた対策も積極的に行うことが大切です。
被リンクの獲得がSEOに与える具体的な効果や対策のためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、ユーザーの口コミや評価(サイテーション)を得るSEO上のメリットやサイテーションを獲得するための具体的な方法については、以下の記事が参考になります。
4.コンテンツ対策編|ECサイトのSEO対策方法
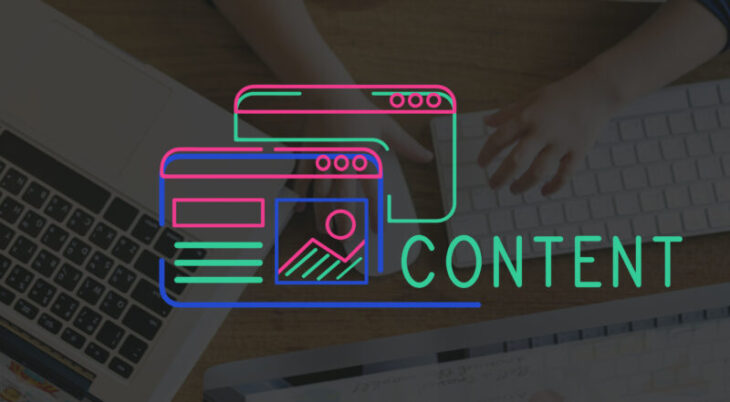
ユーザーへ向けたSEO対策としては、コンテンツ対策を行うことを検討しましょう。
ユーザーにとっての利便性を向上させることは、サイトへのアクセス数の増加やユーザーのアクションなどに直接影響を与えます。
そのため、コンテンツのタイトルや品質などに着目し、ユーザー目線で制作・改善を加えることが最も重要です。
具体的には、以下のポイントを押さえましょう。
- 最適なキーワードを選定する
- タイトルやメタディスクリプションの内容を工夫する
- 掲載する情報を工夫する
- 販売に関する情報を正しく表示する
- メディアECの活用も検討する
なお、ECサイトに効果的なマーケティング戦略については、以下の記事も参考になります。
(1)最適なキーワードを選定する
ユーザーが検索しそうなクエリをもとにして具体的なキーワードを選定することが大切です。
例えば、自社でお酒を販売するECサイトを運営している場合には、「お酒 購入 サイト」のほかにも、「お酒 買える サイト」、「お酒 サイト 安い」などの関連するキーワードも選定しましょう。
また、ECサイトで扱っている商品の種類や品目ごとにキーワードをマッピングすることもおすすめです。
具体的には、以下のようなものが考えられるでしょう。
| 種類・品目 | 具体的なキーワードの例 |
| 日本酒 |
|
| ビール |
|
| ウイスキー |
|
| 焼酎 |
|
| ワイン |
|
このように、共起語やロングテールキーワードなども意識しながら選定を進めましょう。
共起語とは、ユーザーが検索を行うときに、ある検索キーワードと一緒に使われることが多い語句のことをいいます。
上記の例では、「通販」と「サイト」、「購入」と「安い」などがこれにあてはまるでしょう。
また、ロングテールキーワードとは、いくつかの語句をつなぎ合わせたキーワードで、比較的長いものが多いのが特徴です。
上記の例の中では、「オンライン 芋 焼酎 安い おすすめ」や「記念 日 白 ワイン 通販」などがロングテールキーワードにあたります。
共起語やロングテールキーワードには、ユーザーのニーズや検索意図が隠れていることがあり、これらを適切に使用することで潜在層にもアプローチすることが可能です。
このように、自社のECサイトに流入させたいユーザー層を念頭に置きながら、自社の商品・サービスと整合性のあるキーワードを選ぶようにしましょう。
共起語とロングテールキーワードの具体的な活用方法については、以下の記事も参考になります。
(2)タイトルやメタディスクリプションの内容を工夫する
ユーザーが具体的なクエリやキーワードで検索した後に、検索結果からどのサイトにアクセスするかはタイトルとメタディスクリプションの内容が重要な役割を持っています。
そのため、タイトルとメタディスクリプションの内容に工夫をこらすようにしましょう。
具体的には、タイトルにはサイト名を含めることがおすすめです。
例えば、ユーザーが「お酒 通販 サイト」のキーワードで検索した場合に上位表示を目指すなら、「日本中のお酒が大集合する通販サイト|○○(サイト名)」のようにしましょう。
これによって、自社のECサイトに対するユーザーの認知を醸成することができます。
なお、タイトルには上位表示を狙うキーワードを含め、30文字程度におさまる文章を記述することがおすすめです。
また、メタディスクリプションはタイトルの直下に表示されるものですが、サイトやページの概要が一目で分かるような文章にするようにしましょう。
例えば、「お酒 通販 サイト」の場合には、扱っているお酒の種類や品数、配送の条件(○円以上購入で送料無料、1本から配送承ります、など)や範囲(首都圏、全国など)などの情報も含めることがおすすめです。
さらに、簡潔な文章を心がけ、目安として80文字以内におさまるように記述するようにしましょう。
ただし、キーワードをただ詰め込んだような不自然な文章や商品・サービスと関連性のない文章はユーザーに違和感や不信感を与え、離脱の原因になる可能性があります。
また、そのような表現を用いると、検索エンジンからはスパムコンテンツと評価されてしまい、ペナルティの対象となるリスクもあるため注意が必要です。
なお、SEO上で効果的なタイトルのつけ方のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、メタディスクリプションの実践的な書き方や注意点などについては、以下の記事をご覧ください。
(3)掲載する情報を工夫する
商品・サービスのページでは、商品の画像や価格、型番号などの基本情報を掲載することはもちろん、ユーザー視点に立ったコンテンツを制作することが重要です。
例えば、お酒のECサイトの場合には、お酒の購入以外にも、お酒の種類や飲み方に関するキーワードやクエリでユーザーが検索することもあるため、それに応じてコンテンツを工夫しましょう。
具体的には、赤ワインのページの場合には、産地情報や年式、味わい(ライト・ミディアム・フル)、ペアリングにおすすめのおつまみや食べ物など、ユーザーがお酒の基本情報と合わせて知りたいと思われる情報を適宜追加することが大切です。
商品・サービスの情報を起点として、それに関連する情報を網羅的に提供することができれば、ユーザーの目にとまり、サイト全体の滞在時間が長くなる可能性が高まります。
これによって、サイト全体の回遊率を高めることにもつながり、コンテンツに興味を持ったユーザーが購入などの具体的なアクションを起こすことが期待できるでしょう。
このように、ユーザー視点とキーワードの関連性を踏まえた上で、適切なコンテンツ制作を行うこともユーザビリティという観点からは必須といえます。
(4)販売に関する情報を正しく表示する
商品・サービスの販売が終了したり、在庫が欠品していたりする場合には、その情報を正確に反映し、表示させることが大切です。
特にECサイトで扱っている商材が有形のものである場合には、購買需要の変動などによっては、販売終了や欠品が避けられないこともあります。
また、欠品していても在庫の補充に伴って、再び販売できる状態になることもあります。
そのような場合に、商品の在庫情報を正しく表示していなければ、ユーザーは買いたい商品を購入できないと判断し、離脱してしまう可能性が高まることに注意が必要です。
そうすると、販売の機会損失となり、売上につながらないだけでなく、正しい情報が反映されていないサイトと評価されてアクセス数が減少してしまう可能性もあります。
これによって、サイト全体のSEO評価にも悪い影響を与えてしまうリスクがあることにも留意しておきましょう。
そのため、ECサイト内の情報の正確性には細心の注意を払うことが大切です。
(5)メディアECの活用も検討する
メディアECとは、ECサイトにWebメディアのようなコンテンツ機能を加えたものです。
ECサイト上で商品の使い方やお役立ち情報などを読み物として発信するメディアがこれにあたります。
メディアECを活用することで、コンテンツを通して商品・サービスへの興味関心を醸成し、潜在的なニーズを持つユーザーのアクセスと購買アクションを促すことが可能です。
例えば、お酒のECサイトの場合には、「ワインの銘柄の比較」や「赤ワインのペアリングにおすすめの食べ物ランキング」、「日本酒をおいしく味わうための徳利と御猪口の選び方」などのコンテンツが考えられるでしょう。
ユーザーにとって有益であると思われるコンテンツを定期的に発信することで、自社サイトの認知度や信頼を獲得することにもつながります。
これによって、コンテンツを介したサイト全体へのアクセス数の増加や売上の拡大を期待することも可能です。
もっとも、ユーザーの興味関心を掴むコンテンツ制作を行うためには、ユーザー理解とマーケティング調査が欠かせません。
また、定期的にコンテンツを制作するだけの人的リソースの確保が必須であるほか、成果につながるまでに時間がかかることもある点に注意が必要です。
コンテンツを活用したマーケティング手法や具体的な成功事例については、以下の記事も合わせてご覧ください。
5.ECサイトへのSEO対策の効果を高めるためのポイント
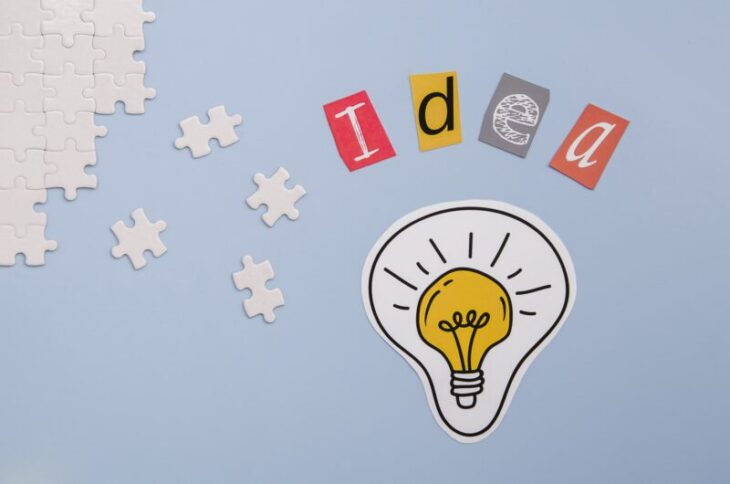
上記で述べたように、ECサイトへSEO対策を行う場合には、検索エンジンとユーザーの双方に向けた対策を行うことが重要です。
もっとも、これらの対策を行えば、自動的に自社サイトのSEO評価が高まるわけではありません。
これらの対策を行う上で、以下のようなポイントも追加で意識することで、SEO効果を高めることにつながります。
- SSL化の対応をしておく
- インデックス状況について定期的に確認する
- ページの表示速度を改善する
- モバイルフレンドリーの対応を行う
順に解説します。
(1)SSL化の対応をしておく
SSLは、「Secure Sockets Layer」の略で、インターネット上でのデータ通信を暗号化するシステムを指します。
顧客情報の入力や登録が必須となる決済システムを導入していることが一般的なECサイトでは、SSL化の対応を行っていない場合には、顧客情報が窃取されてしまう可能性が高まります。
そのため、SSL化がされていないサイトでは、ユーザーが安全性に疑問や不信感を抱き、購入につながらないことがあるため、注意が必要です。
なお、SSL化を行っていることは、SEO評価上も有利にはたらきます。
これは、Google社が検索結果に表示させるWebサイトの順位について、SSL化を行っているサイトを優先的に上位に表示させることを表明しているからです。
つまり、自社のECサイトにSSL化を行うことは、ユーザーだけでなく検索エンジンに対しても、サイト全体のセキュリティ対策の万全性をアピールすることを意味するといえるでしょう。
SSL化の設定方法や注意すべきポイントについては、以下の記事も参考になります。
(2)インデックス状況について定期的に確認する
上記のような対策を行ったとしても、検索エンジンに正しく認識されない限りは検索結果に表示されません。
そのため、自社のECサイトがクローラーにインデックスされているかについては、定期的に確認するようにしましょう。
クローラーがインターネット上のWebサイトやページを巡回する活動量には、上限があります。
例えば、1つのWebサイトについて巡回できるリンクの数には割り当ての上限があり、それを超過してしまうとクローラーはサイトを離れてしまいます。
特に商品のサイズや色に応じて自動的にページが生成される場合、すぐに割り当ての上限に到達してしまい、重要なページをクローラーが巡回する前に離脱してしまう可能性が高まります。
そうすると、インデックス登録もされないことになり、特に新商品などの情報がタイムリーに検索結果に表示されないことによる機会損失のリスクがあることに注意が必要です。
そのため、Google Search Consoleなどのツールを活用して、インデックス登録の状況を確認したり、登録がされていない場合には必要に応じてクローラーの巡回とインデックス登録を促す対策をとるようにしましょう。
インデックスの状況を確認する具体的な方法やインデックスを最適化するためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)ページの表示速度を改善する
ページが表示されるスピードを改善させることは検索結果によい影響を与えるほか、ユーザビリティの観点からも重要です。
ページが表示される速度が遅い場合には、クローラーはサーバーへ負荷がかかることを考慮し、サイトを巡回することなく離脱してしまう可能性が高まります。
そうすると、ページのインデックスも行われず、検索結果に表示されない可能性があります。
また、表示速度の遅いページやサイトでは、ユーザーの離脱原因にもなるため、注意が必要です。
ページの表示速度がSEOに与える具体的な影響や改善方法、計測ツールについては以下の記事が参考になります。
(4)モバイルフレンドリーの対応を行う
モバイルフレンドリーとは、スマホ(SP)やタブレットなどのモバイル端末に最適化されたデザインのことをいいます。
特に一般消費者を対象とするECサイトでは、スマホ(SP)などからのアクセス数が多い傾向があります。
そのため、モバイルフレンドリーに対応した調整を行うことで、ユーザビリティを高めることにつながります。
なお、Google社は2015年から2016年にかけてアルゴリズムのアップデートを行い、モバイル端末への最適化を行っているWebサイトを優先的に検索結果の上位に表示させる対応を行いました。
そのため、モバイルフレンドリーの対応を行うことで、上記のような対策と合わせて、よりSEO対策の効果を高めることができるでしょう。
モバイルフレンドリーなサイトを構築するためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、ECサイトへSEO対策を行う重要性や具体的な方法などについて解説しました。
ECサイトへ効果的なSEO対策を行うことで、アクセス数の増加や売上の向上など、自社にとってよりよい効果を期待することができます。
もっとも、具体的なSEO対策の方法は多岐にわたり、商材や自社のECサイト戦略とも整合的な対策を行うことが重要といえます。
しかし、どのような対策から始めればよいのか疑問や悩みがあり、具体的な対策を行えない場合には、専門の業者や企業に相談するのがおすすめです。
ECサイトのSEO対策について相談したい方は、TMS Partners株式会社へ問い合わせください。
TMS Partners株式会社は、効果的なSEO対策をはじめ、サイト制作・改修や広告運用など、幅広い支援を行っています。
問い合わせは無料なので、まずは以下の問い合わせフォームより気になることや質問をお寄せください。