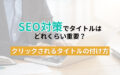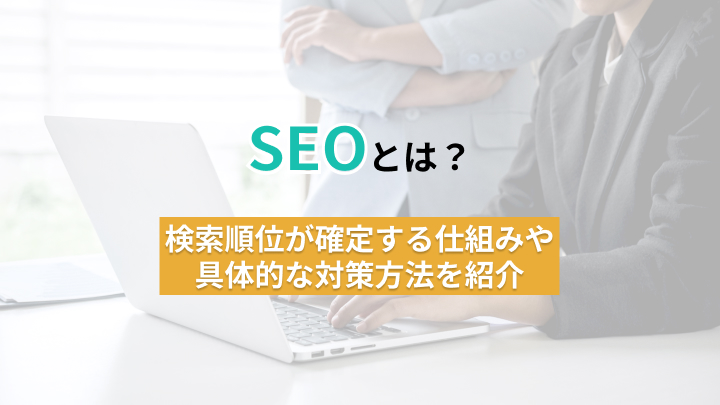Googleの検索アルゴリズムとは?影響を与える要素や効果的なSEO対策

「Googleの検索アルゴリズムとはどのようなものなのか」
「アルゴリズムに影響を与える要素は?」
「効果的な対策方法や順位変動が生じた際の対処法について知りたい」
企業の経営者やマーケティング部門の担当者、Webサイトの運営者の中には、このような疑問やお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
Googleの検索アルゴリズムとは、Google社の検索エンジンに関するルールのことです。
インターネット上での情報の検索・収集が一般的になった現在では、検索エンジンを起点としたマーケティング戦略が必要不可欠となりつつあります。
自社のWebサイトやコンテンツに検索ユーザーがアクセスし、問い合わせや商品・サービスの購入などのアクションをとってもらうためには、自社のWebサイトが検索結果の上位に表示され、露出度を増やしていくことが求められます。
そのためには、検索エンジンを規律するアルゴリズムやルールを把握することが最も大切です。
本記事では、Googleの検索アルゴリズムの内容や影響を与える主な要素などについて解説します。
また、効果的なSEO対策方法やアルゴリズムのアップデートに伴う順位変動への対処法などについても合わせて解説しています。
検索エンジンに関するアルゴリズムは、自社のWebサイトやコンテンツを上位表示させることを目的とするSEO(検索エンジン最適化)施策とも密接に関わります。
SEO対策と検索順位の関係性や目指すべき順位などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
1.Googleの検索アルゴリズムとは

Googleの検索アルゴリズムとは、検索エンジンが特定のキーワードやクエリに対して、インターネット上から最適な情報を抽出して表示させるルールを指します。
つまり、どのような情報をどのような順位で表示させるかについてのルールということができるでしょう。
具体的には、Google社はインターネット上のWebサイトについてさまざまな項目から評価を行い、そのサイトの評価に基づいて検索順位を決定します。
そのため、Googleの検索アルゴリズムを把握することは、自社のWebサイトやコンテンツを上位表示させるためには必要不可欠といえるでしょう。
なお、検索エンジンはインターネット上のWebサイトから情報を取得し、データベースに集積することで具体的な情報を検索結果として表示させます。
このような一連の流れを「クローリング」といい、検索結果に自社のWebサイトを表示させるためには、このクローリングのメカニズムを押さえることも重要です。
クローリングの仕組みや効果的な対策方法などについては、以下の記事も参考になります。
2.Googleの検索アルゴリズムに影響を与える5つの要素

Googleの検索アルゴリズムは、200以上の評価基準によって構成されています。
また、中には評価基準の詳細が公表されていないものもあります。
そのため、アルゴリズムを決定する要素のすべてを把握し、対策を行うことはあまり現実的ではなく、不可能に近いとされているのです。
もっとも、アルゴリズムに大きな影響を与える要素については、主に以下のようなものがあることが知られています。
- 検索意図
- コンテンツの品質
- キーワードとコンテンツの関連性
- ユーザビリティ
- 検索ユーザーに最適化された条件
これらは、Google社も検索順位に影響を与える要因として公表しています。
そのため、これから自社のWebサイトの検索順位を上げるために具体的な対策を行うことを検討されている方は、ぜひポイントを押さえておきましょう。
(1)検索意図
検索意図とは、検索ユーザーがどのような情報を得るために検索を行っているかを意味する概念です。
具体的には、検索ユーザーの検索意図には、以下のような分類があるとされています。
| 検索意図の種類 | 具体的な内容 |
| Know | 疑問に対する答えを探している |
| Do | 具体的な行動に結びつく情報を探している |
| Go | 特定の場所やWebサイトにたどり着く情報を探している |
| Buy | 商品・サービスを購入するために必要な情報を探している |
検索ユーザーが持つこのような検索意図は、実際に検索エンジンに入力するキーワードやクエリに現れることが多いです。
例えば、「seo と は」というキーワードを入力したユーザーは、SEOという概念について網羅的な情報を把握したい検索意図があるといえます。
これに対して、「seo 依頼 制作 会社」の場合には、SEOに関して具体的なアクションを起こすことを前提に、それを依頼できる業者や専門家を探していることを意味するでしょう。
このように、検索キーワードやクエリによって、検索ユーザーが欲している情報が微妙に、あるいは大きく異なることに注意が必要です。
そのため、具体的な検索キーワードやクエリを起点として、コンテンツの設計や制作を進めていくことが重要といえるでしょう。
キーワードがSEO上で持つ意義や具体的な選定方法のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)コンテンツの品質
コンテンツ自体の品質も検索結果に影響を与えます。
Google社は検索ユーザーにとって有益といえるコンテンツやWebサイトを優先的に表示させることを公表しています。
そのため、ここでのコンテンツの品質とは、検索ユーザーを基準にして判断されることに注意が必要です。
具体的には、検索意図に最も合致したコンテンツが優先的に検索順位に反映されていくことになります。
検索意図に合致してるかどうかを判断する基準には、以下のようなものがあるとされています。
- コンテンツ内で最新の情報が扱われている
- コンテンツを通じてユーザーが良質な体験ができる
- コンテンツ内に検索キーワードが現れる回数・頻度 など
これらを満たすことで、上位表示を狙うことができるのです。
もっとも、以下のようなものについては、品質が低いと評価され、検索順位を落としてしまう可能性があるため、注意が必要となります。
- 検索キーワードを無作為に繰り返す
- コンテンツ内にユーザーの知りたい情報が含まれていない
- ほかのWebサイトからリンクを購入している など
このようなコンテンツは、低品質なものであり、検索ユーザーにとって役に立つものであるとはいえません。
そのため、このようなコンテンツが存在するWebサイトは、検索エンジンからの評価を下げ、検索結果に表示されないなどのペナルティを受けるリスクもあるのです。
(3)キーワードとコンテンツの関連性
検索キーワードに対して、コンテンツの関連性が深いかどうかもアルゴリズムに影響を与える要素の1つです。
検索エンジンは、インデックスという処理が施され、データベースに集積されている情報の中から検索キーワードとの関連性が高いものを表示させます。
その際に判断要素となるのは、以下のような項目です。
- 検索キーワードの出現回数・頻度
- タイトル
- 見出しの構成
- 本文の内容・情報 など
このように、複数の要素から総合的に関連性が評価されることを押さえておきましょう。
また、画像や動画などの視覚的な情報のほか、独自の調査や研究に基づくオリジナリティのある情報が掲載されているかどうかもキーワードとコンテンツの関連性が評価される上では重要な要素といえます。
これらを通じて、検索ユーザーの意図に整合的なコンテンツ設計や制作を意識することが検索結果によい影響を与えることにつながるのです。
なお、上記のような判断要素の中でも、とりわけコンテンツのタイトルは検索ユーザーとの最初の接点となります。
そのため、SEO効果を高めるためには、コンテンツのタイトルにもこだわる必要があるといえるでしょう。
SEO上で効果が期待できるタイトルの作り方や改善のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
(4)ユーザビリティ
ユーザビリティとは、検索ユーザーにとってのWebサイトの見やすさ・使いやすさを意味します。
例えば、同じPCからアクセスする場合でも、検索ユーザーによってはその環境やブラウザが異なることがあります。
Google ChromeとMicrosoft Edgeというブラウザの違いによって、動作スピードが異なる場合には、ユーザビリティに影響を与えます。
そのため、ブラウザの違いに関わらず、同じ表示スピードや画面のレイアウトの最適化などの対応を行うことが重要といえます。
なお、従来は、インターネット上のコンテンツはPCから閲覧されることが一般的でした。
しかし、SP(スマホ)やタブレット端末などの普及に伴い、PC以外のデバイス(端末)からのWebサイトやコンテンツへのアクセス数が増加しています。
そのため、どのデバイスを用いても、使いやすく、見やすいコンテンツであることも重要なのです。
(5)検索ユーザーに最適化された条件
検索結果に表示されるコンテンツの順位は、検索キーワードやコンテンツなどの要素だけではなく、検索ユーザー自身の情報や属性によっても変動します。
具体的には、以下のような要素によって表示される情報に変化が生じるのです。
- ユーザーの現在地
- ユーザーの検索履歴
- ユーザーの属性 など
Googleは、検索ユーザーにとって最適であると考えられる情報を優先的に表示させる機能があります。
例えば、京都の検索ユーザーが「レストラン」と検索すると、京都府内のレストランが検索結果に表示されます。
また、京都駅付近で検索を行った場合には、京都駅周辺のレストランから優先的に表示されることになるのです。
このように、検索ユーザーの現在地や属性などによって、検索結果に表示される情報の順位は変動します。
そのため、このような検索ユーザー側の要素によっても自社のWebサイトやコンテンツが表示される順位が変動・最適化されることも押さえておきましょう。
3.アルゴリズムのアップデートに関する動向

検索結果の表示に関するアルゴリズムは、定期的に更新・アップデートが行われています。
そのため、効果的なSEO対策を行うためには、アップデートの内容と動向を定期的にフォローすることが必要不可欠です。
アップデートは毎年のように行われていますが、中には1年のうちに複数回にわたって更新が行われることもあります。
現在に至るまでのアップデートの中でも、以下の内容が特に重要です。
- パンダアップデート(2011年)
- ペンギンアップデート(2012年)
- ハミングバードアップデート(2013年)
- モバイルフレンドリーアップデート(2015~2016年)
- スピードアップデート(2018年)
- ヘルプフルコンテンツアップデート(2022年)
これらのアップデートの内容は、今後のGoogleのアルゴリズムの基本方針ともなっており、これらの内容を把握しておくことが今後のSEO対策のためにも有益です。
(1)パンダアップデート(2011年)
パンダアップデートと呼ばれるアップデートは、上記で述べた要素のうち、コンテンツの品質に関わるものです。
2011年に1回目のアップデートが行われたのをはじめ、現在まで断続的に更新が続けられています。
初回のアップデートでは、以下のようなコンテンツが規制の対象となり、検索結果の順位低下や非表示などの対策がとられました。
- 外部サイトなどからのコピーコンテンツ
- 自動生成されたコンテンツ
- アフィリエイトコンテンツ など
これらに共通しているのは、オリジナリティに欠けている点が挙げられます。
独自性や専門性に乏しいコンテンツの順位を低下させることによって、検索ユーザーにとって有益なオリジナリティのあるコンテンツが優先的に表示されるようになったのです。
(2)ペンギンアップデート(2012年)
ペンギンアップデートでは、過剰なSEO手法やスパムを用いた集客目的のコンテンツやWebサイトが規制の対象となりました。
特に外部のWebサイトから大量の被リンクを受けている場合には、コンテンツの品質が低くても検索上位に表示されていたのです。
これによって、お金を払うことによって不正に被リンクを獲得して検索順位を押し上げる行為が横行していました。
ペンギンアップデートによって、これらの悪質性の高い行為が規制され、検索順位を大きく低下させることになったのです。
(3)ハミングバードアップデート(2013年)
ハミングバードアップデートは、上記の要素のうち、検索ユーザーに最適化された情報に関するアップデートといえます。
従来、検索キーワードについては、入力された単語や語句と一致する情報を機械的に表示するものでした。
例えば、「書店 近く」と入力すると、Webサイトやコンテンツにこの単語を含んでいる情報が優先的に表示されていました。
そのため、検索ユーザーの意図する情報とはかけ離れたものが優先的に表示されていたのです。
しかし、ハミングバードアップデートにより、検索エンジンが入力されたキーワードの意図を推測し、その検索意図と密接に関わる情報を優先的に表示するようになりました。
具体的には、ユーザーが京都駅付近で「書店 近く」と検索すると、京都駅周辺の書店が上位に表示されるようになったのです。
(4)モバイルフレンドリーアップデート(2015~2016年)
モバイルフレンドリーとは、WebページやコンテンツをSP(スマホ)やタブレット端末に合わせて最適化することです。
これは、SP(スマホ)やタブレット端末の普及に伴い、モバイルフレンドリーの対応を行っているWebサイトを優先的に表示させるものであり、上記の要素のうちのユーザビリティに関するものといえます。
具体的には、以下の要素によってモバイルフレンドリーかどうかの評価がなされます。
- 画像サイズ
- 文字のフォントサイズ
- ページの表示速度 など
このように、SP(スマホ)対応を行い、ユーザビリティに対する改善を行うことも重要になったといえるでしょう。
モバイルフレンドリーの基本概念や確認方法、注意点などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(5)スピードアップデート(2018年)
スピードアップデートは、上述のモバイルフレンドリーアップデートを踏まえて、主にモバイル端末用のサイトやページの表示速度に関するものです。
従来、Webサイトやページの表示速度が検索結果の順位に影響を与えることは知られていました。
もっとも、このような評価がなされる対象はPC用のサイトやページのみでした。
スピードアップデートでは、表示速度に関する順位の影響がモバイル用のサイトやページにも及ぶことが明らかとされたのです。
(6)ヘルプフルコンテンツアップデート(2022年)
ヘルプフルコンテンツアップデートは、検索順位を上げるためだけに制作されたコンテンツを排除して、検索ユーザーにとって有益なコンテンツを優先的に表示させることを目的としたものです。
低品質なコンテンツの順位が低下しただけでなく、そのようなコンテンツを大量に含んでいるWebサイト自体も順位が下がったことに特徴があります。
これによって、企業やWebサイトの運営者は、これまで以上にコンテンツの品質などがユーザーにとって有益であるかどうかについて、再評価を行う必要が求められているといえるでしょう。
4.アルゴリズムに対する効果的なSEO対策

Googleのアルゴリズムは定期的に更新が行われます。
そのため、アップデートが行われるごとに、その内容や方針について把握を行い、対策を進めることが重要です。
もっとも、アップデートが繰り返されたとしても、基本方針については大きく変わらないことがほとんどです。
具体的には、以下の点について意識することが効果的といえるでしょう。
- 検索ニーズを満たす良質なコンテンツを制作する
- TDHを意識する
- モバイルフレンドリーの対応を行う
- ページの表示速度を改善する
- サイトの構造を最適化する
これらについては、Google社のガイドラインでも言及されており、効果的かつ実施しやすいといえるでしょう。
なお、SEO対策の概要や具体的な施策、効果測定の方法などについては、以下の記事も参考になります。
(1)検索ニーズを満たす良質なコンテンツを制作する
検索順位には、コンテンツ自体の品質だけでなく、検索キーワードとの関連性も影響を与えます。
そのため、検索ニーズを分析した上で、それに合わせたコンテンツ制作を行うことが最も重要です。
特にコンテンツの品質については、「E-E-A-T」と呼ばれる指標を重視しましょう。
これは、Google社も検索アルゴリズムに影響を与える要素として挙げており、具体的には以下のようなものを意味します。
- E(Experience):経験
- E(Expertise):専門性
- A(Authoritativeness):権威性
- T(Trust):信頼
特に金融や法律、医療などの専門性の高い分野では、「E-E-A-T」が重視される傾向にあります。
そのため、上記のような分野に属するコンテンツ制作を行うためには、専門家の監修や専門機関からの被リンクの獲得など、コンテンツ内に工夫をこらすことが重要です。
また、コンテンツ内に専門家の監修や専門機関の被リンクが設定されている場合には、検索ユーザーも安心してコンテンツを信用することができます。
このように、検索ユーザーの視点からコンテンツの設計や品質を高めることを怠らないようにしましょう。
なお、「E-E-A-T」の概要や各要素を高めるための具体的な施策などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)TDHを意識する
コンテンツに関しては、品質はもちろん、形式面でも最適化を行うことを意識しましょう。
TDHとは、コンテンツ制作において必要となる要素をいい、具体的には以下のようなものを指します。
- T(Title):タイトル
- D(meta description):メタディスクリプション
- H(hタグ):見出し
メタディスクリプションとは、検索結果に表示されるコンテンツの説明文です。
これらの中には、検索キーワードを含めておくことが重要です。
また、これらの要素に検索キーワードを適切に含めておくことは、検索ユーザーに対して、どのような情報が掲載されているかを示すことにもなります。
これによって、ユーザビリティを向上させる効果も期待できるのです。
メタディスクリプションの意義や具体的な書き方のポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、hタグがSEO上で持つ役割や設定方法、ルールなどの詳細については、以下の記事もぜひご覧ください。
(3)モバイルフレンドリーの対応を行う
アルゴリズムのアップデートに伴い、現在ではモバイルフレンドリーの対応を行っているWebサイトが優先的に上位表示されるようになっています。
そのため、モバイルフレンドリーの対応が完了していない場合には、対応を直ちに行うことが重要です。
具体的には、レスポンシブ対応を進めると同時に、文字の大きさや改行などにも注意を払って改善を進めましょう。
モバイルフレンドリーの対応を行うことで、SP(スマホ)ユーザーの離脱を防ぎながらアクセス数を増加させることができます。
(4)ページの表示速度を改善する
ページの表示速度を改善することは、ユーザビリティを向上させる上でも重要といえます。
表示速度が遅い場合には、検索ユーザーの離脱につながってしまいます。
例えば、表示速度が遅い要因としては、以下のようなものが挙げられます。
- サーバーの応答速度が遅い
- 画像データのサイズが大きい
- HTMLやCSSなどが最小化されていない など
これらについて、1つずつ改善していくことで、ページの表示速度を改善させ、ユーザビリティを改善させることにもつながるのです。
なお、ページの表示速度を改善させるツールの使い方や具体的な改善施策については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(5)サイトの構造を最適化する
Webサイト全体の構造やディレクトリを見直し、最適化を行うことも検索アルゴリズムを意識した対策として有効です。
サイトの構造が複雑で、階層が深くなればなるほど、検索ユーザーは欲しい情報にたどり着きづらくなります。
そうなると、ユーザビリティが著しく損なわれ、ユーザーの離脱と順位の低下を引き起こしかねません。
これを回避するためには、サイト構造をできるだけシンプルにし、検索ユーザーにとって必要な情報がどこに配置されているかを明確にすることが重要です。
具体的には、パンくずリストやサイトマップなどを配置して検索ユーザーにサイト構造を示すような工夫が必要となります。
また、関連するコンテンツどうしを内部リンクによってつなげることもユーザビリティ向上のためには有益です。
このような対応を行うことは、ユーザビリティだけでなく、クローリング対策のためにも効果的といえます。
ユーザビリティを高めるためのサイト構造の設計方法やポイントについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
5.中長期的に検索順位を維持するためのポイント
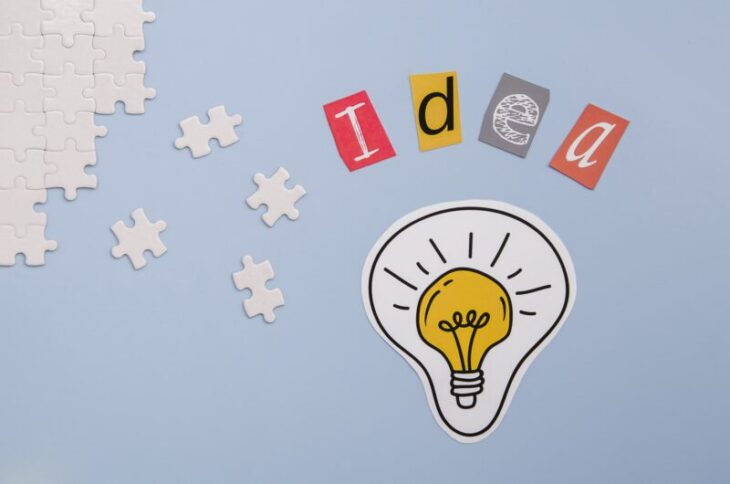
Googleの検索アルゴリズムのアップデートが行われる際には、あらかじめ通知がされます。
そのため、内容を把握することで、自社のWebサイトやコンテンツにどのような影響が生じる可能性があるのかを分析・把握することが重要です。
もっとも、アルゴリズムには具体的な指針や答えがない場合もあり、分析と検証を繰り返しながら対策を行うことが求められます。
どのようなアップデートが行われたとしても、以下の点を意識することも重要です。
- アップデートに過剰反応せずにユーザー目線を意識する
- 独自性のあるブランディング戦略を策定する
- コンテンツのリライトを定期的かつ継続的に行う
順にご説明します。
(1)アップデートに過剰反応せずにユーザー目線を意識する
アップデートが公表されたことに過剰に反応し、コンテンツの修正や改善を急ぐことには慎重になりましょう。
アルゴリズムのアップデートが行われたからといって、直ちに検索順位に影響が及ぶわけではありません。
そのため、まずは分析ツールなどを用いて、具体的に検索順位にどのような影響が生じているのかを把握することが重要です。
アップデート情報に過剰に反応することで、コンテンツに手を加えると、かえって検索順位に悪影響を及ぼしてしまうリスクもあります。
また、Googleの検索アルゴリズムとしては、検索ユーザーにとって有益なコンテンツを評価するという基本方針が揺らぐ可能性は低いです。
そのため、ユーザー目線を重視したコンテンツ制作を意識することが最も重要といえます。
検索アルゴリズムへの対策はあくまで手段であり、その目的はユーザーの満足度を向上させることに尽きることを忘れないようにしましょう。
(2)独自性のあるブランディング戦略を策定する
競合にはない自社独自のブランディング戦略を策定することも重要です。
先ほども述べたように、検索アルゴリズムにおいては、オリジナリティのあるWebサイトやコンテンツが評価され、上位表示が行われる傾向にあります。
また、検索ユーザーもインターネット上の情報については、その内容はもちろん、誰が発信を行ったものであるかという点を評価するようになってきています。
そのため、競合他社にはない自社のオリジナリティを前面に押し出したコンテンツ制作がこれまで以上に求められているといえるでしょう。
(3)コンテンツのリライトを定期的かつ継続的に行う
検索結果の上位に自社のWebサイトやコンテンツが表示されるためには、常に検索ユーザーの意図や求めている情報の分析・最適化が欠かせません。
そのため、定期的かつ継続的なコンテンツの改善も重要といえます。
具体的には、品質の低いコンテンツや情報が古いページについては、定期的にリライトおよび更新を行うことがおすすめです。
コンテンツの最新性や情報の網羅性を担保することで、アルゴリズムのアップデートが生じたとしても、検索順位の変動に対する影響を最小限に食い止める効果も期待できます。
また、過去に検索エンジンから評価を受けていたコンテンツも定期的にリライトや情報の追加を行うことで、SEO評価を下げることなく品質を維持し続けることにつながるのです。
このように、定期的かつ継続的なリライトは、コンテンツの品質を向上させることはもちろん、高い評価を得ていたコンテンツの価値を維持し、サイト全体の評価を維持・向上させる効果も期待することができます。
まとめ
本記事では、Googleの検索アルゴリズムに影響を及ぼす要素や効果的なSEO対策の方法などについて解説しました。
アルゴリズムは定期的にアップデートが行われ、その内容に更新や修正が加えられるため、検索順位を意識した対策を行うためには、まずはアップデート内容をフォローすることが必要不可欠です。
もっとも、Googleの検索アルゴリズムを念頭に置きながら自社のWebサイトやコンテンツの最適化を図るためには専門知識が必要となります。
アップデートの影響を最小限に抑えながらSEO効果を高めるためには、専門の業者やコンサルタントに依頼するのがおすすめです。
そのような場合には、TMS Partners株式会社にご依頼ください。
弊社は、Webサイトの効果的なSEO対策をはじめ、サイト制作・改修や広告運用など、幅広い支援を行い、実績も豊富です。